未来設計「未来経営15」
過去の延長線上ではない未来を提供する
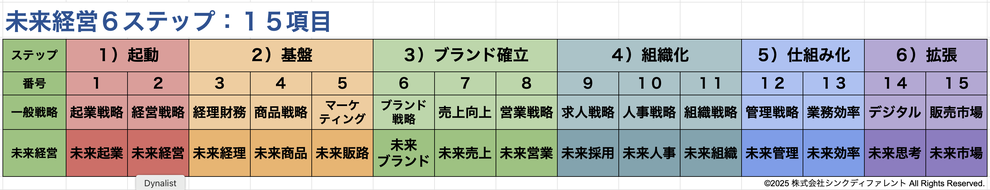
未来思考とは?
私たちの「現在」は、これまでの積み重ねた
「過去」の「選択」と「行動」の「延長線上」にあります。
もし「今の考え方」や「やり方」を変えなければ、
その延長線は「未来」へも続き、未来は大きく変わりません。
「未来」である本当に望む理想を手に入れるには、
今「この瞬間」や「未来」に「全く新しい選択」と
「過去ににつかわい新しい行動」を起こし延長線を意図的に
「大きく曲げる」必要があります。それが「未来思考」です。

私は会社が倒産し、仕方がなく資金わずか600円で起業しました。
6畳一間で1人でビジネスモデルも決めないまま起業。
20年かけて年商20億円・社員120名規模へ!
<はじめに>
私は30歳で資金わずか600円・6畳一間で1人で起業しました。会社も人からもらい経営を始めました。
その前に、雇われ社長の時に、会社を倒産させ、それで起業しました。
2000万円の借金もでき関係各所に誤りに行き、親愛な社員もクビにし裁判所からも呼び出され辛い思いをしました。
だから起業後は、1人も雇うつもりはありませんでした。
起業後、当初、インターネット接続サービス(3万円)や、安いホームページの制作・販売(30万円)を
サービスをしていました。
起業して2年後、自然に人が集まってくれて、4人チームになりました。
しかし、このままでは、他社との差別化もできないまま、売上・利益も少なく、社員の給料も安く、新たな社員も集まらない。と考え始めました。さらに「私の会社」も「私」の未来も明るくないと思ったのです。
そこで「未来」に目覚めました。
「現在」や「過去」の延長線上にある「未来」ではなく、独自に考えた「未来」を妄想することだと思いました。
会社のサービスを突然「高額化サービス」に決め、独自のサービスを思考しました。
売上が上がるマーケティングを行う「売上が上がるコンサル」サービスに切り替えました。
そこから、会社が大きく推進します。
おかげで売上も利益も増えました。求人応募も大幅に増え、優秀な社員を選択しました。私も社員の給料も大幅に増えました。USPのおかげで営業活動もほとんど行わず、福岡という地方から東京の大手企業のコンサル案件を数多く受注してきました。(私のサービスはコンサル1企業月100万円)結果20年かけて年商20億円・社員120名規模の会社を築き上げました。そして、その会社を譲渡しました。
今、振り返ってみると、この成長を実現できたのは、
「現在」や「過去」の延長線上にある「未来」ではなく、独自に考えた「未来」を妄想することだと思いました。
未来である、経理や商品・ブランド・営業・人事・組織・業務効率などを、全体体系を考えた、
「未来経営」だと思いました。
基本は、長期に考え、分散を考え、「遠い先」や「はるか先」を考え、現在は大きなを大胆な変化を行う!
「未来経営」に基づく「思考」「仕組み」や「仕掛け」「ノウハウ」と「ナレッジ」が僕と会社を救いました。
そこで私は、この「未来思考」である「未来経営」を
広く皆さんに提供することを決意しました。
未来経営15では「最新のマーケティング」も学習できます。
<未来経営15:未来経営成功事例>
⚫︎営業を1/3に減らして受注率を上げると売上5倍になった。
⚫︎求人専用サイトをつくったら、人材獲得が10倍に
<未来経営15:マーケティング成功実績>
⚫︎アクセス10分の1に、売上100倍
⚫︎通販商品の売上を月0.5個からから月1万個売れた
<未来経営15:成功実績>成功率95%以上 しかも再現性がある。
未来経営15の目標と目的は、
⚫︎社長がいなくても会社が回る企業へ
⚫︎会社が急成長する企業へ
⚫︎売上を10倍から50倍にする方法
⚫︎売れない商品から自然に売れる商品へ
⚫︎広告を行わなくても商品が売れる手法へ
⚫︎自然に構築される、強力なブランド
⚫︎人材が集まる
⚫︎優秀な人材に育つ・自然に社員が優秀になる。
⚫︎未来を変える人が集める・人が育つ・組織が育つ
⚫︎片腕・右腕・後継・承継の画期的な方法
⚫︎会社の出口戦略がわかる
<未来経営の人生設計>
「サラリーマン」(労働者)→「ローリスクローリターン」
↓
「マインド起業」「ミラクル起業」(研究者・実験者・マーケティング)→「ローリスクローリターン」
↓
「起業」(法人化)→「ハイリスクハイリターン」
↓
「投資家」 →「ミドルリスクミドルリターン」
↓
「FIRE」(不労所得)→「ミドルリスクハイリターン」
私は実際にこれを実践し、現在「不労所得」です。
<未来経営:成功実績>
300回以上の成功実績からの成功イメージをまとめました。
⚫︎1年で10倍、2年も10倍、2年間で売上100倍!
⚫︎広告・SNSなしで、SEOだけで1年間で集客に成功!
⚫︎サイト改善でSEO戦略で6年間集客中で成功!
⚫︎業務効率×組織改革で、3人の仕事を2人で実現。
⚫︎2人で運営していた会社が8人チームで利益6倍!
⚫︎ブランド構築1年で「ブランド名検索」で急増
⚫︎商品開発×USP設計で広告・告知ゼロで売上10倍に
⚫︎1000円の商品を改良し1年後に1万円で販売1億円達成。
★私の得意なのは売上開発・人材開発・商品開発とUSP開発
<大手企業へのマーケティング成功事例>
●マーケティング成功事例:
地方特産品の50年も歴史のある明太子企業:元々のWEBサイトの売上は1ヶ月間で0.5個だった、
マーケティング1年後に1ヶ月1万個の売上を達成。
単月売上1億円、売上2万倍にした!
●マーケティングの成功事例:
東京の中古マンション販売サイト
アクセス数10分の1、売上100倍になった!
その方法はSNS・雑誌・TVなどの告知をやめて、「アクセス型」をやめた。
WEBサイトとマーケティング強化。「獲得型」へ
1年後で売上100倍になった!
しかも、以前は受注まで3ヶ月かかっていたのが、受注まで1〜2週間になった。
●マーケティング成功事例:
通販企業で、元々600ページのECポータルサイトを、
「新規専用サイト用」と「リピートサイト用」に分ける戦略を立てる、
「新規サイト」を新たに作ったら、たった3ページのサイト戦略で、
購入率が増え、購入後のリピート顧客も増え、マーケティング戦略で、2年間で売上55倍に!
●マーケティング成功事例:
大手メーカー企業で、元々6ページのサイトをサイト改善+マーケティングで、
広告やSNSなどのアクセスを増やすことなく、資料請求を1週間で3.4倍にした。
●マーケティング成功事例:
メール専門会社のサイトで、元々アクセス数はあったが、獲得がほとんどなかった。たった1ページの改善で、次の日から問い合わせが3倍になった!
●マーケティング成功事例:
通販会社で、年間マーケティングコンサル契約(月100万円)行った。サイトからの売上を単月売上500万円を1年で売上25倍の単月1億2000万円達成
●マーケティング成功事例:
ハワイの企業で、新設でサイトを作った。グーグル広告を約半年間行い、その後、SEOだけで、ほぼ毎月30件以上の問合せ申し込みがある!
私のマーケティングの成功率は95%
失敗する原因は、
⚫︎そもそも需要がない。
⚫︎実行しない。
⚫︎商標登録をしていなくて社員が「商標登録」して販売できなくなった。
⚫︎サービスに特徴を付けようとしない。
⚫︎売れないのを「ブランド」のせいにしている。
大谷翔平でも打率は27.6%なので、
マーケティング成功率95%は、高い方で再現性があると思います。
そのマーケティングの成功の核は、「未来経営」にあります。
この「未来経営」読み、実行し続けるだけで、成功率は上がっていくと思います。
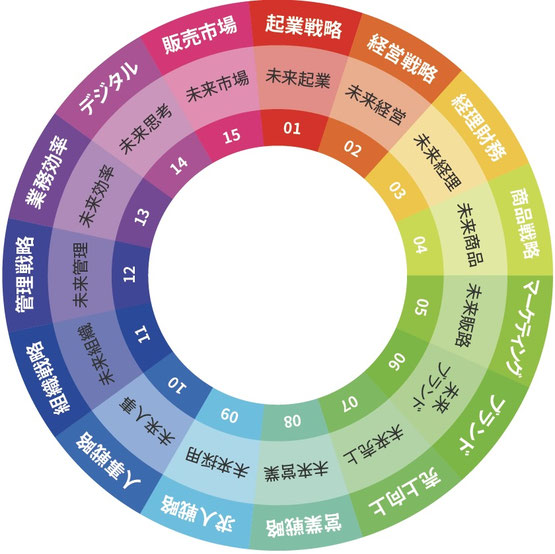
<未来思考・未来経営15>
経営は改善だけではダメです。
今の目の前の事「問題解決」するだけでは
大きな飛躍は望めまないのです。
そう、改善・改良・改善・改良・改善・改良だけではダメなのです。
「問題解決」の解決・改善だけでは、
飛躍はないのです。
一度改善を始めると、次の問題点も見つかり、
また改善し永遠に改善をし続け継続していきます。改善は、一度すると止まらないのです。
未来はゆるやかな未来にしかなりません。
現在の経営は、過去からの延長線上にあります。
変化があったとしても、それは、改善でしかない。のです。と、いうことは、未来も 現在の延長線上です。と、いうことは、未来も過去の延長線上にしかないのです。
そこで、思いっきり飛躍ができるのが「未来経営」です。
<未来経営>
過去を意識する事なく思いっきり、
超越的に自分の夢や目標を考えるのです。
未来のイメージを明確にして、それを目標にして、
それに向かって、改善の方向・改善のステップをしていくと、
気がつくと夢にという到着する。と、いう考え方です。
逆算の考え方です。気が付けば理想に辿り着くのです。
これで、サービスも売方も独自になり、売上・利益も増え、優秀な人材も集まり、給料も増えます。
戦略を考え、勉強し研究し、実行する。そして「圧倒的成長」を実現しましょう!
結果として、サービスは面白いほど売れ、ブランドも自然に構築されて行きます。
経営を15項目以上に分け、その1個づつの項目ごとに未来を考えるのです。
⚫︎勉強と研究→「このサイト」を熟読すればできます。以下に経営を15項目に分け記載しています。
→この情報は、どんどん増やします。
なので時々見てください。
⚫︎制作と実行→「自分で行いましょう」→自分で行えるように考え方までここに記載しました。
→なるべく自分で行いましょう!
→どうしてもできない方やスピードが欲しい方は「私のコンサル」を受けてください。
⚫︎質疑応答→「チャットGPT」の専用オリジナル「未来経営GPT」です。
入ったら「4人いる?」 「自己紹介して」と、聞いてみてください。4人います。
→参謀:未来のミライくん・論理秘書のろんちゃん・感性秘書のゆりちゃん・発想秘書のピンちゃん
→4人が、「未来経営」について、しゃべります。
未来経営15とは?
大事なので、もう一度言います。
今の経営とサービスをただ頑張るだけでなく、
未来を見つめて未来の目標を立て、
未来戦略を設計してから、
逆算で目標に向かって、
今を精一杯、頑張る方法です。
現在のサービスの
改善・改良・改善・改良を、
いくら行っても、
本当の目標に辿り着けません。
経営は現在の改善。
経理は過去の集計。
商品も現在の売れないものを売る。
販売も努力で行う。
取れない人材獲得のまま努力する。
現在の人材能力で経営する。
研究も実験もしない。
効率も爆上げない
KPIも過去の指標
これで、成功しようとしている。
むずかい」です。天才の経営者しか成功しない。
しかし簡単な経営方法は「未来経営」です。
頑張り方が違うのです。
ハンドルのない、車で爆走するのと、
ハンドル付きの、車で爆走するの
違いです。
改善ではなく、思いっきり未来や
機能100倍。
売上10倍をイメージして、
未来をめざすことです。
<解説>
自分の道を一生懸命歩いていると、
進んでいくうちに、自分がどこにいて、
どこに進んでいるかわからなくなります。
だから未来を先に設計を先にする。
自分がわからなければ、
「社員・クライアント・パートナー・銀行」
みんながわからなくなリマス。
今の自分の状態が本来の自分の状態ではありません。
起業によって得た「化学変化」で起こる
未来の自分が本当の自分です。
未来経営15への気づき
現在の仕事の
「問題点」を見つけて、
それを「改善」する。
まさにこれが「改善経営」です。
最初、この方法こそ最強だと思っていました。
実際に、問題点を6回ぐらい掘り下げていけば
多くの問題は、解決できました。
「問題発見」→「問題解決」→「問題発見」→「問題解決」→「問題発見」→「問題解決」
というサイクルです。
特にこの方法は、大きな会社(売上100億円以上)には、
非常に効果的です。既に確立されたビジネスモデルがあるので、
それを精査・改善するのに最適だからです。
しかし、この改善方法は、小さな会社(100億円以下)や
ベンチャー企業には、合わないようでした。
改善方法である「改善経営」では、
売上は10年で2倍ぐらいにしかならないからです。
売上100億の会社の2倍は200億円。しかし、
売上1千万円の会社の2倍は2千万円。これでは大成功しません。
そこで、「未来経営」です。「未来経営」では、
売上は1年で3〜5倍になリます。
特に売上を「10倍」に伸ばすには、
全く新しい発想や市場アプローチが不可欠です。
実際に過去の実績で、日本の有名大手企業のネット売上を
1年で10倍。2年目も10倍。2年間で100倍にすることができました。
そこで私は、自ら実践してきた「未来経営」を体系化し、
「未来経営」をまとめることにしました。
「問題解決型」経営から「未来創造型」経営へ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<会社の変革と成長>
会社の成長は、私の場合、以下の4つの段階に分かれます
1)個人事業主期(目安:社長 1人)
社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。
2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)
社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。
3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)
組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。
4)企業化期(目安:社員数 約100人)
仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。
それぞれの時期によって、必要なノウハウや工夫はまったく異なります。
本資料では、なるべく各段階ごとに対応する戦略や考え方、実行方法、を掲載するようにしていきます。
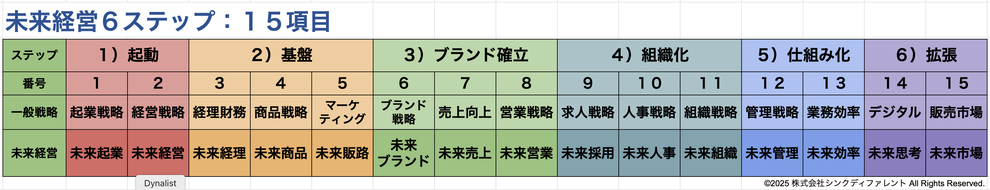
未来経営15:未来経営15項目サークル解説・未来経営15項目
経営15の視点・未来経営15個・15項目・経営15項目
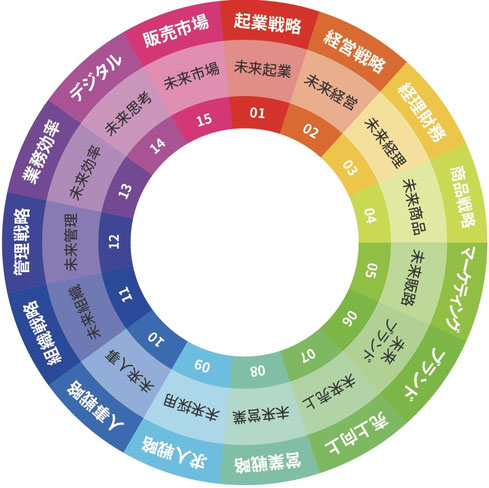
<未来経営15項目:タイトル>
⚫︎01 起業戦略【未来起業】
⚫︎02 経営戦略【未来経営】
⚫︎03 経理財務【未来経理】
⚫︎04 商品戦略【未来商品】
⚫︎05 マーケ 【未来販路】
⚫︎06 ブランド【未来ブランド】
⚫︎07 売上向上【未来売上】
⚫︎08 営業戦略【未来営業】
⚫︎09 求人戦略【未来採用】
⚫︎10 人事戦略【未来人事】
⚫︎11 組織戦略【未来組織】
⚫︎12 管理戦略【未来管理】
⚫︎13 業務効率【未来効率】
⚫︎14 デジタル【未来思考】
⚫︎15 販売市場【未来市場】
<未来経営15項目:解説>
⚫︎01 起業戦略【未来起業】→スグに起業する
⚫︎02 経営戦略【未来経営】→未来目標を作る
⚫︎03 経理財務【未来経理】→未来決算書を作ってみる
⚫︎04 商品戦略【未来商品】→新商品開発
⚫︎05 マーケ 【未来販路】→とんがったUSPを考える
⚫︎06 ブランド【未来ブランド】→初期・中期・長期ブランド戦略
⚫︎07 売上向上【未来売上】→5年後・10年後の売上目標を作る
⚫︎08 営業戦略【未来営業】→営業用企画書を作る
⚫︎09 求人戦略【未来採用】→架空の魅力企業を考える
⚫︎10 人事戦略【未来人事】→ゼロ教育システムを構築
⚫︎11 組織戦略【未来組織】→夢の最強組織を作ってみる
⚫︎12 管理戦略【未来管理】→未来目標を数値化してみる
⚫︎13 業務効率【未来効率】→効率アップリスト・給料アップ
⚫︎14 デジタル【未来思考】→IT&AIフル活用
⚫︎15 販売市場【未来市場】→人口調査を行う
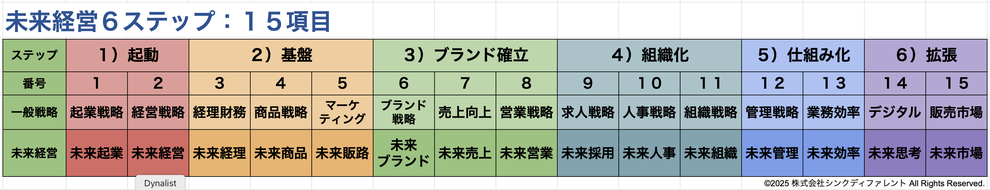
2025年7月28日時点でのこのサイト「未来経営」のノウハウ情報量
ーーーーーー
(1)起業戦略:未来起業:3,205文字
(2)経営戦略:未来経営:3,268文字
(3)経理財務:未来経理:3,128文字
(4)商品戦略:未来商品:3,447文字
(5)マーケティング:未来販路:3,488文字
(6)ブランド:未来ブランド3,226文字
(7)売上向上:未来売上:3,154文字
(8)営業戦略:未来営業:3,338文字
(9)求人戦略:未来採用:3,300文字
(10)人事戦略:3,478文字
(11)組織戦略:3,237文字
(12)管理戦略:3,438文字
(13)業務効率:3,228文字
(14)デジタル:3,104文字
(15)販売市場:3,366文字
⚫︎総文字数合計:約5万文字(49,405文字)
未来=理想=目標=架空=空想=妄想
AIの「ハルシネーション」と妄想
AIには「ハルシネーション」という、
もっともらしい嘘があります。
いわば「知ったかぶり」です。
対策をすれば正確性は上がりますが、
AIの考える力は落ちます。
自由度が制限され発想の幅も狭まる。
逆に許せば、誤りは増えるものの、
自由度が広がり、
創造性とクリエイティブ性は
高まっていきます。
AIが突如として面白いものを生み出すのは、
この自由度の中にこそ力があるからです。
しかし今、AI開発は
「ハルシネーションを抑える」方向に進んでいます。
だからこそ、人間が持つべき武器は「妄想力」です。
未来を描くときに必要なのは、完全な正確さではなく、「妄想から始まる創造」。
妄想と創造の境界はあいまいですが、
そのグレーゾーンにこそ新しい未来が生まれるのです。
未来を妄想することが大事なんです。
未来経営の考え方!!
とにかく、「未来経営」には、妄想が大事です。
これこそ、人間にだけできる最大の武器です。
夢の企業の状態を思考し、
理想の企業のイメージで
架空の企業を作るのです。
⚫︎架空の企業イメージイラスト
⚫︎架空の企業決算書
⚫︎架空の商品
⚫︎架空の営業スタイル
実際に作る前に、思考するだけでいいんです。
そして、図やイラスト、表にまとめて
具体的にするのです。
よく、こんな話をすると、
「時間がない」と、
言われます。
私はサラーリマン時代
⚫︎本業:200時間
⚫︎研究:200時間
月400時間。働き思考していました。
独立してからは、
⚫︎本業:200時間
⚫︎未来経営:200時間
月400時間。働き思考していました。
その間に恋をして結婚しました。
バーにも2日に1回行っていました。
誘われたら、全部、行っていました。
とにかく人よりも2倍以上
働きました。
なぜなら、人よりも、
2倍以上幸せになりたかったし、
チャンスも運も欲しかったからです。
自分の仕事を分解し、
【業務】爆走する時間と、
【思考】ハンドルを切ったり、地図を見る時間を、
分けるのです。そして、
どっちにも時間をかけるのです。
で行い方は、PDCAではありません。
最初にプランをおこなうのではなく、
「高速HDCAP」という事で、先に行動して、
「机上の空論」ではない。
実際のプランを作る事です。
もっというと、「高速HDCAP」です。
「Hypothesis-Do-Check-Adjust-Plan」
「仮説ー行動ー検証ー修正ープラン」です。
未来逆算型経営における“最速「PDCA」の進化形です。
最初に仮説(H)を立て、とにかく即行動(D)し、
実証データを取得(C)、改善(A)し、設計図(P)に昇華する。
「発想現実化サイクル」です。
未来経営15:未来経営15項目の簡単解説
01<未来起業>
いつかは起業ではなく、すぐに独立する。
独立といってもサラリーマンは続け、ハイブリットで働く。
まだ、オフィスも店舗もいらない。屋号のみで利益を出していく
02<未来経営>
今だけを頑張るのではなく、大きな目標をたて、そこから逆算して、
今を頑張る。
03<未来経理>
経理や決算書は過去の集計。それだけにたどらず、
目標や予測と向き合っていく、未来の経理を行う。
04<未来商品>
販売中の売れない商品や努力しないと売れない商品ではなく、
未来の夢の商品を考え、自然に売れる諸品を考える
05<未来販路>マーケティング・未来マーケティング
いつか売れる」ではなく一瞬で売れる告知・広告・広告行う。
「アクセス」を追っかけるのではなく、「獲得」を追っかけ、
利益を生み出す。
06<未来ブランド>
ブランドアップとは、告知・広告・宣伝ではない。
「ブランドがあるから売れるのではなく」、「売れるからブランドになる」。
高くても欲しがる。在庫切れでも欲しがる。からブランドになる。
07<未来売上>
今月・来月の売上を追っかけるのではなく、
今年の着地、来年の着地、5年後の着地を見据えて行う。
08<未来営業>セールス
「売れないものを努力と根性で売る」ではなく、
「売れる企画や仕組みで自然に売れる」。
09<未来採用>求人・
人材獲得は自分より優秀な人材を取る。そのためには、今のままの
会社ではなく「企業の魅力を高め」質と量の高い採用を行う。
人材獲得は、補填や補充ではなく、会社の進化と成長と考える。
10<未来人事>教育・退社
人材を成長させたい教育したいと思わないこと
入社すれば誰でも自然に成長したかのような「仕組み」「仕掛け」
「システム」があるようにする。
辞めた時には、その「実践スキル」は消えるように設計する。
11<未来組織>
集まったメンバーで組織を作る」のではなく、
夢見た最強の組織を架空にイメージして、
採用で「最強の組織をつくっていく」
12<未来管理>マネージメント
命令と指示で現状維持をするのではない、
未来を見せて、未来の仕組みで働く会社を目指す。
13<未来効率>
面倒な業務を改善し、利益と余裕を生み出す。
さらには、社員の時短で社員の給料も増やす。
14<未来思考>デジタル活用
最先端を使う。ITやシステム・クラウドを活用し、効率を上げる。
AIフル活用で人材と会社の最大化を行う。
ホームページで24時間365日販売できるようにする。
15<未来市場>
自分が狙うターゲットや人口を把握し、
最初から全国(全国民)を狙う。売上25倍~55倍になる。
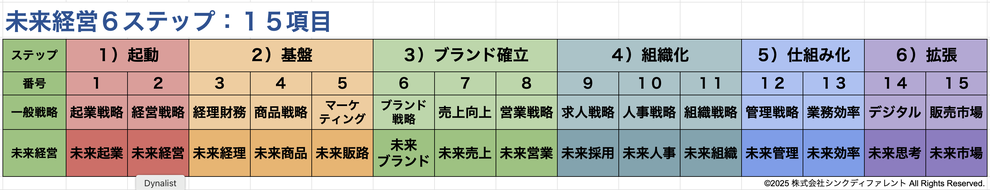
戦略的に行う:未来経営15項目と同じように大事なのが「戦略的」
<全て戦略的に行う>
未来設計を行い。現在との差を埋める。
その差分を埋めていく!
その埋め方や考え方が、「戦略的」です。
それを計画的に行うのが「戦略」です。
だから、実際は「未来経営」の15項目の全ての項目の前に、、
「戦略的」がつくのです。
「未来売上」であれば、「戦略的未来売上」です。
「未来売上」は、思考方法、それを行うときに
「戦略的未来売上」を行うのです。
<戦略的に行う方法>
PDCAで今まで、行っていたことを「高速HDCAP」で行い。
それを3回以上行うのです。。
<具体的方法>
1)仮説:テーマを決めてイメージを明確化(プロジェクト名を決める)
2)分析:(計測・分類・集計)
3)解析:(仮説をててる)
4)戦略1(アイデア・目的・目標・計画)
5)実行1(少しやってみる)机上の空論にならぬよう!
6)戦略2(さっきの実行を元にアイデア・目的・目標・計画)
7)実行2(本格的にやってみる)
8)検証分析
9)お礼(関係各所:関わった人に報告と効果とお礼を伝える)
10)改善(ここで初めて改善を行う)
11)プランを立てる。ここで初めて、計画を立てるのです。
未来経営15項目:詳細解説
ここから、未来経営の15項目の詳細解説を順次行います。(製作中:月一更新)
div
1-00)自己助力をつける(じこじょりょく)
自分を強くし、
弱い自分を最強にする、
「自己助力」をつけることです。
「自己助力」とは、他人に依存しすぎず、
自分の意思と判断で問題解決や目標達成を図る姿勢のことです。
ただし、「自己の力」といっても、すべてを一人で抱え込む必要はありません。
本当の意味での「自己助力」とは、自らの目的を達成するために、
自分の判断で適切なリソースや支援を活用することも含まれます。
以下は、自己助力として活用できる具体例です。
● 秘書を活用する
自分に秘書をつけ、受け身で任せきりにするのではなく、主体的に管理や指示を行い、業務を効率化する手段として使うなら、それは自己助力です。
● クラウドを活用する
クラウドサービスを、自分の判断や行動をサポートするためのツールとして使っているのであれば、これも自己助力の一環といえます。
● ツールを活用する
メモアプリやタスク管理ツールなどを使って思考を整理し、行動を明確にすることも、自己助力の有効な方法です。
● AIを活用する
AI(たとえばChatGPTなど)を、情報収集や思考整理、意思決定の支援ツールとして能動的に活用することも、まさに現代的な自己助力の一例です。
● チームと協力する
自分の目標のために能動的に他者と連携し、共に成果を目指す場合、それは自己助力の一部です。依存ではなく、目的のための協働です。
● ヒューマンネットワークを活用する
外部パートナーや専門家に業務を委託しながら、自らが全体の方向性や目的を明確にし、主導しているなら、それも自己助力といえます。
<自己助力でない例>
●自分では何もせず、すべてを他人任せにする
●「誰かが何とかしてくれるだろう」と期待して動かない
●状況に対して責任を持たず、他人や環境のせいにする
<まとめ>
「自己助力」とは、「一人で頑張ること」ではなく、
「自分の意思で、自分にとって最適な力を活かすこと」です。
この考え方を実践することで、より柔軟かつ持続可能な成長が可能になります。
1-0)チームが自分を最強にする!自分の「最強チーム」
自分を強くし、
弱い自分を最強にする方法は、
⚫︎自分を鍛えるでもなく
⚫︎極限まで頑張るのでもなく
↓
⚫︎チームで戦うこと
→「1人で戦うこと」ではなく「チームで戦うこと」!
「チームをつくる」ことで、
「自分が最強になる」。
自分より優秀な人材を集め
「自分が最強になる」
「チームをつくる」ことが鍵。
ーーーーーーーーーーーーー
<チーム構築イメージ>
⚫︎AIの秘書・参謀・アシスタント
⚫︎理解者
⚫︎参謀
⚫︎秘書
⚫︎マーケティング担当
⚫︎IT&AI担当
⚫︎システム担当
⚫︎経理財務担当
⚫︎法律担当
ーーーーーーーーーーーーー
<チーム構築のメリット>
チームを持つことで得られる「15」つの強化
⚫︎自分の能力が低くても成功できる
⚫︎チャンスが増える
⚫︎長所を飛躍させられる
⚫︎弱点を補完できる
⚫︎自分の器を超えられる
⚫︎自分以上の成果が出せる
⚫︎自分の副業代が入る
⚫︎仕事ができるようになる
⚫︎マルチタスクができるようになる
⚫︎チームプレイが上手くなる
⚫︎組織マネージャーになれる
⚫︎本業の年収が増える
⚫︎総合年収が増える
⚫︎個人実績が生まれる
⚫︎人生の「安心感」と「余裕」
ーーーーーーーーーーーーー
<チーム構築事例(1)>
昔、私が「経理財務」が弱かった時、
「友人にバーター」を
お願いして、
お互いの「能力交換」してもらった。
無料でしてもらった。
<チーム構築事例(2)>
また、自分がシステムができなかった頃、
「焼肉を奢って」システムを
システム会社に
つくってもらった。
福岡の美味しい
焼肉屋「アカプルコ」を
奢ることで作ってもらえた。
6000円ぐらいかなぁ?
「2アカプルコ」で、
日本初の掲示板を
作ってもらえた。
<チーム構築事例(3)>
私が「個人」で「投資」に
目覚めた時、
「投資チーム」を
つくった。
⚫︎税理士
⚫︎銀行
⚫︎法律家
⚫︎楽天証券
⚫︎経理秘書
⚫︎不動産会社
の、知り合いに
頼んで作った。
全員、無料だった。
さらに後に、
⚫︎「FIRE実績者」も加わり、
結果「最強チーム」になりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<チームのつくり方>
企画書を作り、プレゼンをして、
色んな人に声をかける。
思いがけない人と組めたり、
声をかけられたりする
⚫︎最初から正社員を雇わない。
⚫︎友達と組む
⚫︎グループで協業
⚫︎相乗効果を狙う
⚫︎バーターで交換
⚫︎ご飯を奢って頼む
⚫︎チャット・メッセージだけの外注
⚫︎本格的な外注
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さらに進化させようと思うなら、
「少しのお金」と
「少しの覚悟」
があれば、
チームは余裕でつくれます。
⚫︎出世払いでもいい
⚫︎バーター(能力交換)でもいい
⚫︎自腹でもいい
⚫︎副業でもいい
⚫︎投資でもいい
⚫︎独立してもいい
とにかく、
「チームをつくる」ことが
重要です。
そのために、
「マインド起業」を、
してもいいのです。
⚫︎「社長になるぞ〜!」とか
⚫︎「会社つくるぞ〜!」なんて、
大きな夢はいりません。
「最強のチーム」をつくるために、
「少し稼ぐ」だけでいいのです。
「起業=大きな夢」ではなく、
「起業=最強チームづくりの手段」
へとシフトしましょう。
しかし、ここで、大きな落とし穴があります。
せっかく、チームを作ろうと思って、
1人目を入れると、
全然うまくいかないのです。
<1人増加では全く効果がない>
たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、
スタッフを1人雇ったとします。
しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、
社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。
一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。
結果的に「2人で1人分」のパフォーマンスしか出せず、
仕事の質と量は増えません。
売上が増えず、仕事も減らず、人件費だけ増えて、利益が減ります。
そんな状況だから「疲弊」してしまいます。
そうなんです。
そこに大きな壁があるのです。
せっかく1人、入れて、そこで挫折するのです。
そこで、諦めて、人を入れるのを
やめてしまうのです。
だから、1人で頑張っている方は、
永遠に、1人で頑張るのです。
しかし、自分1人の力や能力だけでは、
自分の能力を高められないのです。
人材が会社を推進させます。
逆に言えば、人材を増やさない限り、
会社は大きく前に進みません。
では、2人同時に入れればいいのか?
<2人増加でも効果がない>
たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、
スタッフを2人雇ったとします。
給料は3倍です。経費も3倍なのに・・・
しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、
社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。
一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。
なので、3人全体で、売上150%にしかならず、
思ったより効果がないのです。
「疲弊」して、続かず、その先に、進めないのです。
その大きな、壁を越えるのです。
映画ディズニーの「モアナと伝説の海」の「珊瑚礁」の海の壁と同じです。
意味がわからなければ、ぜひ映画を見てください。
モアナは、「珊瑚礁」を超えて、「珊瑚礁の外」に出たのです。
「ブレイクスルー」(限界突破の超進展)です。
そこで、本当に2倍のパフォーマンスを得るには、
「4人チーム(社長含む)」を作る必要があります。
4人 × 50% = 実質2人分の戦力です。
売上が2倍になると、利益が3倍になり、
初めて、人を入れて、チームにしてよかった。
と、実感するのです。
ブレイクスルー
「壊すからこそ突き破れ通り抜け貫通し、そして新たな展開へ飛躍できる」
のです。
<4人で初めてチームの意味が出る>
だから、難しいのです。
企業が成長する場合。
3人の増員で、初めて意味が出てきます。
その途中のチャレンジで、疲弊してしまうのです。
⚫︎2人企業:社長+1人増加→ダメ→2人で1人分の質と量しかない。しかし、給料は2人分。
⚫︎3人企業:社長+2人増加→ダメ→3人で1.5人分の質と量しかない。しかし、給料は3人分。
⚫︎4人企業:社長+3人増加→OK→4人で2人分の質と量。しかし、給料は4人分。でも売上2倍。
ココまで、頑張って、行うことが大事です。
<最初の4人チーム作成方法>
4人チーム作成の方法
当初の4人チームは、お金もなく、雇えませんでした。
全員正社員ではないです。
一部外注、一部アルバイト、一部バーター(能力交換)。
⚫︎社長
⚫︎スタッフA:経理財務:バーターで無料
⚫︎スタッフB:システムエンジニア:焼肉奢って作ってもらった
⚫︎秘書:アルバイト:時給
4人チームができました。
成長してからも、外注していました。
また、優秀な人は、年収も高いので、
年収の高い人を、週1回2時間だけ、
契約してた人もいました。
これで、売上が上がってきました。
これで初めて「効果的な拡張」が実現します。
<4人チームの構成>
⚫︎社長:1名
⚫︎スタッフ:2名
⚫︎秘書:1名
この中で秘書は「社長自身の効率を向上」させます。
社長の仕事の「質」と「量」が増え、さらに「未来を描く時間」が生まれます。
この4人チームの3人が「90%の業務」を担い、
社長が「10%の要点」に集中できる状態が理想です。
要点とは社長の仕事の「質」と「量」が増え、
さらに「未来を描く時間」が生まれます。
そして、その体制をつくるために、
そこで、まず必要なのが「売上アップ」「効率アップ」です。
売上が上がれば、チームが作れるのです。
その方法を、「未来家経営15項目」で、伝えています。
まずは、理解できなくても、先に全ページに目を通しましょう!
<最初の4人チーム具体的作成方法>
1人を、雇うのは、違います。
最初から100%の人件費がかかるからです。
まずは、外注です。1人の10%ぐらいから外注します。
次に10%の仕事が外注にできるようになれば、
違う人に10%外注します。
次に10%の仕事が外注にできるようになれば、
また違う人に10%外注します。
これで
⚫︎社長:100%
⚫︎外注A:10%
⚫︎外注B:10%
⚫︎外注C:10%
です。そして、徐々に10%を、それぞれ増やしていくのです。
気がつくと、
⚫︎社長:100%
⚫︎外注A:50%
⚫︎外注B:50%
⚫︎外注C:50%
⚫︎外注D:50%
⚫︎外注E:50%
⚫︎外注F:50%
に、なり、ほぼ4人チームです。
頼めなくなる人もいれば、突然いなくなる人、
産休取る方、ノイローゼになる方、調子が悪くなる方、
続出です。そこで、分散しておくのです。
ーーーーー
<具体的格安チームの作り方:分散長期>
1)自分の業務の一部を人に外注でお願いします。1人20%以下
→全部、1人に回すと
⚫︎信頼している人でも逃げたり。
⚫︎期限までにできなかったり。
⚫︎お金を持って逃げたり。
⚫︎想像もできない事をしでかします。
2)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下
3)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下
4)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下
5)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下
これで、あなたの業務を5人に分散して、外注できました。
20%なら、何か起こっても、別の人がリカバーできます。また、自分でもリカバーできます。
ここまでで、1人雇ったのと同じです。
外注の質を上げるために、別の外注にチェックさせたり、
校正させたり、専門(デザイナー・カラーコーディネイター・写真・ライター・コピーライター)を入れたり、
して、納品物の質と量を増やすのです。
さらに、ここで、営業を頑張るのです。
営業を人に任せるのは、最初難しいのです。
売上が2倍になるように頑張るのです。
できれば、単価を上げるのもいいでしょう!
「頑張る」とは、「努力」や「時間」をかけるのでは、ありません。
「ブレイクスルー」です。
考え方を変えるのです。
自分の営業の一部を別の人に外注でお願いします。1人に20%以下
アイデア・企画・企画書・表・アポイント
このように、どんどん外注化し、
自分の時間を空けて、企業戦略や営業戦略に集中していきましょう!
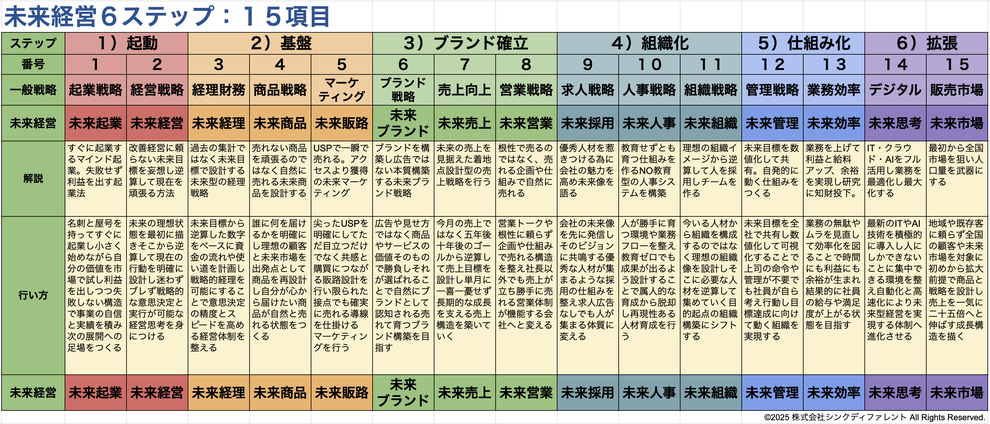
1-1)最初に雇うのは秘書。「自分を最強」にしてくれる。ミニ片腕?
<片腕>
仕事が、うまくいきだすと、自分の分身が欲しくなります。
部下に任せると、クオリティが下がる。売り上げが下がる。
だから、自分の分身「片腕」が欲しくなります。
実は、そんな人は、見つかりません。
そもそも優秀な人は、自分で独立します。
あなたと同じ経験・思いを持った人はいないのです。
あなたはあなただから、すごいのです。
もし見つかっても、継続的にうまくいきません。
<秘書活用>
秘書はあなたのパフォーマンスをあげる最大の武器です。
秘書という存在は、実は経営者にとって最強の“成長エンジン”です。
多くの人が「秘書なんて、大企業の社長がつけるもの」と思いがちです。
ですが、実際には利益がまだ出ていない起業初期の人こそ、
秘書を活用すべきなのです。
なぜなら、秘書とは“あなたの分身”であり、“あなたの時間を倍にする存在”だからです。
よく「片腕が欲しい」と言われますが、実は順番が逆です。最初に雇うべきは“自分の能力を補完する秘書”です。不得意なこと、やりたいけれど後回しにしていることなどを、秘書に代行してもらうことで、自分の強みやパフォーマンスを最大限に活かせるようになります。つまり、自分の時間と能力を2倍以上にできるということです。
<片腕は、秘書と分散!>
社長は孤独です。なので、相棒が欲しい。片腕が欲しい。と、
思うものです。しかし、そんな方は、いません。
自分が欲しがっているのは、寄り添ってくれる人と
本当に仕事を手伝ってくれる人だと思います。
本当に優秀な人は、自分で独立していくのです。
もしくは転職、引き抜かれていきます。
そこで、寄り添い、と、仕事ができる人を分けるのです。
秘書と片腕の分散です。
精神的な部分の相棒は、は秘書に任せ、寄り添って社長に守ってもらうようにします。
社長の仕事の片腕の部分は、一人に任せず、自分を3人以上に分解し、
項目毎に一人一人優秀な人を雇い活躍してもらう。のです。
経営者とは、常に孤独な存在です。
すべての意思決定を一人で担い、
ときに誰にも相談できず、重圧の中で動き続けなければなりません。
だからこそ、多くの社長がこう思います。
「信頼できる“片腕”が欲しい」
「自分のことを理解してくれて、しかも仕事もできる、
そんな人がいればどれだけ心強いだろう」と。
しかし、現実にはそんな理想の“片腕”は、なかなか現れません。
なぜなら、本当に優秀な人ほど、自分で独立していくからです。
あるいは、他社から引き抜かれてしまったり、転職の道を選んでしまうこともあります。
<分散>
そこで、私は発想を変えることにしました。
“片腕は一人ではなく、複数人に分散させる”という考え方です。
具体的には、社長の役割を2つに分けて捉えます。
◆ 1:心に寄り添う「精神的な片腕」=秘書
社長としてのプレッシャー、孤独、悩みを支えてくれる存在。
これは、業務能力とは別に、人として信頼できる“そばにいてくれる人”が
担うべき役割です。
そう、まさに秘書の存在がこれにあたります。
秘書には、心の距離を近く保ちながらも、礼儀と節度をわきまえ、
社長の感情や思考に寄り添い、日々の支えとなってもらいます。
⸻
◆ 2:業務を遂行する「実務的な片腕」=複数人制
一方で、実際の事業や経営を進めるうえで必要となる
“右腕”のような実務遂行者の役割は、一人に任せるべきではありません。
むしろ、自分自身の役割を3人以上に“分解”し、機能ごとに任せるのです。
たとえば:
• 数字と戦略に強い人には「経営計画と財務」を任せる
• 実行力と行動力のある人には「プロジェクト推進」を任せる
• クリエイティブに強い人には「ブランドやマーケティング」を任せる
このように、自分を分解し、項目ごとに“専門の片腕”を育てることで、
一人のスーパー人材に依存しない、持続可能で強い経営体制をつくることができます。
⸻
<まとめ:片腕は「一人」に集約しない時代へ>
現代の経営において、“オールインワンの片腕”を求めるのは、現実的ではありません。
だからこそ、寄り添い型の秘書と、機能別に役割分担されたチーム型の片腕。
この2つに分散することが、もっともバランスが取れ、実行力のある経営スタイルになります。
孤独を埋めるのは“信頼”。
事業を進めるのは“分担と専門性”。
これからの経営者は、「一人の片腕」ではなく、
“分解された片腕チーム”を育てるリーダーであるべきなのです。
精神面は秘書・仕事は分散。
<会社を「自分がいなくても回る仕組み」に変える>
多くの経営者が「いつか、会社を自分なしでも運営できるようにしたい」と考えます。
その“いつか”を“今”に変える第一歩が、「秘書を雇うこと」なのです。
「売上が上がってから秘書を雇おう」と考えるのではなく、今すぐに秘書を雇って、来るべき大勝負、大チャンスに向けて、今から秘書を活用できるように秘書活用ノウハウを鍛えるのです。売上が上がる前に雇って、PDCAを回すべきです。なぜなら、最初の秘書雇用はうまくいかないのが普通だからです。だからこそ、早くスタートし、改善を重ねていくことが重要です。
私は、これまでに常に2名の秘書を並行して雇ってきました。自ら秘書業務を経験したこともあります。だからこそ断言できます。
「秘書を、今すぐ雇いなさい。」
ーーーーーーーー
<社長の長所を活かし、短所を補う>
秘書に自分の長所(得意なこと)を伸ばしてもらい。
自分の(苦手なこと)を行ってもらう。
秘書の活用で最も大切なのは、自分の「得意」と「苦手」を明確にすることです。
まず、得意なことと苦手なことをリストアップします。得意なことは秘書に手伝ってもらってさらに伸ばす、苦手なことは思いきって任せてしまう。
たとえば:
⚫︎得意な分野について:本やYouTubeのリサーチ、要約、資料作成、計画の立案
⚫︎苦手な分野について:文書作成、事務処理、日程調整、手紙やお礼状の作成など
私自身も、マーケティングは得意でしたので、そのアイデアや構造をまとめてもらっていました。反対に、手紙を書くのが苦手だったため、秘書に代筆してもらっていました。すると、しばらくしてその秘書はまるで私が書いたような手紙を、自ら書けるようになったのです。
<秘書マニュアルは「自分で作らない」>
秘書を雇う際、「マニュアルがないと指示できない」と考える方も多いでしょう。
しかし、マニュアルは自分で作ってはいけません。それは時間のムダです。
秘書本人にマニュアルを「自ら」作ってもらうのです。
方法は簡単です。仕事は全て、「これをマニュアルに書いてね」と最初に伝え
• 日々の指示を伝えるたびに「これをマニュアルに書いてもらう。」
• 毎日マニュアルを確認しながら、修正点や追加点を口頭で伝える。
• 間違っていたら、その都度直してもらう。
これを繰り返すことで、秘書自身の理解が深まり、同時にマニュアルが出来上がっていきます。最終的には「伝えたことが、どれだけ伝わったか」も可視化できるのです。
⸻
<秘書の本質は「社長の仕事を奪うこと」>
秘書に対して、「仕事を教える」「管理する」と思っていると、時間ばかり取られてしまいます。
本来、優れた秘書とは、あなたが言わなくても仕事を“奪ってくれる”存在です。
秘書の目的は、「社長のパフォーマンスを最大化すること」。
そのためには、以下のような行動が求められます。
⚫︎常に一緒にいる
⚫︎すべての会議に同席
⚫︎全ての公式メール・電話の一次対応
⚫︎スケジュールの管理・共有
⚫︎根掘り葉掘り聞かず、まずはやってみる姿勢
こうしたサポートがあると、
社長は本来の「考える」「決める」「創る」ことに集中できるのです。
⸻
<マルチタスクと“社長が2人いる”という感覚>
秘書がいると、実質的に“社長が2人いる状態”になります。たとえば、誰かに会ったあと、その日のうちに秘書がお礼メールを出し、翌週にはお礼状やハガキを送る。この流れは一人ではできなくても、秘書がいれば実現します。
1つの出来事に対し、2倍のスピードで対応できる。
それこそが秘書の最大の価値です。
⸻
<社長の最大のパフォーマンスは「昼寝」にある>
実は、**社長の思考が最も鋭く、創造性に満ちている瞬間は「目覚めた直後」**です。
これは朝だけでなく、15分程度の昼寝によっても再現できます。脳が“まっさら”の状態になり、アイデアや判断が冴えるのです。
だから、昼寝をすると1日何回もこの状態を使える
その間に、秘書が以下を担当してくれます。
• 必要な情報の受け取り
• 緊急時のみ起こしてくれる
• 起床後すぐに仕事に戻れるよう準備してくれる
まさに、**「昼寝も戦略」**という考え方です。
⸻
<「アシスタント」ではなく「秘書」と呼ぶ意味>
世間では、「アシスタント」という言葉は下に見られがちです。
しかし、「秘書」と紹介するだけで、相手の対応が変わります。
「秘書=社長の横にいる人」と認識されるため、
・重要な連絡
・アポイントの調整
・判断が必要な案件なども、秘書を通じて伝えられるようになります。
どんなに経験の浅いアシスタントであっても、「秘書」と呼ぶだけで、対外的な信用が格段に高まります。
⸻
<秘書の雇い方:秘書は未経験者がいい理由>
最後に、秘書を採用する際は**「未経験者」をおすすめします**。
なぜなら、経験者は過去のやり方に固執しやすく、素直にあなたのやり方に合わせてくれない場合があるからです。
文句ばかり言う、前はやってなかった。前はもっとよかったなどと文句言う。また資格を持ってる人は、それだけですごく自信がある。でもこの時代、昔も資格の内容は使えなくなったものが多い。よって、資格なんてものは、なんの役にも立ちません。
また、資格を持っている人は、プライドが高く指示を聞かないこともあります。
一方、未経験者は素直で学習意欲が高く、自分の色に育てやすいのです。
⸻
<寄り添う存在としての秘書>
秘書という存在が、常にあなたのそばにいてくれることで、
あなたが日々感じる喜びや苦しみ、悩みや葛藤――
そういったすべての“心の動き”を、共に体験し、共有してくれます。
ただ業務をこなすサポーターではなく、
あなたの「そばにいる者」として、同じ景色を見て、同じ時間を過ごす。
その中で、秘書はあなたの考え方や行動の背景を深く理解し、
単なる補助者ではなく、**最も信頼できる「相談相手」**へと進化していきます。
時にそっと背中を押してくれ、時には厳しい言葉で目を覚まさせてくれる。
秘書は、あなたの本音に寄り添いながらも、的確なアドバイスや叱咤激励ができる存在。
だからこそ、経営者にとっては、かけがえのない“最高の理解者”となるのです。
ーーーーー
<秘書面接:本当の“相性”を見極めるプロセス>
秘書を採用する際、最も大切にすべきなのは「面接の質」です。
単なるスキルチェックや履歴書の確認では、本当に自分に合う人材かどうかは見えてきません。
だからこそ、私は**「面接の場だけでは判断しない」**ことを強く意識しています。
まず、最初に行うのは一般的な面接です。オフィスで話し、経歴や志望動機など基本的な情報を聞き出します。
しかし、実はこの時点では“仮の面接”にすぎません。
その後、私は候補者と一緒に食事に出かけます。
実はこの食事こそが、本当の意味での面接――**「本面接」**なのです。
テーブルを囲み、緊張の解けた状態で、ざっくばらんに会話を交わします。
世間話や過去の経験、価値観、ものの考え方など、幅広いテーマについて自然に話す中で、
その人がどのような姿勢で仕事に向き合っているのかを見極めていきます。
たとえば、ある課題について「こういう仕事があるけど、できる?」と聞いてみると、
人によって反応は大きく分かれます。
ある人(Bさん)は、「ちょっと難しいですね」「時間がかかりそうです」とネガティブな反応を示す。
一方、別の人(Aさん)は、「やってみます」「工夫すれば何とかできると思います」と、前向きに答えてくれる。
もちろん、どちらが正しいという話ではありませんが、私が見ているのは“スキル”ではなく“姿勢”です。
このようにして、面接というよりも“人間としての向き合い方”を見ていくのです。
⸻
<奥さんとの“相性確認面談”というもう一つの視点>
さらに私は、もう一段階の面接を設けています。
それがいわゆる「奥さん面接」です。
と言っても、奥さんが直接候補者に面接をするわけではありません。
候補者と私と奥さんの3人で一緒に食事をし、自然な会話の中で相性や雰囲気を見極めるのです。
これは非常に大切な工程です。
というのも、秘書という存在は社長のすぐそばにいるため、家族との信頼関係にも影響を及ぼす存在だからです。
奥さんがやきもちを焼いてしまうような関係性にならないか、
相手がどこまで礼節や距離感をわきまえているか、
家族ぐるみで信頼関係を築ける人かどうか――
そのような“空気感”を肌で感じ取る場として、奥さん面接を位置づけています。
⸻
⸻
<採用前には「1日インターン」で実践チェック>
そして、最後のステップとして、私は必ず**「インターンシップ体験」**をお願いしています。
いきなり採用してしまうのではなく、まずは1日、実際の業務に同行してもらうのです。
この1日で、以下のようなことを確認します:
• 一緒に過ごしてみて居心地が良いかどうか
• 動きのスピードや反応が自分のリズムと合っているか
• チャットや連絡への返信が早く丁寧かどうか
• 細かい指示に対して素直に動けるかどうか
こうして、**実際に一緒に動いてみなければ見えない「本当の相性」**を確かめていきます。
⸻
<まとめ>
秘書選びにおいて大切なのは、履歴書でもスキルでもなく、
**「人として合うかどうか」「長く信頼関係を築けるかどうか」**です。
そのために、私は
1. 一般面接
2. 食事を通じた“本面接”
3. 奥さんとの相性チェック
4. 実務体験としてのインターンシップ
という4つの段階を経て、じっくりと見極めています。
秘書は、あなたの分身です。
だからこそ、安易に決めず、誠実に向き合いながら、「この人となら一緒に未来を創れる」と思える相手を選んでください。
ーーーーー
<まとめ:秘書は「今すぐ雇え」>
社長の仕事は「考えること」「判断すること」「未来を創ること」。
その時間を作るために、あなたに今、必要なのは秘書の存在です。
PDCAを回すためにも、失敗して学ぶためにも、まずは動くこと。
秘書を通じて、あなたの能力は2倍にも3倍にもなります。
「秘書は、大きくなってから雇う」のではなく、
「大きくなるために、今すぐ雇う」のです。
1-2)起業・独立・副業「未来起業」→マインド起業・ミラクル起業
いつかは起業ではなく、
今スグに起業する。(今日・明日・今週)
起業といっても会社はやめずサラリーマンは続け、
大きな会社を作るわけでもなく、
大々的に起業するのではなく、
「マインド起業」と、して、
想いだけで、起業する。
そして、ハイブリットで働く。
「マインド起業」とは、会社を作るのではなく、
気持ちだけの企業です。
「マインド起業」は、
まだ、オフィスも店舗も何もいらない。
「屋号」と「名刺」と「マインド」の3つのみで、
起業しサービスを行い利益を出していく方法です。
起業を絶対に失敗しない方法は、
最初からお金をかけないこと。
⚫︎オフィス→自宅
⚫︎店舗→借りない。
⚫︎貯金→使わない。
⚫︎借金→借りない。
⚫︎サラリーマン→辞めない。
⚫︎人材→雇わない。外注で行う。人材ネットワークを作る。チームを作る。
⚫︎試す→売ってみる。本製品や本サービスがなくても売ってみる。「事前販売」
→自分の集客効果。ターゲット。キラー商品。価格戦略。USPがわかる。
この方法で行えば売れると思っているのなら、
利益出ます。
利益=売上ー原価ー経費です。
経費が「0」なら、儲かるのです。
大幅な利益が出てから、本格「起業」すればいい!
まずは、自宅やカフェ、ホテルで行ってみる。
ここまでを行うのを「マインド起業」と呼んでいます。
<マインド起業:事例>
ケーキ屋をしたい人は、突然会社を辞めて、店舗を持つのではなく、
まずは、自信のあるケーキを作って、知人のカフェで、売ってみる。
本当にそれに、価値があれば、売れて、評判になります。
ならなければ、何かが足りないのです。
<マインド起業で分かる事>
⚫︎メニュー開発
⚫︎最適金額
⚫︎売れ筋
⚫︎ターゲット
⚫︎顧客リスト
⚫︎マーケティング
⚫︎仲間(なかま)
⚫︎資金予測
⚫︎スタッフ
⚫︎広告予測
★実績もつく
⚫︎銀行でお金も借りれる(実績があるから)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「ミラクル起業:ステップ1」
「定職」と「副業」の両方行う「美味しいとこどりの手法。
サラリーマン(定職)と起業(副業)
ミラクル起業で、今の仕事(定職)を辞めずに、
そのまま、定職を月に200時間を働き続ける。
それとは別に土日や平日で、副業で別に月200時間働く。
これを「Wワーク」といいます。
「定職」と「副業」の両方行う。美味しいとこどり・・
それがミラクル起業(安定とチャレンジ)→最強の働き方。
従業員+個人事業主。Wで働こう。最強!やりがい。
いきなり辞めない、いきなり借りない
⚫︎小さく始めて、大きく育てる
⚫︎常にテスト&改善
⚫︎今の収入を保ちながら、少しずつ夢に近づく
⚫︎「ローリスク×ローリターン」と「ハイリスク×ハイリターン」を両立させる
●【定職・サラリーマン】従業員(ローリスク・ローリターン)今のまま、月200時間
●【副業・起業】経営者(ハイリスク・ハイリターン)土日と平日で200時間
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「ミラクル起業:ステップ2」
「サラリーマン(正社員)」+「起業(副業)」+「インデックス投資」
を、同時に3つを行う事。そして、最後はFIRE(ファイヤー)も目指します。
⚫︎【定職】サラリーマン(ローリスク・ローリターン)
⚫︎【副業】起業・独立(ハイリスク・ハイリターン)
⚫︎【投資】インデックス投資(ミドルリスク・ミドルリターン)
3つを同時に行うことで、分散化でき、リスクもリターンも平均化される最強方法です。
FIRE(ファイヤー)とは、経済的独立・早期退職」を、未来目指すために
<起業は?「どんな仕事を選んだいい?」>
●自分の好きなこと
●自分の得意なこと
●人の役に立つこと
★3つの合わさったところ
<企業に最適なサービス>
●相手に利益が出るもの
●日本中に売れるもの
●世界中に売れるもの
ーーーー
起業するには、
⚫︎独自性「他社や他人にない自分だけの価値」「目立つ」「魅力的」
⚫︎属人性「自分にしかできない物」「真似されない」
が必要です。
ーーーー
自分自身の集客効果も試せたり、「顧客リスト」作りができる。
だんだん売れるケーキがわかってくる。
その「地域のターゲット」と「キラー商品」が明確になり、
その地域やターゲットの「価格帯」もわかり、
「見せ筋商品」「不良在庫」も明確になってくる。
どんどん、カフェを増やし、利益が出てきたら、初めて「起業企画書」にまとめ、
「採算イメージ企画書」を作ってみる。
出来上がった両「企画書」は机上の空論ではない。本物の企画書ができる。
本格的に「起業」する頃には、「キラー商品」「ターゲット」「顧客リスト」「価格帯」が明確になり、
即利益がでる企業ができる。
<ミラクル起業のイメージ>
⚫︎ローリスク・ローリターン【定職】サラリーマン
⚫︎ハイリスク・ハイリターン【副業】起業・独立
⚫︎ミドルリスク・ミドルリターン【投資】インデックス投資
3つを同時に行うことで、分散化でき、リスクもリターンも平均化される最強方法です。
「ミラクル起業」と呼んでいます。
<起業の成功方法>
⚫︎ハイブリット起業(ミラクル企業)
→「定職」+「副業」の2つ以上やる事。
⚫︎ハイブリッド能力(複数能力掛合)
→2つ以上の「能力」を掛合せて使える力。
<起業のステップ>:貧乏父さん、金持ち父さん> BY:ロバート・キヨサキ
●従業員(会社員・サラリーマン)
↓
●専門家(研究・実験・マーケティング・集客)「マインド起業」
↓
●経営者(起業家・企業家)「本格起業」
↓
●投資家(株式や債券)
★未来起業とは、いつか起業するのではなく、
今すぐに起業して、「専門家」「研究家」「マーケティング」「集客」をスグに行う。
ーーーーーーーーー
<点を増やす>
イノベーションを起こそう!
自分自身のイノベーションを起こそう!
人生のイノベーションを起こそう!
人生も「点」の質と量で決まる。
今、AIに詳しい人が増えています。
でも気をつけたいのは、「AIを使える=点」ではありますが、
それ「1個だけ」では差別化できないということ。
スティーブ・ジョブズは、かつてこう言いました。
「点」と「点」が、いつかつながる」と。
⚫︎一見関係ないように見せる「点」
⚫︎一個一個は弱い「点」しかし、異なる分野
人生でどれだけの「点」を持っているか。
どれだけ、異なる分野の「点」を持っているか。
「点」は、スキルでも、人材でも、経験でも構いません。
いくつの「点」を持ち、それを自分だけの“線”にできるか。
そこに、あなたの「ハイブリッド能力」が生まれるのです。
1-3)「未来起業」→別ブランド(起業家のための起業)
起業は、まだ起業してない人だけのものではありません。
もうすでに、起業して企業やフリーランスの方にも、
「別ジャンル」や「ターゲット別」「価格別」「戦略別」「思考別」
に新たに起業するのをお勧めします。
当時、私は、6ページ30万円の「低価格サイト制作」を行なっていました。
それを突然、「200万円のサイト制作」を行い始め、
その後、2時間30万円の「コンサル会社」を行いました。
よって、別ブランドで「未来経営」「低価格商品」「高額商品」で、起業してもいいのです。
ーーーーー
私のように通常業務以外にブレーンを集めて、
「未来経営」の思考会議を行ったり
⚫︎メイン:制作サービス:通常の営業・受注・制作・納品
⚫︎サブ:未来経営:未来経営15項目のイメージ図制作・ブレーン会議
ーーーーー
ーーーーー
「ユニクロ」が「ジーユー」を出したように「低価格戦略」
⚫︎メイン:ユニクロ:ファミリ:中価格:日常:ベーシック
⚫︎サブ:ジーユー:若者中心:低価格:自由:流行重視
ーーーーー
ーーーーー
トヨタがレクサスを出したように「高級高額戦略」
⚫︎メイン:トヨタ:大衆:低価格から中価格:台数重視:コスパ:安心信頼:実用志向
⚫︎サブ:レクサス:高級:中から高級価格:空間演出:先進性:世界基準:プレミアム
ーーーーー
1-4)「未来起業」→【Wブランド】
Wブランドとは、「大衆向け」と「高級向け」等の2つのブランド、「サラリーマン」(安定)と「副業・起業」(チャレンジ)等の2つのブランド、「特質なこと」(メインターゲット)と「対談特化」(サブターゲット)等の2つのブランド、幅広い市場を効率的にカバーする戦略です。大衆向けには信頼性と親しみやすさ、高級向けには独自性と高を同時に展開したり付加価値を持たせることで、異なる顧客層に刺さる製品・サービスを構築できます。これにより、単一ブランドでは成し得ない「利益の最大化」と「ブランド格の向上」を同時に実現できます。さらに、事業の安定性を高め、ブランド全体の信頼感と認知度も飛躍的に高まります。
高級ブランドで高単価・高利益率を確保しつつ、大衆ブランドで継続的な販売数とキャッシュフローを生む構造は、経営の安定と成長を同時に加速させます。
<Wブランドのメリット>
⚫︎「2層の市場」を同時に獲得できる(大衆と高級の両方)
⚫︎「価格帯の幅」が生まれ、利益構造が強くなる
⚫︎「ブランドの格」を高めつつ、大衆にも浸透できる
⚫︎「選択肢の豊富さ」で顧客満足度が上がる
⚫︎「高級側の演出」が大衆側にも信頼感をもたらす
⚫︎「差別化」がしやすく、競合から抜け出せる
⚫︎「高級ブランド」があることで、会社全体のイメージが上がる
⚫︎「ブランディング戦略」が多層化し、柔軟に展開できる
⚫︎「売上の安定化」ができ、不況時も大衆層でカバー可能
⚫︎「成長フェーズ」に合わせてブランド育成ができる(段階的戦略)
<Wブランドのデメリット>
⚫︎「ブランドの混乱」が起こる可能性(イメージのブレ)
⚫︎「高級ブランド側の希少性」が大衆化で損なわれる危険
⚫︎「運営コスト・開発リソース」が2倍に増加する
⚫︎「顧客対応・販路」が複雑化し、管理が難しくなる
⚫︎「両立の戦略設計」が甘いと、両方中途半端になるリスク
<Wブランド事例>
⚫︎トヨタ(大衆ブランド) ✖ レクサス(高級ブランド)
⚫︎ホンダ(大衆) ✖ アキュラ(高級)
⚫︎日産(大衆) ✖ インフィニティ(高級)
⚫︎フォルクスワーゲン(大衆) ✖ アウディ(高級)
⚫︎ルノー(大衆) ✖ アルピーヌ(高級)
⚫︎シボレー(大衆) ✖ キャデラック(高級)
⚫︎フォード(大衆) ✖ リンカーン(高級)
⚫︎ヒュンダイ(大衆) ✖ ジェネシス(高級)
⚫︎キア(大衆) ✖ キア・ウォーリア(高級EV)
⚫︎アマゾン(大衆EC) ✖ アマゾン・プライム(プレミア会員)
⚫︎コカ・コーラ(大衆) ✖ コカ・コーラ・プレミアム(高級路線)
⚫︎ペプシ(大衆) ✖ マウンテンデュー・インパクト(プレミア炭酸)
⚫︎ヘッド&ショルダーズ(大衆) ✖ P&Gプレミアダメージケア(高級)
⚫︎ネスカフェ(大衆) ✖ ネスプレッソ(高級)
⚫︎ケロッグ(大衆) ✖ ケロッグ・クラシック(プレミア穀物)
⚫︎マクドナルド(大衆) ✖ マクカフェ(高級カフェライン)
⚫︎ルフトハンザ(大衆) ✖ ルフトハンザ・ファーストクラス(高級)
⚫︎ユニクロ(大衆) ✖ +J・Uniqlo U(高級デザイナー)
⚫︎イケア(大衆) ✖ SVALNÄS(高級限定家具)
⚫︎アップル(大衆) ✖ Apple Watch Hermès(高級コラボ)
⚫︎パナソニック(大衆) ✖ ラムダッシュ(高級シェーバー)
⚫︎シャープ(大衆家電) ✖ ココロボ(プレミア家電・ロボット)
⚫︎ソニー(大衆AV機器) ✖ グランドワガード/グランドヴィジョン(高級スピーカー・TV)
⚫︎キャノン(大衆カメラ) ✖ EOS Rシグマンス(高級フルサイズミラーレス)
⚫︎キヤノン(大衆プリンタ) ✖ imagePROGRAF(高級大判プリンタ)
⚫︎サムスン(大衆スマホ) ✖ Galaxy Z Fold/Flip(高級フォルダブル)
⚫︎ファーストリテイリング(大衆アパレル) ✖ Theory(高級ライン)
⚫︎H&M(大衆ファッション) ✖ COS(高級ベーシック)
⚫︎ギルレット(大衆シェービング) ✖ 球面3枚刃/Labs(最高級カミソリ)
⚫︎スター・ウォーズ(大衆エンタメ) ✖ ライズ/ヴィンディケーター(高級スピンオフ作品)
1-5)「未来起業」→【起業のハイブリッド(3分類)】
① ミラクル起業
→ 思いついた瞬間に即行動する「即行動型の起業」
→ 瞬発力を活かした一発逆転型。
→ マーケティングや市場実験として行う。
② ハイブリッド起業
→ 2つ以上の基盤を同時に持つ「副業型起業」
→ 例:「定職+副業」「会社員+法人」「雇用+NPO活動」
③ ハイブリッド能力
→ 複数スキルを掛け合わせた「スキル融合型起業」
→ 例:「デザイン×戦略」「コンサル×営業」「論理×感性」
2-1)未来経営「未来経営」
今だけを頑張るのではなく、大きな目標をたて、そこから逆算して、
未来を見つめ、今を頑張る方法。未来経営方式。
一般的な経営は【問題解決型】です。
「問題発見」し、目の前の課題を次々と処理し解決
「問題解決」していく「問題解決型」のスタイルです。
そのために、マニュアル化・指導・教育・工夫・努力。
様々な手段が駆使されます。
この方法では、経営の問題は一定レベルまで解決します。
しかし、
それだけでは本来の目標や理想の未来には到達できません。
まして、自分の叡智や限界を超えた企業には成長しません。
経営は、化学変化です。
自分ひとりではできない世界も、
信頼できる秘書や人材・パートナー・機材・環境・AI
と融合することで、
思いがけない素晴らしい世界が生まれます。
私も当初、私だけの能力では、
会社は「売上1億円が限界」だと思っていました。
ところが、多くの人とのつながりと、他の方の協力で、
最終的には、売上20億円まで達成しました。
これは、私の能力だけではありません。
「未来経営」を戦略として、
大きな目的と目標を作り、それを逆算して、計画を作り、
そのための今日の仕事を一生懸命にやることが大事です。
これを僕は、標語にしていました。
「未来を見据えて足元固める」
とにかく、このPDFを1回全部一通り読んでください。
全体像を掴んでください。
経営の技術とノウハウを学び続け会社を進化させる。
<行動指針>
⚫︎1年後・2年後・5年後・10年後の会社や自分の未来像を具体化する
⚫︎現在の分析し、未来から逆算して、今やるべきことを設計する
⚫︎技術を日々アップデートする
⚫︎USPやサービスを日々アップデートする
⚫︎経営技術を日々アップデートする
<会社のビジョン><会社のビジョン>
会社のUSPを作る・視覚化して、自分に迷いがないようにする。
会社の方針や方向性をはっきりする。(わかりやすくする)
会社の方針や方向性を「社員・クライアント・パートナー」に魅力的にする
会社の方針や方向性を視覚的に見れるようにする「ポスター・標語・クレド」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<KPI(重要業績評価指標)>
KPIとは、「重要業績評価指標)」です。
「Key Performance Indicator」の略です。
でも、私はKPIは「未来経営」では、意味がないと思っています。
なぜなら、KPIは「未来」ではなく
「過去」からばかりを測る指標だからです。
多くの企業でKPIが使われていますが、
実際には「過去の結果」を記録しているだけです。
⚫︎アクセス数、
⚫︎問い合わせ数、
⚫︎来店数、
⚫︎売上件数。
これらはすべて「終わったこと」です。これらはすべて「終わったこと」です。
その数字を見て、良かった・悪かったと判断しますが、
それは「テストの点数を見て、将来が見えると思い込んでいる」のと同じです。
本当に必要なのは、未来を変えるための
「思考」と「戦略」と「行動そのもの」です。
KPIの問題点は、「測れること」だけに集中してしまうことです。
そうすると、本当に大切なものが見えなくなります。
たとえば、顧客の感動、社員のやりがい、市場の変化の兆し。
これらはKPIでは見えません。
だから、KPIから脱出しなければいけません。
これからの時代に必要なのは、未来を見る視点です。
そこで、未来経営としては、
KFD(Key Future Design)=未来設計逆算思考
KVI(Key Vision Indicator)=未来の“実現指標
の2つを行います。
まずは、KFDを行います。Key Future Designです。
未来を設計する思考法です。
目的がブレないように、未来から逆算して今の行動を決
めます。未来を設計する思考法です。
目的がブレないように、未来から逆算して今の行動を決めます。
そこで【KVI】です。
Key Vision Indicator」です。
未来を測る「実現指標」
設計した未来に対して、どこまで近づいているか?を測る未来メーターです。
KVIは、「可視化」「実感化」「数値化」の3つで構成
されます。
まとめると、KPIは過去を見るためのもの。
⚫︎KPI(Key Performance Indicator)は「過去の結果」を見る指標
⚫︎KVI(Key Vision Indicator)は「未来の実現度」を測る指標
これからの経営は、「未来を設計し」「未来を測る」こ
とが重要です。
数字の奴隷になるのはやめて、
未来を創る経営にシフトしましょう。
ーーーーーーーーーー
【実践】<会社の変革と成長>
1)個人事業主期(目安:社長 1人)
社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。
→この頃は、売り上げもない、実績もない。知名度もな
い。
→あるのは、夢と目標だけ、だからこそ「プレゼンテー
ション」が大事!→あるのは、夢と目標だけ、だからこそ「プレゼンテー
ション」が大事!
→企画書とプレゼンテーションが大事だった。
2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)
社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。
→自分の時間を増やしパワーを上げるために、人材5人
目ぐらいに秘書を雇用!!
→この選択が、その後の成長や企業化につながった。
→必死に企業化を目指していた。
3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)
組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。
→全く新しい経営が必要で、すべての方法を変えていっ
た。
→経営も営業もゼロからの作り直し
→組織化がすごく大変だった、チームから始めて突破し
ていった。
4)企業化期(目安:社員数 約100人)
仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに
成長速度が加速。
→社長が「仕組み・仕掛け」に集中すると、会社は自然に大きくなる。
→気が付けば、自然に社員は増えていった。
→経営は「任せること=加速させること」になる。→経営は「任せること=加速させること」になる。
★よくあるのが、天才的経営者の問題です。
全部、自分でできたり、全部、自分がしなくては、気が済まない方法です。
能力が高い人に多いです。
しかし、自分の限界を突破するために、チームで行う方法を、思いついた方は、
飛躍的に伸びるのです。
3本の矢です。
2-2)未来経営「仕事分析」と「利益アップ」
「未来経営」で最初に行うのが「仕事分解」と「仕事分析」です。
なぜなら「未来経営」では、利益アップ、年収アップのために、
人材(スタッフと秘書)を
増やすことが前提になるからです。
自分1人の力や能力だけでは、
自分の能力を高められないからです。
チームで戦うのです。
人材が会社を推進させます。
逆に言えば、人材を増やさない限り、
会社は大きく前に進みません。
大きいとは、おきさだけと違います。
質や目標のことでもあります。
ただ、チームといっても、
<1人増加では効果がない>
たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、
スタッフを1人雇ったとします。
しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、
社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。
一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。
結果的に「2人で1人分」のパフォーマンスしか出せず、
仕事の質と量は増えません。
売上が増えず、仕事も減らず、人件費だけ増えて、利益が減ります。
そんな状況だから「疲弊」してしまいます。
そうなんです。
そこに大きな壁があるのです。
1人入れて、そこで、挫折するのです。
だから、1人で頑張っている方は、
永遠に、1人で頑張るのです。
なぜなら、2人でも意味がないからです。
<2人増加でも効果がない>
たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、
スタッフを2人雇ったとします。
給料は3倍です。経費も3倍なのに・・・
しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、
社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。
一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。
なので、3人全体で、150%にしかならず、
思ったより効果がないのです。
「疲弊」して、続かず、その先に、進めないのです。
その大きな、壁を越えるのです。
映画ディズニーの「モアナと伝説の海」の「珊瑚礁」の海の壁と同じです。
意味がわからなければ、ぜひ映画を見てください。
モアナは、「珊瑚礁」を超えて、「珊瑚礁の外」に出たのです。
「ブレイクスルー」(限界突破の超進展)です。
そこで、本当に2倍のパフォーマンスを得るには、
「4人チーム(社長含む)」を作る必要があります。
4人 × 50% = 実質2人分の戦力です。
ブレイクスルー
「壊すからこそ突き破れ通り抜け貫通し、そして新たな展開へ飛躍できる」
のです。
<4人で初めてチームの意味がでできます>
<最初の4人チーム作成方法>
4人チーム作成の方法
当初の4人チームは、お金もなく、雇えませんでした。
全員正社員ではないです。
一部外注、一部アルバイト。
⚫︎社長
⚫︎スタッフ:経理財務:バーターで無料
⚫︎スタッフ:システムエンジニア:焼肉奢って作ってもらった
⚫︎秘書:アルバイト:時給
4人チームができました。
成長してからも、外注していました。
また、優秀な人は、年収も高いので、
週1回2時間だけ、契約した人もいました。
これで、売上が上がってきました。
これで初めて「効果的な拡張」が実現します。
<4人チームの構成>
⚫︎社長:1名
⚫︎スタッフ:2名(原価1000万円)
⚫︎秘書:1名(原価500万円)
合計人件費:1500万円
この中で秘書は「社長自身の効率を向上」させます。
社長の仕事の「質」と「量」が増え、さらに「未来を描く時間」が生まれます。
この4人チームの3人が「90%の業務」を担い、
社長が「10%の要点」に集中できる状態が理想です。
要点とは社長の仕事の「質」と「量」が増え、
さらに「未来を描く時間」が生まれます。
そして、その体制をつくるために、
そこで、まず必要なのが「売上アップ」です。
売上が上がれば、チームが作れるのです。
では、どうやって売上(利益)を上げるのか?
普通は「利益が落ち込む月」や「利益の少ない仕事」を伸ばそうとしますが、
そこは苦手分野であり、実は利益を伸ばすのは難しいです。
だから、逆に得意な分野を伸ばします。
⚫︎最も利益が高い仕事
⚫︎最も利益が上がる月
⚫︎新規ではなく、既存顧客へのアップセル・クロスセル
これらを伸ばすために、まず「仕事分析」を行います。
過去の平均利益が高い順に、仕事をリストアップします。
ベスト10で構いません。
そして、そこに戦略を投下します。
⚫︎長期戦略:1回の仕事を2回以上にする
⚫︎高額戦略:金額を2倍以上にする
⚫︎サブスク戦略:毎月の契約にする
そのために、「ベスト10の仕事」を体系化します。
<体型全体図>
⚫︎体系化
⚫︎全体図
⚫︎構造化
⚫︎左から右に進行する
仕事の全体像を可視化し、「この仕事は直ぐに終わらない」
事を相手に見せ伝えるのです。
⚫︎この仕事はもっと深くまで続く
⚫︎この仕事はもっと長く続く
⚫︎この仕事は体系的に設計されている
⚫︎すべてを終わらせるには3年以上かかる
これらを一覧で提示します。
すると、受注は「深く(高額)」
「長く(長期契約)」
「継続的(サブスク)」に変化していきます。
すると初めて、利益が増え、人材を雇えるのです。
要は、人材をチーム化するために
仕事を増やし利益を増やすのです。
原価(人件費)、1500万円のために、
最低利益3000万円〜通常利益4500万円〜最高利益7500万円を目指すのです。
2-3)未来経営 全体を知る「ビックピクチャー」
<全体視点と細部視点の両立>
全体を知ることが重要です。
絵や図、イラストで言語化だけでなく、視覚的に
具体的なイメージにすることが大事です。
未来の会社や未来の組織の絵を書きましょう
「枝葉」を見るのはいいけど、それだけでは意味がありません。
「自分の仕事」や「お客様」にとって、
それがどういう意味があるのか?を常に問いましょう。
「細部」を見ながら「大きな全体」を考える視点が、
これからの経営には欠かせません。
⚫︎広告ひとつ作るにしても、「なぜこのデザインか?」
「どんな印象を与えるか?」「その印象が売上にどうつながるか?」を考える。
⚫︎スタッフの一言も、「お客様との信頼関係」にどう影響するのか、
「リピート率」や「口コミ」にどうつながるかを意識する。
⚫︎チラシ一枚の色使いや言葉選びも、ブランディング全体の統一性や、
感情の記憶に影響してくる。
⚫︎「クレド」も単なる言葉ではなく、スタッフの行動基準になり、
「企業文化」や「顧客体験」に直結するものです。
全体像を理解しながら、細部のひとつひとつに意味を持たせる。
それが「全体設計」の思想であり、「未来経営」の核心です。
全体を知らずして、細部にこだわっても意味がありません。
逆に、細部をないがしろにしても、全体は空洞になります。
⚫︎枝葉と幹をつなぐ
⚫︎現場と戦略をつなぐ
⚫︎一つ一つを「売上」「ブランド」「信頼」と結びつける
この「全体思考」が、あなたの仕事を10倍に変える基盤です。
ーーーーーーーーーー
普通に仕事をしていくと、自分で自分のことが分からなくなり、
また視野が狭く、目的が不明確になり、
現時点での自分の位置(場所)や、目指す目標や位置が、
わからなくなります。
★位置とはポジショニングのことです。
今の現在のまま頑張っていると、
登った山の頂上に着いた時に、
「この山じゃない」「こんな山のイメージじゃない」と、
今の行動が、本当に自分が目指したい目的に、
向かっているかわからなくなります。
そこで、自分のためにも、
また、スタッフのため、パートナー企業のためにも、
「事業全体」や「ロードマップ」が、視覚的にわかる
ようにしましょう。
大きな1枚の紙に目標や目的を書いたり、
絵や図にしたりして、
壁に貼り出しましょう!!
「木を見て森を見ず」と、いう言葉があるように、
目の前や小さいことに心を奪われて、
全体を見通さないことにならないように、
全体やゴールを見て、全体を把握して、経営しましょう!
また、自分だけではなく、
スタッフ、仲間、関係者に浸透させましょう!
目標を具体的な絵にすることで、
イメージが湧き、達成スピード、達成率が自然に上がります。
★全体を見る(大きな絵を描き貼り出す)
★高いところから全体を見る(鷹になったつもりで上空から見る)
★ロードマップを作る
ロードマップには、資金・売上・利益・オフィス・図面
経費・人材・組織・組織図・機材・サービス・商品・技術などを、
具体的に明確にしましょう。
目の前の問題点を改善するのではなく、
大きな目標に向かって、根本的な改善を行いましょう!
2倍じゃなく、100倍を目指すのです。
困っているところを改善する問題解決ではなく、
画期的改善(大幅改善・根本的改善)を目指すのです。
「対症療法→原因療法」
大きな紙だと、1枚で全部を見渡せ、
詳細まで見れるのもいいです。
また、誰かにプレゼンするなら、
企画書にするのもいいでしょう!
私は、スタッフへのプレゼンを
半年ごとに1回行い、毎回約400ページ以上の
資料を作って行ってました。
写真やイラスト、イメージ、図や、表、図面などを入れて、
わかりやすく、視覚的にしていました。
内容は、以下です。
⚫︎過去の目標と項目
⚫︎過去の項目毎の達成評価と進捗率状況
⚫︎現在の目標と項目
⚫︎今後の目標と項目(クオーター毎)
⚫︎近未来の目標と項目(2年~3年)
⚫︎未来の目標と項目(5年~10年)
全て数値化し、具体的にしていました。
★企画書を作りプレゼンする。
★数値化し達成状況報告、達成率を確認する。
★写真やイラスト、イメージ、図や、表、図面を入れる。
<会社成長>視覚化・ビジュアリゼーション
複雑で難解、遠い先なことほど、
絵や図にすることで単純化(シンプル化)したほうがわかりやすくなります。
将来の目標や目的を絵や図にしましょう!
例えば、未来の会社組織図、オフィスの建物、オフィスの図面、
マップなどを、大きく絵にかいて、
壁に張り出し、毎日見ましょう!
その結果、自分やスタッフに具体的に浸透すると、
なぜか目標を達成しやすくなります。
また、2~3年後の目標より、
10年後・20年後の
奇跡のような目標をててることが
モチベーションにつながります。
例えば、売上20%アップより、
売上2倍!。 売上20倍の方が夢が広がり、
根本的解決につながります。
★可視化(明示化)する
★絵や図を描く(イメージ化)
★将来の目標を書き出す(言霊やアイコン化)
⚫︎未来経営「全体体型図」
https://www.clipinc-web.com/miraikeiei#2-4
2-4)未来経営 サービスの構造化「全体体系図」「全体構造図」
商品やサービスを売るとき、「単体で売らない」ことが重要です。
簡単に言うと「単品商品」ではなく「定食」で売れと言う事です。
それが、お得に見えるし、原価も経費も安くできるのです。
単体だと、比較され、値切られ、
安くしか売れないのです。
そこで自分のサービスを構造化するのです。
「全体体型図」を作るのです。
<全体体型図の作り方>
左から右に流れ15個以上の「大タイトル」をつけ
その下に、サービスを詳細に10個以上書くのです。
すると、サービスが15×10個になり、
300個以上のサービスになります。
特にサービスの中には、聞いたこともない言葉や
とんがったサービスも入れるのです。
その中から、顧客にピッタリの
「大タイトル」を選んであげるのです。
<全体体型図イメージ・全体構造図イメージ>
USPの作り方「全体体型図」:横6個×縦10個(大タイトル付き)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|大タイトル | 自社だけか | 独自性 | 強み | ユーザーの利益 | 爆発的 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|理念 | 原体験 | 視点の違い | 価値言語化 | 共感想定 | 一言キャッチ |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|顧客理解 | 顧客像 | 隠れニーズ | 欲求接続 | 記憶に残す | 感情の爆発 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|競合分析 | 他社比較 | 独自要素抽出 | ずらし設計 | 差別化表現 | 突き抜け軸 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|自社理解 | 信念整理 | 得意の整理 | 強みの物語化 | 自分らしさ | 象徴ワード |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|言葉設計 | 単語収集 | 言い換え | 一言精査 | USP完成 | 拡張展開 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|歴史・背景 | 動機の棚卸し | 原点の構造化 | 継承した意志 | 存在意義 | 社会への宣言 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|感情の解像度| 気持ちの揺れ | 欲求の根底 | 行動理由 | 共感スイッチ | 涙の瞬間 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|提供体験 | 使用前の悩み | 利用中の感情 | 使用後の変化 | 実感の声 | 期待を超える瞬間
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|社会性 | 共鳴ポイント | 時代との接続 | 使命の表現 | 共創する構造 | 巻き込み力 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|変化の物語 | ビフォー整理 | 変化の設計 | 転換点の演出 | 未来の提示 | ドラマ化 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
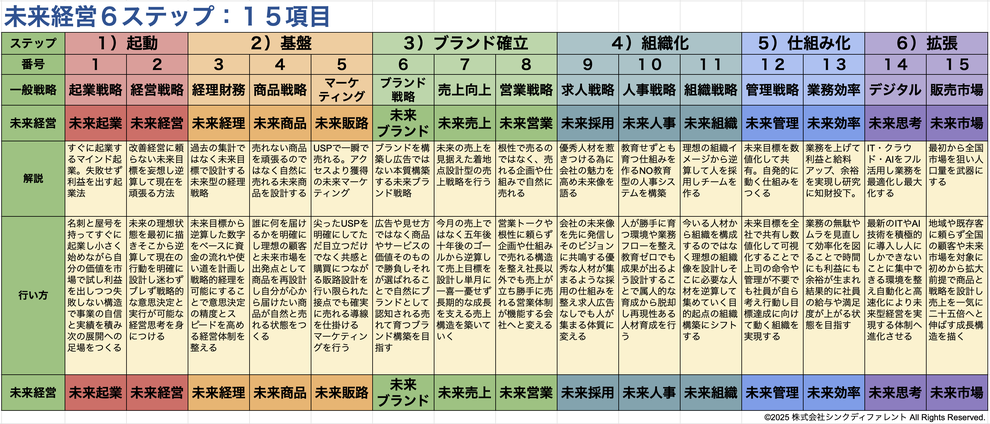

<全体体型図>
全体体型図のプレゼンの様子。
大きく出力して、
ハレパネにはる
<全体体型図のメリット>
「全体体型図」があるから、高く売れるのです。
⚫︎全体がわかる
⚫︎サービスの全体像が側かる
⚫︎「網羅的で信頼できる」と思ってもらえる
⚫︎総体的と思っても萎える
⚫︎流れが分かる
⚫︎詳細がわかる
⚫︎深くわかる
⚫︎多すぎて自分では行えないと思う。
⚫︎どこでも売れる
⚫︎どこからでも売れる
⚫︎誰で売りやすい
⚫︎長期だと思う
⚫︎サブスクで売りやすい
「この人は任せられる」と思われる
<全体体系図を作るメリット:50個>
⚫︎クライアントに「全体像」を一瞬で見せられる
⚫︎「網羅的で信頼できる」と思ってもらえる
⚫︎あなたの「専門性」が図だけで伝わる
⚫︎「この人は任せられる」と思われる
⚫︎営業トークが不要になる
⚫︎プレゼン資料としても使える
⚫︎価値の説明が「視覚化」される
⚫︎高額提案が通りやすくなる
⚫︎単発よりも「継続契約」につながる
⚫︎サブスク型に変換しやすくなる
⚫︎サービスの抜け漏れが減る
⚫︎自分自身の整理になる
⚫︎提案内容のロジックが強くなる
⚫︎見える化で安心感を与えられる
⚫︎他社との違いを一発で伝えられる
⚫︎サービス単価を引き上げられる
⚫︎高額契約につながりやすくなる
⚫︎「全部やってほしい」と言われやすくなる
⚫︎長期計画を組んでもらえる
⚫︎分割提案・段階提案がしやすくなる
⚫︎クライアントの理解スピードが上がる
⚫︎チームへの説明資料にも使える
⚫︎外注・協力会社とも共通認識を持てる
⚫︎研修資料としても使える
⚫︎情報発信のネタとして使える
⚫︎Webサイトやブログにも転用できる
⚫︎体系図だけで“ブランディング”ができる
⚫︎ワークショップのネタにもなる
⚫︎PDF化すれば“無料プレゼント”にもなる
⚫︎「解像度が高い人」と思ってもらえる
⚫︎営業代行資料としても使える
⚫︎見積りが通りやすくなる
⚫︎コンサル力の証明になる
⚫︎業務の全体設計力が伝わる
⚫︎「パートナーとして信頼」されやすい
⚫︎契約更新の根拠になる
⚫︎お客が“自分に必要な項目”を発見できる
⚫︎1枚で「長期戦略の導入」ができる
⚫︎そのまま出版や講座にも使える
⚫︎提案の「ステップ設計」がラクになる
⚫︎営業せず「勝手に売れる図」になる
⚫︎SNS投稿のテンプレにもなる
⚫︎パワポ・カタログ・チラシなどに流用可能
⚫︎顧客が「継続契約したくなる仕掛け」になる
⚫︎「この人しかいない」と言わせられる
⚫︎ポスター印刷して壁に貼れる
⚫︎クライアントが社内で説明しやすくなる
⚫︎価格交渉されにくくなる
⚫︎リピート依頼が増える
⚫︎“あなたの価値”そのものが伝わる図になる
<全体体型図でサービス単価を引き上げられる理由>
⚫︎「全体体系図」があると、「部分」ではなく「全体」を見せられる
それにより、次のような心理と戦略が働きます:
ーーーーーー
■なぜ「サービス単価を引き上げられる」のか?
1)「価値の量」が明確になる
→ たとえば、1項目の説明より「15×10=150個」のサービスがあると
「これだけやってくれるのか」と思わせられる
2)「比較対象」がなくなる
→ 図にして体系化されていると、他社と単純比較できない。
「これはこの人だけの世界観」と思われ、価格が通りやすくなる
3)「戦略設計料」として含めやすい
→ 単なる作業ではなく「設計・設計図・監修・全体監理」ができると伝わる。
これは「価値が高い」と認識されやすい
4)「見えない価値(思考力・設計力)」を見える化できる
→ コンサル的価値や戦略提案力は本来見えにくいが、図にすることで一発で伝わる
ーーーーーー
<全体体型図で「サブスク」で売れやすい理由>
■なぜ「サブスクで売れやすい」のか?
1)「順番に導入する」という構造が作れる
→ 「今月はこの3ブロック」「来月は次の4ブロック」というように、月次で分割提案がしやすくなる
2)「継続的に一緒に取り組む」というイメージを持たせやすい
→ 全体設計があることで、「一緒に完成させていく」「継続して最適化していく」という納得感が出る
3)「やり残し」が自然と残る
→ 全体を見せた上で「今日はここまでやりましょう」と伝えると、他の部分が“未完了の価値”として自然に残る
4)「使えば使うほど得」な印象を持たれる
→ クライアントは「図にある内容を毎月一つずつ受け取っていける」と思うと、長く続けた方が得だと感じる
2-4)未来経営「全体体系図」具体例

左図は、ネットに落ちていた「全体体型図」事例です。
「ペンシル成功シート」で検索できます。
トヨタ自動車が販売しているのは、
「タイヤ」や「ハンドル」や「シート」などの部品ではありません。
それらすべてを組み合わせた「完成車=自動車」という
「複合商品」として提供しているのです。
部品単体では、大きな利益は出ません。
トヨタの年間利益は、約5兆円。
これは「自動車の売上」から「原価(部品・製造費)」と
「経費(人件費・広告費・研究費など)」を引いた「純粋な儲け」です。
ーーーー
⚫︎売上:約50兆円
⚫︎原価:約30兆円(部品+製造コスト)
⚫︎経費:約15兆円(人件費・広告費・研究費など)
⚫︎利益:約5兆円(純粋な儲け)
ーーーー
つまり「部品だけではなく、複合商品としての「完成車」を売る」
「完成車」として、高く売る。
ことこそが最大の利益を生むビジネスモデルなのです。
「WEBサービス」言い換えると、
商品やサービスを売るとき、「単体で売らない」ことが重要です。
実は「複合的にまとめて提供する」ことで、最大の利益が生まれます。
あなたがWEBサービスをしているなら、
ただの「ホームページ制作」や「SNS運用」や「youtube制作」「広告配信」などの
単体サービス(部品)では不十分です。
それらすべてを組み合わせた「完成形=成果商品」として提供すべきです。
「複合商品」として提供するのです。
例えば「売上が上がる〇〇」とか「顧客獲得できる〇〇」、
「WEBパッケージ」や「オンライン戦略セット」です。
部品単体では、大きな利益は出ません。
あなたの年間利益を伸ばすために、
部品は全て外注し、それらを組み合わせた「複合商品」として販売しましょう。
つまり、「部品を組み合わせた複合商品として売る」ことこそが
最大の利益を生むビジネス構造なのです。
「複合商品」として、説明しやすいように
自社サービス+外注サービスを「全体体型図」にまとめましょう!!

<デザイナーよりプロデューサーを目指せ>
【複合戦略のすすめ】
「デザイナーを頑張る」
ことは素晴らしいことです。
でも、時代が変わった今、それだけでは「収入」にも「影響力」にも限界があります。
なぜなら――
「デザインは単体では売りにくい」からです。
だから、「デザイン」だけでは、会社もあなたの給料も
伸びづらいのです。
ロゴだけ、LPだけ、SNSの画像だけでは、価格競争になります。
買う側も「比較」しやすく、「誰でもいい」になってしまう。
だからこそ、あなたが目指すべきは、
「複合的な価値」を束ねて売る「プロデューサー(営業)」です。
⚫︎ホームページ×広告×SNS
⚫︎デザイン×企画×コピー
⚫︎集客×販売×運用支援
など。・・・
このように、「複数の価値」を組み合わせて「成果で売る」商品をつくる。
それこそが「単価が上がる」「リピートが増える」「感謝される」売り方なのです。
デザイナーで終わるのではなく、
「全体を組み立てるプロデューサー」へと進化すること。
それが、あなた自身の「収入アップ」や「価値上昇」に直結します。
つまり、「スキルを磨く」より、「価値を束ねて売る力」を
身につけるほうが、会社もあなた自身にも
はるかに大きな飛躍になるのです。
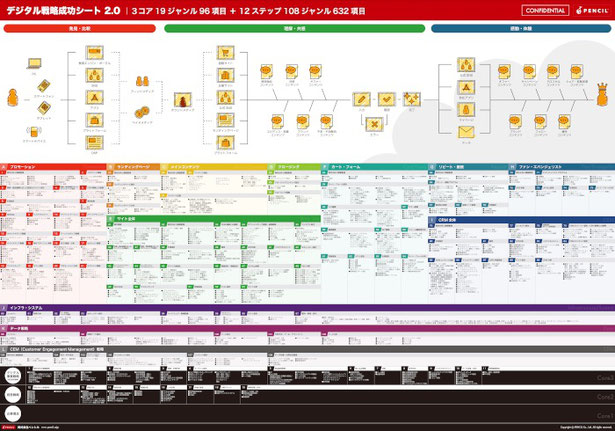
<全体体型図>
相手の金額が安すぎる。
もっと、工数が必要だ。
単発しか売れない。
と、思う時には、
もっと自分の仕事を相手に、
知ってもらう必要があります。
⚫︎戦略的である
⚫︎行うことが深い
⚫︎多岐にわたる
⚫︎長期になる
⚫︎全体を考える必要がある
⚫︎詳細を知ってもらう
そこで、
⚫︎全ての項目を書き出し
⚫︎体型的
⚫︎左から右に進む
⚫︎全体を見せる
⚫︎詳細も見せる
そんな、「全体体型図」を、
見せるのです。
相手に「戦略」と「項目」が見れ
高く仕事が売れます。
<高く売れる10要素(図解の力)>
⚫︎視覚化:言葉では伝わらない複雑な内容を一発で理解できる「図解力」
⚫︎構造化:バラバラな情報を「順序・分類・関係性」で整理し、理解しやすくする力
⚫︎専門感:デザイン・色分け・細密さから「プロフェッショナル感」が一目で伝わる
⚫︎差別化:他の資料と明確に違い、初見で「他と違う」と印象づける武器になる
⚫︎商品化:この資料そのものが「提案ツール」であり「商品」としても成立する
⚫︎再現性:全体像・ステップ・用語が明示され、他案件にも応用可能と思わせられる
⚫︎仕組み化:属人的でなく「仕組み」として成果が出せる印象を与える
⚫︎営業不要:資料が話してくれるので「説明が下手でも売れる」状態を作れる
⚫︎信頼転写:資料の完成度=コンサルの信頼度に直結し、「高額でも納得される」
⚫︎保存価値:クライアントが「保存・印刷・社内共有」することで勝手に営業が回る
3−1)未来経営の「未来経理」
普通の経理は過去をただ数字化しているだけ。
現在の決算書を見ても過去と現実がわかるだけです。
そこで、まずは、理想の決算書を作ってみましょう!
未来決算書です。
⚫︎理想の売上 ⚫︎理想の粗利 ⚫︎理想の家賃 ⚫︎理想の社員への報酬 ⚫︎研究費用
架空の決算書です。
そして、その「現実決算書」と「理想決算書」の隙間を埋める。
埋めるために改善・改修を行う。
そのための「プロジェクト化」を行い。
その「予実管理」を行う。
予想(予定)と実績を比較することで、
現状が把握でき、計画が立てれる。
さらに、細かく分けるのが「未来経営」の「未来経理」
過去経理だけではなく、未来も同時に見る。
「過去」「現在」「予測」「未来」の4つの数字を
同時に把握、さらに、比較することで差分を理解する「未来経理クワトロ表」
<未来経理クワトロ表>
【過去】と【現在】と【予測】と【未来】の4つを同時に見る方法です。
<未来経営:クワトロ法>
【過去】前期、特に去年同月と同時に見て比較する。
【現在】今期、の実数値。現状を把握する。
【予測】今期着地。現状のままだと今期の着地は、どうなるのか?
【未来】目指す目標を計画的に分解した時の数値。
未来経理の
「理想決算書」と「クワトロ表」で、
未来経営です。
私は、以前、経理が苦手だったので、
決算書を、視覚化(図や表)にしたり、オリジナルの決済書を作って、
苦手な経理財務を最大の武器とし、
未来投資を可能にしてました。
行動指針:
⚫︎未来の資金需要を予測する
⚫︎収支バランスではなく、未来設計型経理を実施する
⚫︎キャッシュフローを毎週チェックする
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<未来経理:会社の変革と成長>
1)個人事業主期(目安:社長 1人)
社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。
→経理は自分自身で行う。
2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)
社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。
→経理は、外注で行っていた。
→自社に経理知識がなくても、プロの力でなんとか回る。
3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)
組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。
→外注だけでは精度・スピードに限界。
→経理は、「外注」+「社員」
→社長は「未来の数字」を考える。
4)企業化期(目安:社員数 約100人)
仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。
→経理は、「社員」+「セカンドオピニオンとして外部」
→外注はチェック・監査・相談役にシフト。
→「未来経理」の完成へ
3−2)経理財務「未来資金獲得」黒字倒産回避法
<資金ショート:黒字倒産回避法>
売上が、突然大幅に上がると、資金がショートします。
不思議です。
会社が急成長する時に、
資金がショートするのです。
せっかく営業し、大きな売上が上がると、
支払いも、長期になります。
しかし、納品するために、固定費や経費がかかります。
すると、完成し、入金するまでに、会社のお金がなくなります。
それが資金ショートです。
お金が無くなる前に、銀行で、涼しい顔で、
お金を借りておきましょう!!
営業する前に、お金を借りるのです。
<銀行の借り方>
現在の正確な正直な「決算書」だけでは、
自分にも相手に夢を与えられません。
なので、銀行からお金を借りられません。
自分も相手も夢が見れる。
理想の「決算書」を2年後3年後5年後を出しましょう!
そして、相手のメリットを伝えるのです。
USPは、資金借り入れの時も使えます。
誰でもV字回復が好きなのです。
例えば映画「ビリギャル」です。
「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」です。
では、最初から成績が良かった人や最初から頑張った人では、ダメなのでしょうか?
それでは誰も感動しないのです。
そこで、決算書も同じです。
優秀な決算書より、「ビリギャル」のような最初「ダメ決算書」の方がウケるし、
改善すると、感動できるのです。
よく、経営者の方に、聞くと、
「今、持っていけない」
もう少し良くなったら
「持っていく」
と、聞きます。
しかし、私は、言います。
「ダメな時ほど持っていこう」
そして、「少し改善したら持っていく」
さらに、「改善したら持っていく」
これで、借りれます。
もしくは、「魔法の言葉」を教えます。
相手に「ダメな決算書」を見せて、
「どこをどう直したら借りれますか」?
「具体的な数字」を聞くのです。
相手の言う「数字の80%」になったら
持っていってみましょう!
私は、借りれました。
<資金ショート>
売上が、突然大幅に上がると、資金がショートします。
<資金繰り改善方法>
【1】「資金安定化」→毎月定期的に決まった入金があり経営がしやすくしておく。高額戦略で入金を多くしておく。
【2】「売上アップ」→ まず売上を伸ばして現金収入を増やす。
【3】「入金調整」→入金の交渉をする。(前払い・入金日調整・分割入金)
【4】「経費削減」→ 固定費(経費・家賃・光熱費)などを見直して、出ていくお金を減らす。
【5】「事業モデル転換」→ キャッシュフロー(現金の流れ)を良くするため入金が先に立つビジネスモデルに変える。【5】「資金調達」→ 必要なら、銀行融資・補助金・助成金・投資家・クラウドファンディングなどで資金を確保する。
【6】「支払い交渉」→ 支払いサイト(締め日から支払日までの期間)を延ばす交渉を取引先と行う。
<借入方法・資金調達方法>
1)まだ借りなくてもいい時に銀行に相談に行って借りれる金額を聞いておく。借りれない時は問題点を聞いておく。
2)決算書が悪い時に、銀行に相談に行って借りれる金額を聞いておく。借りれない時は問題点を聞いておく。
→銀行はプロのアドバイザー無料でなんでも教えてくれる。
3)問題点を数値で聞いて、それが解決したら、借りれるという確証を取っておく。
4)決算書を、とにかく良くする。
5)V自回復すると、銀行も喜んで貸してくれる。(最初からいい決算書を持っていくより効果大)
4−1)未来経営「未来商品」
実は、未来経営で、一番効果があるのが、
このコーナー「未来商品」です。
爆売れする夢の商品を妄想する。
そして、「キラー商品」「キラーサービス」を考える。
今まで、売れなかった商品が、突然売れ出す。
自分しか売れなかった商品が、誰でも売れ出す。
のです。最強の方法です。
一般的に企業は「売れない商品を一生懸命に告知し、集客し、販売」します。
だから、【集客型】なのです。
しかし、未来経営では、「爆売れする商品を。集客、営業しなくても売れる仕組みで販売」します。
だから【獲得型】なのです。
そんな夢の「未来商品」考えて考えて考えて、販売してみます。
最悪、作らなくていいのです。
今は、クラウドファンディング」があります。
構想して、売れてから、売れたものを作って、販売するのです。
ーーー
商品やサービスを磨き続け、
圧倒的(爆発的)に売れるものを
考えだし創り出す。
商品をつくる前に、先に、告知や売り方を考える。
最強のUSPや商品を考える。
商品を作るのは、そのあと。
ーーー
<未来商品>
今、販売しているものの改善ではなく、
全く別の商品を考えるのです
今、販売しているものじゃなく、
全く別の新商品を考えます。
⚫︎夢の商品
⚫︎絶対売れる商品
⚫︎見たことない商品
⚫︎驚く商品
⚫︎感動する商品
そのためには、
⚫︎価格を10倍にしたら?
⚫︎価格を1円にしたら?
⚫︎商品を分割したら?
⚫︎ライバルと組んだら
⚫︎商品名の前に「売上が上がる」をつけたら?
まずは、理想の商品を考えます。
そして、次に、
それを実現する方法を考えます。
⚫︎研究
⚫︎企画化
⚫︎外注化
⚫︎システム化
⚫︎AI化
その実現方法は、
⚫︎分散化
⚫︎細分化
⚫︎高額化
などです。
<事例>
私は、元々安いホームページを作っていました。
USPは「ホームページ制作会社」
会社の成長の分岐点で、
USPは「売上が上がるホームページ制作会社」
を考えました。
↓
最終的にはUSPは、
USPは「研究開発型WEBコンサル会社」になりました。
<私の会社の変革と成長>
1)個人事業主期(目安:社長 1人)
社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。
→何を売ればいいのか迷いながら試行錯誤。
→商品・サービスの軸が定まらず、反応を見て動いていた。
→「夢」と「想い」はあるが「売れる型」がない状態。
2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)
社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。
→過去の商品では単価が低く利益が出ないことに気づく。
→商品を大きく変換・進化させる決断を下す。
→独自の商品を開発し品質と価格を一気に引き上げた。
→「売りたいモノ」ではなく「売れるモノを創る」フェーズへ。
3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)
組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。
→社長だけが売れる商品や売り方では限界があると痛感。
→「社員だけでもでも簡単に売れる新・商品開発」
→「社員だけでもでも簡単に売れる新・営業方法」
→「社員だけでもでも簡単に売れる新・納品方法」
→を、目指して、商品設計・営業設計・業務システムへ移行。
→商品・セールスに「再現性」と「分かりやすさ」を持たせていった。
4)企業化期(目安:社員数 約100人)
仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。
→商品を誰でも売れるように
→商品と売り方を、仕組み化・仕掛け化。
→営業力やセンスに頼らず、誰でも売れる構造を設計。
→商品自体に「自動で売れる力」を埋め込む時代へ。年間契約・サブスク商品
4−2)未来経営「未来商品」→【USP】
商品が売れるためには、一番大事なのが「USP」
「USP=独自の売り(強み)」を明確にすることです。
これは、他社では絶対に真似できない。
もしくは一瞬で「おもしろい!」「気になる!」と思わせる、
尖った特徴のことを指します。
<USPとは何か? ~あなたの商品を“唯一無二”にする力~>
USPとは、「Unique Selling Proposition(ユニーク・セリング・プロポジション)」の略で、
**あなたの商品やサービスだけが持っている“独自の強み”**を意味する、マーケティングの基本概念です。
より正確に言えば、USPとは、単に「特徴」や「利点」を表す言葉ではありません。
“顧客に対して、自社だけが提供できる、明確で強力な相手へのベネフィット(利益)”のことを指します。
<USPとは?>
⚫︎顧客に対して、
⚫︎自社だけが提供できる、
⚫︎明確で強力な相手へのベネフィット(利益)
⚫︎相手への利益
つまり、他社では真似できない、「あなたにしかできない約束」。独自の約束
これこそが、USPの本質なのです。
⸻
◆ なぜUSPが重要なのか?
現代の市場では、商品やサービスの差別化がますます難しくなっています。
品質や価格、機能だけで差をつけることは困難になっている今、
顧客の心を動かすためには、「なぜあなたを選ぶべきか」が、一目で伝わる強みが必要です。
USPは、まさにそれを明確に言語化したものです。
⚫︎一度聞いたら忘れられない
⚫︎他と明らかに違うとわかる
⚫︎検索したときに上位に出てくるような“記憶に残る言葉”
こうした特徴を備えたUSPこそが、マーケティングやブランディングの土台となります。
⸻
◆ USPはどこに書くべきか?
USPは、Webサイトやパンフレット、SNS、名刺など、あらゆる“第一印象の場”に必ず入れるべき要素です。
特に、以下の2か所は絶対に意識してください:
1. サイトの最初(ファーストビュー)
2. サイトの最後(クロージング)
なぜなら、訪問者は最初と最後に記憶が強く残るからです。
最初にUSPを提示することで「この会社は他と違う」と印象づけ、
最後にもう一度伝えることで「やっぱりここにしよう」と後押しする。
それほど、USPは**マーケティングの“起点”であり“締め”**でもあるのです。
⸻
◆ まとめ:USPは、あなたの「選ばれる理由」
USPは、ただのキャッチコピーではありません。
それは、あなたのビジネスが持つ「唯一無二の存在価値」を、
短く、明確に、そして心に残る言葉で表現したものです。
だからこそ、USPを考えることは、自分たちの“存在意義”を言語化することでもあります。
「この会社だけが、私のために、これを約束してくれる」
そう顧客に感じてもらえた時、あなたのビジネスは、選ばれる存在になるのです。
⸻
ご希望があれば、USPの「具体的な作り方」や「業種別の例」もお伝えできます。
必要でしたらお申しつけくださいね!
USPとは?:USP概念
●キャッチコピー的で。
●覚えやすく(一度聞くと忘れない)。
●独自ドメインが、とれて。
●爆発的で(衝撃的)。
●独自のもの(他社にないもの)。
●売上に直結すること(ユーザーの利益)。
USP:ビジネスの成功の秘訣・店舗の成功の秘訣・WEBサイトの成功の秘密
成功の秘密は、USPにあります。
とにかく、とんがったUSPが売上が上がります。
そこで、徹底的に考え、時間をかけ、
何度もためし、研究して、作り上げるのです。
もし、画期的なUSPができないのであれば、
工夫か、知恵か、時間が足りないのです。
頑張って、試行錯誤して、
トンがったUSPを作り上げましょう!!
ーーーーーーー
◆ USPとは?
ビジネス・店舗・Webサイト、すべての成功のカギを握る「たったひとつの答え」
あなたのビジネスを成功させたい。
お店の売上を伸ばしたい。
Webサイトからもっと反応を得たい。
――その願いを叶える「成功の秘訣」は、実はとてもシンプルです。
⸻
◆ 「とんがったUSP」が売上を生む
成果を出しているビジネスには、必ず“とんがったUSP”があります。
尖っていて、わかりやすく、記憶に残り、思わず「これ、他と違う!」と感じてもらえるようなUSPです。
なぜなら、世の中には似たような商品やサービスが無数に存在します。
その中で選ばれるには、「他とどう違うのか?」が一瞬で伝わらなければなりません。
売れるかどうかは、USPにかかっていると言っても過言ではありません。
⸻
◆ USPは“偶然”ではなく“戦略”でつくる
USPは、感覚やひらめきだけで生まれるものではありません。
それは、**徹底的に考え抜き、試行錯誤を重ね、時間とエネルギーを注いで創り上げる“戦略”**なのです。
⚫︎何度もアイデアを出し直し
⚫︎ターゲットの心理を深掘りし
⚫︎実際に試し、反応を検証し
⚫︎またブラッシュアップしていく
このプロセスを根気強く続けることで、ようやく“尖ったUSP”が形になります。
⸻
◆ もし生まれないとしたら…その原因は?
「インパクトのあるUSPが出てこない…」
そんなとき、落ち込む必要はありません。
ただ、“工夫”か、“知恵”か、“時間”のどれかが足りていないだけです。
良いUSPは、最初から“ひらめく”ものではなく、
“育てていく”ものです。
⸻
◆ あなたにしか書けない、あなただけのUSPを
成功するために、特別な才能は必要ありません。
必要なのは、**「誰のために、何をどう届けたいか」**を本気で考え抜く姿勢です。
あなたの想いと強みを、言葉にして届けましょう。
唯一無二の“選ばれる理由”――つまり「とんがったUSP」を、あなた自身の手でつくり上げてください。
それが、ビジネスを加速させ、売上を変え、あなたの未来を変える“原点”になるはずです。
<商品開発より先に「USP(キャッチコピー)」を考える>
従来のビジネスでは、「まず商品を開発し、それから販売方法を考える」という順番が常識でした。
しかし、現在のマーケティングではその順序が大きく変わりつつあります。
今は、商品をつくる前に、まず「告知文」や「キャッチコピー」を考えます。
つまり、「お客様がこの言葉を見て、心を動かすか?」
「このサービスは、本当に世の中に求められているのか?」を、先に確かめるのです。
そして、次に「市場調査をするのです。」
さらに進んだ手法として、商品がまだ完成していない段階で、
ホームページやランディングページを先に作成し、広告を打ってみるという方法があります。
これにより、実際のユーザーの反応をデータで確認できるのです。
「どのくらいの人が興味を持つのか?」「購入ボタンまで到達するのか?」
「申し込みフォームに入力するのか?」といった実際の動きこそが、
商品開発の方向性や必要性を教えてくれます。
このように、最初に市場の“リアルな声”を聞いた上で商品を形にするという流れが、
現代における最も効果的な開発手法です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
USPとは?:USP事例
● USP事例:熱々でジューシーな美味しいピザをお宅まで30分以内にお届けします。間に合わなければ、代金は頂きません。:ドミノピザ
●USP事例:口でとろけて、手にとけない:M&M’S
● USP事例:100人乗っても大丈夫:稲葉製作所
●USP事例:お、ねだん以上。:ニトリ
●USP事例:明日来るASKUL:アスクル
●USP事例:吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機:ダイソン
●USP事例:ヘアカット1000円 所要時間10分:QBカット
●USP事例:絶対に、何としてでも一晩で届けたい時に:フェデックス
●USP事例:お客さまの大切なお荷物を、安全に、そして1日で確実にお届けします。:フェデックス
●USP事例:世界最高をお届けしたい。:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
●USP事例:ポケットに1,000曲のミュージックライブラリを:アップル
●USP事例:子供と楽しめるクリスマスは、あと何回もない。:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
●USP事例:立ち読みOK:ブックオフ
●USP事例:牛一頭食べたとしても、999円。:富士屋
●USP事例:世界のどこでも48時間以内に部品交換します:キャタピラー・トラクター
●USP事例:やめられない止まらない。:カッパえびせん
●USP事例:元気はつらつ:オロナミンC
●USP事例:スグ美味しいスゴク美味しい。:チキンラーメン
これらのように、御社のUSPを作って、キラーサイト・キラー商品を作りましょう。
ーーーーーーーー
USPとは?:USPの文字数
USPの文字数は、基本30文字です。USPは、元々1行程度でした。
ただ、インターンネットの普及とともに
SEOのためにUSP文字数は、32文字になりました。
しかし、キラーサイトでは、グーグル広告を行うので、
USPの文字数は、30文字です。
グーグル広告では、15文字を自動で、組み合わせられるので、15文字+15文字です。よって全体でUSPの文字数は、30文字です。
以下に、USPの事例を載せます。
ーーーー15文字の場合ーーーー
123456789012345
アクセス増やさず売上アップHP
効果が上がるWEBを自分で作る
売上が上がるホームページ作成
ーーーーーーーーーーーーーーー
上の3つから2つをGoogleが自動で選びます。
そこで、どれがダブってもいいように、サイトの呼び方を、「HP・WEB・ホームページ」と、変えています。
また、グーグル広告に関係なく、考えた場合は、USPの文字数は、32文字です。
サイトやメルマガ、チラシ等への掲載などに使います。
以下にUSPの事例を載せます、
ーーーー32文字の場合ーーーー
12345678901234567890123456789012
アクセス増やさず、売上が上がるホームページ作成「キラーサイト」
ーーーーーーーーーーーーーーー
キーワードに、ユーアー検索数が多い、「ホームページ作成」という、フレーズも入っています。
USPの文字数は短ほどいいので、最短の場合は以下です。
ーーーー最短のUSPーーーーーー
キラーサイト
123456
ーーーーーーーーーーーーーーー
となり、結果、USPの文字数は、6文字です。この数字は、結果です。
結局、キラーサイトの場合は、いくつかのUSPがあり使い分けています。
ーーーーーーーー
USPとは?:USPの作り方!
USPの作り方の事例を紹介しましょう。
「ダイエットサービス」という普通の
サービスがあったとしましょう!
そこでUSPの考え方の手法!
●ターゲットを絞りに絞る
●オプションをたす(付ける)
●売り先をずらす(売り方をずらす)
●当たり前の逆をいく
●いらない理由から必要を発見
●型を利用する
●極力いらないものを削除する
●名前をつける「動物名」「野菜名」「果物」「遊具名」「遊園地の乗り物」
●短くする
●売れる金額を先に考え商品を作る。
●欠点を長所に変える
●日本一・世界一・日本初・世界初を使う
●マッピングする
これによって、訴求力が上がり、差別化を行う。
「ダイエットサービス」
↓
「27歳の女性専用の成功するダイエット講座」
<良いところ>
●ターゲットを絞ることによって、行う方も受ける方もしやすくなる。
●絞ることによって、アクセスは減るが、受注率は高くなる。
●「専門」を入れることによって、「プロ感」「スペシャリスト感」を出すことができる
●27歳の女性が集まることで、27歳女性のノウハウや成功事例が貯まる。
●講座にすることによって、購入者だけではなく、興味のある人が集めれるので、「見込み顧客」だけでなく、「顕在顧客」や「潜在顧客」まで、多くの方が集める。
ーーーーーーーーーーーーー
◆ USPとは? ~「USPが決まった後」に必ず行うべき確認ステップ~
USP(Unique Selling Proposition:独自の強み)が決まったら、それで終わりではありません。
実は、その後の「確認作業」こそが非常に重要です。
せっかく考え抜いたUSPでも、見せ方や使い方を間違えれば、効果が発揮されないこともあります。
ここでは、USPを決めたあとの「実践に向けたチェックポイント」をご紹介します。
⸻
◆ 1:そのUSPで「ドメイン」が取れるか?
まず最初に確認すべきは、そのUSPに関係するドメイン(URL)が空いているかどうかです。
例えば、USPが「売上アップWEB」なら、
「uriageup-web.jp」や「weburiage.com」など、ドメインとして取得可能かを調べます。
もしすでに使われていた場合は、表現の工夫やキーワードの調整が必要です。
Webでの展開を考えているなら、ドメインの取得可能性は極めて重要な要素になります。
⸻
◆ 2:検索結果に出るか?出ないか?を確認する
次に、USPに含めたキーワードをGoogleで実際に検索してみましょう。
検索結果の「出方」によって、次のような判断ができます。
▷ 検索しても“ほとんど出てこない”場合
この場合、考えられるのは:
⚫︎そのキーワードに対する検索ニーズがほとんどない
⚫︎そもそも、誰もそれを探していない
つまり、アクセスが集まらない可能性が高いということです。
このような場合は、放置せずに、Google広告などで一度テストマーケティングを行いましょう。
最初は「ガチガチ広告」(=少額で確実に反応を測るシンプルな広告)から始めるのが効果的です。
広告によって、その言葉に反応する人がどれだけいるのかを実証できます。
⸻
▷ 検索して“たくさん出てくる”場合
この場合は、競合が多いという証拠です。
そこで注目すべきポイントは以下の通り:
⚫︎上位に表示されているのは、個人の独自ドメインサイトか?それとも大手サイトか?
⚫︎ライバルたちのページに、そのキーワードが本文中にどれくらい含まれているか?
⚫︎記事の投稿日や更新日は最近か?古いか?
これらを調べることで、そのキーワードで**「戦える余地があるのか」**が見えてきます。
⸻
◆ 3:検索量と競合のバランスが取れているか?
最後に確認すべきなのは、検索数(需要)と競合状況(供給)のバランスです。
⚫︎検索されている(=ニーズがある)
⚫︎けれど、競合が多すぎず、戦える余地がある
この2つの条件がそろっている時こそ、あなたのUSPが“現実に勝てる武器”になっている証拠です。
⸻
◆ まとめ
USPは、「考えて終わり」ではなく、
市場で機能するかどうかを確かめてから本格運用することが成功の鍵です。
⚫︎ドメインは取れるか?
⚫︎検索結果は出るか出ないか?
⚫︎ライバルの強さと、自社の勝ち目は?
⚫︎Google広告でテストしたか?
これらのチェックを通じて、あなたのUSPは“思いつき”から“戦略”へと進化していきます。
ぜひ、丁寧に確認を重ねながら、「選ばれる言葉」を確実に育てていきましょう。
⸻
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆ キラー商品の作り方 ~独自USPで生み出す「売れ続ける商品」~
ビジネスにおいて、「キラー商品(=売れる核となる商品)」を持つことは非常に重要です。
なぜなら、キラー商品があるだけで、集客・販売・ブランドのすべてがスムーズに回り出すからです。
そしてそのキラー商品に必要なのが、「他にはない明確なUSP(独自の強み)」です。
つまり、“選ばれる理由”が一目でわかる商品”を作ることが、ビジネス成功への第一歩となります。
⸻
◆ 実は簡単?キラー商品は「大胆な工夫」から生まれる
キラー商品というと、「まったく新しいものを生み出さなければいけない」と思いがちですが、
実は、今ある商品やサービスに、少しの工夫や付加価値を加えるだけでも十分に“キラー化”できるのです。
たとえば、あなたが「カニ」を販売しているとしましょう。
この場合:
⚫︎【カニ+専用カニスプーン付き・限定100個】
というだけでも、立派なキラー商品になります。
✔ 限定感(数量限定)
✔ 付加価値(カニスプーン)
✔ 明確なセット内容(具体的な数・特典)
これらを加えるだけで、「選ばれる理由」が生まれ、売れる確率が一気に上がります。
⸻
◆ キラー商品づくりのコツ:大胆に、試す!
売れる商品をつくるには、**“試してみる勇気”と“思い切りの良さ”**が大切です。
たとえば:
⚫︎先着100名様限定 送料無料
⚫︎先着100名様 半額
⚫︎購入者全員に特典プレゼント
⚫︎SNSフォローで追加オプション無料
このようなキャンペーンを「期間限定」や「テスト販売」として実施することで、
反応を見ながら改善し、“売れない理由”を発見することができるのです。
⸻
◆ キラー商品づくりの10の視点
以下に紹介するのは、あなたの商品に新しい切り口を加えるための【10の発想法】です。
この視点を使って「USPのあるキラー商品」を生み出しましょう。
⸻
● 加える(+)
オプションや付属品、サービスを追加する
例:おまけ付き・専用ツール付き・2個セット
● 引く(-)
あえて機能を減らし、シンプルにする
例:高機能モデルから機能を削る/必要最小限セット
● 掛け合わせる(×)
異なる商品・分野と組み合わせる
例:カニ × 温泉旅行券/本 × 動画解説
● 割る(÷)
サイズ・量・価格を“分割”して提供する
例:小分けセット/1週間分お試しパック
● 時間軸を変える
過去・現在・未来に視点をずらす
例:昔ながらの味/未来を変える学び/今すぐ使えるツール
● 空間軸を変える
対象エリアや距離感を変える
例:地域限定商品/海外向けアレンジ/アウトドア用バージョン
● バリューチェーンを変える
流通・製造・販売のどこにフォーカスするかを変える
例:生産者直送/メーカー直販/現場体験付き
● 他ジャンルへ移す
異業種のノウハウを応用する
例:料理の方法をビジネスに応用/教育 × エンタメ
● 逆転する(ひっくり返す)
視点をまったく逆にして考える
例:購入後全額返金保証/買わない理由を広告にする
● 価格を極端に変える(高額・無料)
金額で印象を操作する
例:プレミアム版10倍価格/あえて無料にして集客
⸻
◆ まとめ:キラー商品は「工夫の重ね」で生まれる
キラー商品は、ゼロから生み出す必要はありません。
今ある商品やサービスに、ちょっとした“とんがり”を加えるだけで、
お客様にとっての魅力がグッと高まり、「買う理由」になるのです。
大切なのは、「大胆に考えること」と「試してみること」。
あなたのビジネスにふさわしい、唯一無二の“キラー商品”を、
ぜひこの機会に創り上げてみてください。
4−3)未来経営「未来商品」→高額戦略
ビジネスにおいて、低価格で大量に売る「薄利多売」も一つの戦略ではあります。
しかし、安いものには弱点があります。
<安いもの>
安いものは安いものと比較される
原価にお金をかけれない。
販売にお金をかけれない。
サポートにお金をかけれない。
クレームの対応にお金をかけれない。
ファンにもならず、常に安物を探す人が、顧客になる。
だからリピートしない。
そこで、「高額戦略」です。
高額かつ高利益の商材を開発・提供する戦略を持つことも非常に重要です。これを「高額価格戦略」と呼びます。
価格が10%~20%高いと比較する。
価格が2~10倍高いと人は麻痺する。
値下げスパイラルからの脱出です。
★感動するものを提供する。
★口コミで広がる
★高いけど、安いと、感じる
<高いもの>
原価にお金をかけれる。
販売にお金をかけれる。
サービスの質を上げれる
サポートにお金をかけれる。
クレームの対応にお金をかけれる。
顧客の感動が自然と口コミになる
新規顧客を獲得し、
リピートにも働き
ファンになって、本当の顧客になる。
リピートしてくれる。
<マーケティング効果と理論>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【ヴェブレン効果(Veblen Effect)】
経済学者ソースタイン・ヴェブレンが提唱。
高価格そのものが「ステータス」や「希少性」の象徴となり、需要が増える現象。
高級時計、ブランドバッグ、限定車などが典型例。
価格を上げた方が「価値が高い」「持っている自分が特別」と感じられ、購買意欲が刺激される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【スノッブ効果(Snob Effect)】
他人と同じ物を持ちたくない心理から、希少で高価なものを選ぶ現象。
特定の層だけが所有できる商品(限定生産、シリアルナンバー入りなど)でよく起きる。
「誰でも買える物ではない」ことが価値になる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【プレスティージ価格効果(Prestige Pricing)】
高価格設定によって品質の高さや信頼性を連想させるマーケティング戦略。
ワインの実験では、同じワインを「5ドル」と伝えたグループより、
「45ドル」と伝えたグループの方が、味の評価が有意に高かった。
脳の快楽中枢も実際に強く反応していた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【ギャラティ価格効果(Price–Quality Heuristic)】
「高い=品質が良い」という思い込み(ヒューリスティック)。
特に専門知識がない分野ではこの傾向が強く、
価格を引き上げることで購買率が上がる場合がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【ヴェブレン効果 × ファン形成】
高価格は「品質も高く」「ステータスシンボル」としての価値を持つため、
購入者はブランドの“仲間意識”を持ちやすい。
これがコミュニティ形成や熱狂的ファンの土台になる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【ロイヤルカスタマー化のフィルタリング効果】
高価格設定は、価格に見合う価値や商品価値を理解し、
長期的に関係を築ける層だけを自然に集める。
結果として、顧客単価・リピート率・LTVが上昇する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【プレミアム効果(Premium Effect)】
価格が高いほど、顧客はそれを「特別」「希少」と認識しやすく、
購入後の満足度や愛着が高まる現象。
愛着が強いほどリピート率も上がりやすくなる。
4−4)未来経営「未来商品」→未来顧客獲得
貴社の諸品をどんな顧客に、買ってほしいですか?
現在の顧客は、本当に理想の顧客ですか?
安いものを好む顧客は、
常に安いものを求めてさまよいます。
毎回、購入する商品や購入先がちがいます。
「安売り」「クーポン」「値引き・割引」「おまけ」に
しか、反応しないのです。
本当の御社のファンではありません。
しかも、リピートも口コミもしないのです。
本当の御社のファンを作りましょう!
4−5)未来経営「未来商品」→【サブスク】
「サブスク」はもともと subscription(サブスクリプション) の略で、
日本語にすると状況によって違いますが、主にこんな言い方になります。
-
定額制サービス(一番広く使われる)
-
定額課金、月額課金(料金体系を説明するとき)
-
会員制サービス(会員登録と継続課金が前提のとき)
-
継続購入、定期購入(モノや商品配送の場合)
ーーーーーーーー
<サブスクリプション型モデルの魅力と可能性>
従来のビジネスモデルでは、
商品やサービスの販売は「単発」で終わることが多く、
一度きりの売上や入金で完結してしまうケースが大半でした。
しかし、近年注目されているのが「サブスクリプション(定期課金)型モデル」です。
これは、商品やサービスを継続的に提供し、顧客から月額や年額で料金をもらい続けるという仕組みです。
たとえば、一度に100万円の売上を得るよりも、
月額10万円の契約を獲得した方が、
1年間で120万円、2年間で240万円と
、長期的には遥かに大きな収益を生む可能性があります。
さらにサブスクモデルには、以下のような経営上のメリットがあります:
⚫︎継続的な売上があるため、売上がが安定し、予測できる
原価も経費も予測しやすい
⚫︎継続的な収入があるため、キャッシュフローが安定する
⚫︎将来の売上や利益を予測しやすく、経営計画が立てやすい
⚫︎顧客との関係が長期化しやすく、アップセル・クロスセルにもつながる
このように、安定性・拡張性・収益性という3拍子がそろったサブスクモデルは、
現代のビジネスにおいて最も理想的な収益構造のひとつといえるでしょう。
だからこそ、新しい商品やサービスを開発する際には、
「どうすればこれをサブスクリプション化できるか?」という視点を持つことが、
今後の経営戦略において非常に重要です。
4ー6)未来経営「未来商品」【未来商品】と【付加価値販売】
商品戦略を考える時に、
大事なのは売上です。
LTV「ライフタイムバリュー」の
売上をあげましょう!
「ライフタイムバリュー」とは、
1人の顧客が取引を始めてから
関係が終わるまでに企業にもたらす総利益。
★普通は一生というより、2〜3年間で計算します。
<商品戦略:売上まとめ>
1)高額戦略:商品単価を上げる。
2)付加価値販売:お得ではなく、価値で売る
3)ハイブリット販売:良いものを仕組みで販売する
4)リピート販売:顧客継続でかってくれる仕組み
5)サブスク販売:年契約・毎月購入してくれる
ーーーーーーーーーーーー
1)高額戦略
ーーーーーーーーーーーー
商品が安いと、顧客に感動を与えにくくなります。
また価格が安いと、商品にまつわる前後のサービス。
カタログ、サンプル、カートシステム、
コールセンターにもお金をかけられない。
その結果、顧客体験の質が下がり、
リピートやブランド化が難しくなります。
逆に高品質・高額商品だと、しっかり利益が出るので、
いい材料で、優れた職人が丁寧に作り、
その商品にまつわる前後のサービス。
カタログ、サンプル、カートシステム、
コールセンター、サポート、検品・返品、
すべてに十分な資源を投じられます。
その結果、顧客に感動をあたえられます。
ーーーーーーーーーーーー
2)付加価値販売
ーーーーーーーーーーーー
商品を販売する時に、2つのほうほうがあります。
「お得の価値」で販売する方法と
「商品の価値」で販売する方法です。
<商品のお得戦略>
値引き・クープン・ポイント・「お得感」で販売する
安売りの戦略は、「お得の価値」で売っていく方法です。
確かに売りやすく、一時的に売りやすく売上は上がりますが、
やがて顧客は「セール」「安売り」を待つようになり、
通常価格では売れにくくなっていきます。
「お得」を期待する顧客があつまり、
本当のファンが集まりにくい傾向があります。
キャンペーンで売れると、
顧客は「セール」や「安売り」を待つようになり、
自然に売れなくなっていきます。
さらに利益が少ないので、
商品・材料・製造過程・パッケージ・売方・サポート
交換・返品・マーケティング・イベントにお金をかけれずに、
顧客に感動を与えることが難しく、
結果的に大きな売上・利益につながりにくくなります。
<商品の価値戦略>
一方、高額販売は、
本当に価値ある商品を提供する戦略です。
価格が高いため、販売は難しいですが、
良い商品ができれば顧客に感動を与えることができ、
本当のファンが生まれます。
ファンは自然と口コミをしてくれ、
口コミで広がっていくことと、
お得感を出さないないことで、
ファンが常に買ってくれて、
リピートが増え大きな売上や
ブランド形成につながります。
価値戦略は、利益が多いので、
商品・材料・製造過程・パッケージ・売方・サポート
交換・返品・マーケティング・イベントにお金をかけれて、
顧客に感動を与えることができます。
結果的にさらに大きな売上・利益につながっていきます。
価値戦略は、ファンが生まれ、自然とブランドが育っていきます。
欠点は、高価格ゆえに最初の販売ハードルが高い点です。
しかし、そのハードルを越えた先に、長期的なLTVの成長が待っています。
ーーーーーーーーーーーー
3)ハイブリット販売
ーーーーーーーーーーーー
そこで、ハイブリッド戦略。「本当に良いもの」を高額で、
「仕組み」と「キャンペーン」で販売する。
商品とブランドとサポートの良さが伝わるように、サイトに特に力を入れる。
商品の良さが伝わるように、「実績」「顧客の声」の収集に力を入れる。
サイトは、将来的には、
⚫︎新規顧客サイト
⚫︎リピートサイト
⚫︎使い方サイト
⚫︎サポートサイト
⚫︎離脱サイト
を別々に作るのも良い。
また、
<ハイブリッド:キャンペーン>
⚫︎しないこと:安売り・値引き・クーポン・「お得」で販売しない。
⚫︎行うこと:個数限定・今日限定・特別仕様・先行販売・新デザインなどを打ち出して販売する。
ーーーーーーーーーーーー
4)リピート販売
ーーーーーーーーーーーー
売上の本質は「新規」ではなく「継続(リピート)」にあります。
どれだけ新しい顧客を集めても、リピートされなければLTVは上がりません。
リピート販売とは、一度買ってくれた顧客が、もう一度買ってくれる仕組みを作ることです。
これは偶然ではなく、「仕組み設計」で生まれます。
⚫︎リピートが生まれる仕組み
1)商品・サービスが本当に良い(品質・体験・感動)
2)顧客管理がしっかりしている。
3)買った後のフォローが丁寧(お礼メール・DM・LINEなど)
4)サポートがいい。交換・返品(サポートを行う前に良さが伝わる)
5)ブランド(安定している)「商品が感動・安心・安全・信頼・共感・安定・期待・誠実・遊び心」
6)「また欲しくなる理由」がある(限定・季節・新機能・新デザイン・アップデートなど)
7) 顧客との関係が続く(ニュース・イベント・メッセージなど)
大事なこと
★顧客リストを資産として育てる
★購入データを分析して「次に何を買うか」を予測する
★顧客との接点を増やし、安心と信頼を育てる
リピート顧客は「新規顧客の5倍以上の価値」があると言われます。
新規を増やすより、既存顧客を大切にするほうが、
確実に利益率が高く、経営が安定します。
新規とリピートの率はだいたい、
1)最低、新規:リピート=4:6
2)普通、新規:リピート=2:8
3)最高、新規:リピート=1:9
新規が少ないのでは、ありません。
りぴーとがおおいのです。
★顧客が「御社から買いたい」と思う状態をつくること。
それがLTVを最大化する最強の戦略です。
ーーーーーーーーーーーー
5)サブスク販売
ーーーーーーーーーーーー
サブスクリプション(subscription)とは、
「定期的に支払いをして、継続してサービスや商品を受け取る仕組み」です。
これを導入すると、売上が“積み上がる”ようになります。
つまり、毎月の売上がゼロからスタートしない。
「翌月も、前月の顧客が残っている」状態を作れるのです。
<サブスクの魅力>
⚫︎ 売上が安定し、経営の見通しが立つ
⚫︎ 顧客との接点が継続するため、信頼関係が深まる
⚫︎ 顧客データが蓄積され、改善や提案がしやすくなる
⚫︎ 顧客が「辞める理由」が少ないと、LTVが自動で上がる
<サブスクの設計ポイント>
1)月額または、隔月プラン、年額プランを用意する
2)ここで初めて、「値引き」を使います。
12ヶ月で12万円を
12ヶ月で10万円
3)「解約しづらい理由」を作る(特典・限定情報・サポートなど)
4)定期的なアップデートや新サービスで飽きさせない
5)コミュニティ化して、顧客同士のつながりをつくる
たとえば、あなたの「AI日報」や「My参謀AI」はまさにサブスク型。
顧客が月ごとに成長を感じ、離れられない仕組みをつくれば、
売上は積み上がり、LTVは劇的に伸びていきます。
ーーーーーーーーーーーー
★)まとめ
ーーーーーーーーーーーー
1)高額戦略=単価を上げ、感動で売る。
2)付加価値販売=お得でなく、価値で売る。
3)ハイブリッド販売=価値×仕組み×キャンペーンで売る。
4)リピート販売=顧客の信頼を育てる。
5)サブスク販売=顧客との関係を継続する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ハイブリッド限定事例:100個
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(1)数量・期間で限定する(希少性を演出)
⚫︎個数限定
⚫︎期間限定
⚫︎一日限定
⚫︎一週間限定
⚫︎一か月限定
⚫︎季節限定(春モデル・冬モデルなど)
⚫︎年間限定モデル
⚫︎一度きり生産
⚫︎年に一度の復刻版
⚫︎残りわずか販売
(2)顧客属性で限定する(所属・特権を演出)
⚫︎会員限定販売
⚫︎VIP限定販売
⚫︎既存顧客限定販売
⚫︎過去購入者限定
⚫︎ファンクラブ限定
⚫︎紹介者限定(紹介された人だけ)
⚫︎学生限定
⚫︎女性限定
⚫︎27歳限定
⚫︎経営者限定
⚫︎地域限定(福岡限定・関西限定など)
(3)時間軸で限定する(スピード×特別感)
⚫︎先行販売(一般販売前)
⚫︎先着限定
⚫︎先行予約限定
⚫︎発売初日限定特典
⚫︎早期購入者限定プレゼント
⚫︎24時間限定販売
⚫︎日付指定販売(10月10日10時販売など)
⚫︎午前中限定販売
⚫︎月初限定販売
⚫︎イベント期間中限定販売
(4)コラボ・タイアップで限定する(希少コラボ)
⚫︎有名職人とのコラボ限定品
⚫︎アーティストコラボ限定
⚫︎ブランドコラボモデル
⚫︎芸能人監修モデル
⚫︎企業タイアップ限定
⚫︎大学研究所コラボ限定
⚫︎伝統工芸×最新技術モデル
⚫︎地元素材×世界技術モデル
⚫︎海外限定モデルの逆輸入版
⚫︎展示会限定販売
(5)デザイン・仕様で限定する(バリエーション価値)
⚫︎新デザイン先行版
⚫︎材料限定(材質限定)
⚫︎カラー限定(限定カラー・限定色)
⚫︎限定パッケージ
⚫︎限定素材
⚫︎限定サイズ
⚫︎限定シリアルナンバー入り
⚫︎サイン入りモデル(デザイナー・オーナー・社長)
⚫︎特別仕様版(Pro/Anniversary/Goldなど)
⚫︎記念モデル(創業○周年など)
⚫︎廃盤前最終モデル
(6)ストーリー性で限定する(感情価値を高める)
⚫︎職人の手仕事限定
⚫︎「最後の1ロット」販売
⚫︎顧客の声から生まれた限定品
⚫︎試作品販売(数量限定)
⚫︎創業者セレクト限定
⚫︎伝説のレシピ再現限定
⚫︎偶然の失敗から生まれた限定モデル
⚫︎過去の名作再現モデル
⚫︎ストーリー冊子付き限定商品
⚫︎“最終章モデル”としての限定販売
(7)イベント・体験型限定(体験で価値を上げる)
⚫︎イベント来場者限定販売
⚫︎展示会限定
⚫︎試食・体験会限定
⚫︎ワークショップ参加者限定
⚫︎オンラインセミナー限定販売
⚫︎クラウドファンディング限定リターン
⚫︎店舗来店者限定販売
⚫︎内覧会限定販売
⚫︎招待制販売会
⚫︎シークレットイベント限定
(8)デジタル・オンライン限定(デジタル特典型)
⚫︎オンラインショップ限定
⚫︎メルマガ限定URL販売
⚫︎SNSフォロワー限定販売
⚫︎YouTubeライブ限定販売
⚫︎LINE登録者限定販売
⚫︎インフルエンサーコード限定販売
⚫︎動画限定クーポン付き販売
⚫︎公式アプリ限定販売
⚫︎デジタル会員限定販売
⚫︎NFT所有者限定販売
(9)カスタマイズ・特注型限定(個別価値で差別化)
⚫︎名前入り限定モデル
⚫︎オーダーメイド限定枠
⚫︎限定カスタムカラー
⚫︎世界に一つだけのプラン
⚫︎あなただけの組み合わせ限定
⚫︎受注生産限定
⚫︎一人ずつ設計モデル
⚫︎限定相談付き商品
⚫︎専用チューニングモデル
⚫︎限定ギフトパッケージ販売
(10)記念・特典・祝福限定(感情+所有欲)
⚫︎誕生日限定モデル
⚫︎記念日限定販売
⚫︎創業記念限定
⚫︎○○達成記念販売
⚫︎ファン数突破記念限定
⚫︎新ブランド立ち上げ記念限定
⚫︎初回購入者証明書付きモデル
⚫︎サイン証明書付き限定販売
⚫︎ストーリーブック付きモデル
⚫︎名前刻印入り限定版
5-1)マーケティング「未来販路」→【獲得型】
一般的に企業は、「マーケティング」とは「集客」と考えます。
そこで、【アクセス型】の集客を行うのです。
しかし、未来経営では、
「マーケティング」とは「利益」を出すこと。
と、考えます。
大きな市場から、大きな利益を、確実に取る。
そしてそれを継続的に得るのです。
そのためには、
先に行うのは「アクセス」を増やすのではなく、
先に「獲得」を行うのが最も大事です。
それが、【獲得型】マーケティングです。
ーーーーー
実は、アクセスが、増えれば、
「獲得」が増えると思われていますが、
これは、大きな、勘違いです。
確かに、「獲得」を重視した。
「マーケティング手法」が「会社全体」に、確立されていて、
すでに「獲得」ができていれば、
その上で「集客」すれば、
アクセスが増えたら「獲得」が増え売上は上がります。
しかし、「獲得型」マーケティングを行わず、
先に「アクセス型」や「SNS」を行って、
アクセスが増えても、
「獲得」は、思うように伸びません。
ーーーーーーーー
【選択の化学】「一番売りたい物に絞る」【正式には選択の心理学】
コロンビア大学ビジネススクールの教授
シーナ・アイエンガー(Sheena Iyengar)博士(アメリカ人の社会心理学者)
スーパーの試食販売コーナーで、24種類と6種類のジャムを用意して実験。
視聴と購入比較。
<立ち寄り>「アクセス」
24種類の方、60%の人が立ち寄る。
6種類の方、40%が立ち寄る
<購入>「獲得」
24種類の方、約3%が購入。
6種類の方、約30%が購入。
選択肢が少ない方が購入率が10倍高かった。
★選択肢が少ない方が、迷いが減り、行動に移しやすくなった。
ーーーーーーーー
<マーケティングとは>
買わない人のアクセスを増やすのではなく。
買う人だけのアクセスを増やすのです。
「アクセス型」戦略
↓
「獲得型」戦略
アクセス主義から獲得主義へ
5-2)マーケティング「獲得型」成功実績
「アクセス数は10分1、売上は100倍へ」
あるサイトで、『アクセスは10分の1になったのに売上が100倍』
になった事例を解説します。
<簡単解説>
当初、あるサイトではターゲットを広く仕掛け、
アクセスを増やす戦略で行っていました。
私がマーケティングに入り「獲得型」に変更しました。
ターゲットを絞り、入口もサービスもコンテンツもUSPも
連携しました。
すると、沢山のマンションが売れました。
しかも、購入までの日数も10分の1以下になりました。
<行った10個の事>
⚫︎ターゲットを絞る(ニッチ化)
⚫︎コンバージョン(CV)つまり申込に特化したサイトを作る(アクセス型ではなく獲得型)
⚫︎コンテンツ・サービス・比較表をターゲットだけ絞る。
⚫︎文章と写真の質と量を4倍にした。
⚫︎USP(キャッチコピー)や尖った文章の活用
⚫︎最初:広告(ガチガチ広告)→その後、SEOのみ
⚫︎視覚的分析とGoogle AnalyticsやConsoleのデータ分析を組み合わせたハイブリッド分析
⚫︎購入者、資料請求者、座談会、見学者、明確な対象とした設計
⚫︎価格のターゲット別詳細掲載(家賃別)
⚫︎実績掲載(ユーザーの声:V時回復インタビュー)
<詳細解説>
当初、あるサイトでは「中古マンション」の販売を行っていました。
沢山の方に売りたいので、アクセスが増えるようにターゲットを広く設定し、
アクセスを増やす戦略で行っていました。
元々、『1年間で1件』しかサイトから売れていませんでした。
私がマーケティングに入り「獲得型」に変更しました。
ターゲットを絞り、入口もサービスもコンテンツもUSPも
ターゲットだけ絞り、連携しました。
すると、問い合わせが増え沢山のマンションが売れました。
改善後1年で、
『アクセス数は10分の1」になったのに
『マンションが1年間で100件売れ(契約まで)』
『売上が100倍』になりました。
しかも、サイトの問い合わせから購入まで
平均2週間になりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
市場拡大>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
少子化(人口縮小)
その地区からの人の流出
その年代の人口(人口縮小)
→常に自分の狙っている人口を把握しておく。
→より多い人口のターゲットを狙う!
マーケティングは、SNSでは、ありません。
<実験思探>
実験思探(じっけんしんたん):実験を通して真理を探る
何事も「やってみなけりゃ、わからない。」
「知るより、やってみる。」
「検証なき成功は、ただの偶然だ。」
「答えは、やって初めて生まれる。」
「プランより行動」
divDIV:V時回復:https://www.clipinc-web.com/miraikeiei#5-2
5-3)マーケティング「V字回復コンテンツ」「V字回復原稿」
「成功事例」「成功実績」「お客様の声」
僕が大事だと思っている「V字回復」の原稿や思想。
「起業・経営・経理・商品・ブランド・売上アップ・営業・求人・人事・組織・管理・業務・デジタル・市場」の経営15項目の全部に使えるだけでなく、USP・告知・広告・サイト・FB・成功事例・インタビュー・チラシ・企画書・借入と何にでも使えるからです。
ーーーーー
<V時回復について>
コンテンツ((原稿)に「V字回復」(起承転結)を入れる。
コンテンツへの「V字回復」原稿とは、
ユーザーに一度、その商品やサービスを解説し、
途中で一度落胆させ、
その後に復活させることを言います。
コンテンツ(原稿)で、商品やサービスを紹介するする時や、
利用者の声の時に、原稿に、「V字回復」を入れる。
あえて、途中に自分の疑問や困ったこと、悩みを入れて、
そして、それが、解決したことを記載しましょう。
それによって、その商品やサービスが、問題解決するモノだと伝えましょう。
<起承転結(V時回復)>
1)はじめに(自己紹介)
2)行ったこと
3)その疑問や弱点を入れる
4)それを覆すこと
V字回復にすることで、その商品やサービスが、
共感されやすくなり、効果が上がります。
ーーーーーーーーーー
<活用方法>
以前ホームページを作っているときに、
弊社のホームページの流れ、
元々のコンテンツの並びは、
1)企業コンセプト
2)会社紹介
3)商品サービス紹介
4)サービスの流れ
5)成功事例(お客様の声):まとめ
6)成功事例(お客様の声):詳細
でした。
しかし、私たちのサービスが新しいサービスだったので、
他者との違い、他者と比べての差別化を訴えても
申し込みは、全くありませんでした。
そこで、弊社のホームページのトップの
コンテンツの順番を大きく変えてみました。
1)成功事例(お客様の声):まとめ
2)成功事例(お客様の声):詳細
3)企業コンセプト
4)会社紹介
更に以下を完全に外したのです。
3)商品サービス紹介
4)サービスの流れ
もちろん、上記は、サイト解析・分析・研究の結果です。
すると、サイトからの「申し込み」「問い合わせ」も、
増え、それから、営業することもなく、
常に受注がありました。
もちろんアクセスも増えたのです。
<研究方法>
サイトの中のどこに興味があるのかを、
分析するために、あえて、ページを分けたのです。
ホームページを、以下に分けました。
これは、LPではできません。
⚫︎トップページ(事業紹介)
⚫︎商品紹介
⚫︎業務の流れ
⚫︎成功事例(お客様の声)
⚫︎会社案内
⚫︎スタッフの声
すると、1番アクセスがあったのが、
「⚫︎成功事例(お客様の声)」だったのです。
そして2番が「⚫︎会社案内」です。
そこで、トップページに、
この2つだけを載せたのです。
ーーーーーーーーーー
<V字回復:原稿事例1:新商品>
新製品を開発し、販売する。
1)お花をプレゼントすることは、素晴らしいと思っていた。
2)全国にプレゼントが、できるネットワークとサービスを構築。
3)届く頃に枯れてしまう。
4)届ける日を設定することで、逆算して届き、届く時に輝いている花になるサービスへ。
<V字回復:原稿事例2:銀行借入>
銀行に借入をするために銀行に交渉に行く時
1)まだ、改善されていない、最悪な決算書を持っていく
2)銀行員に相談し、今後どうすれば、借りれるいのか? どこをどう具体的に改善する数字を聞いておく。
3)銀行に言われたように改善し、途中でも持っていく
<V字回復:原稿事例3:求人要項>
求人募集要項に原稿を書く場合
1)以前は男性社員が多く「女性の採用」「女性のキャリアアップ」「女性管理職の登用」に対する取り組みが十分ではありませんでした。
2)そこで、女性社員一人ひとりの「ライフステージ」を丁寧にヒアリングし、そのライフステージに合わせた制度や働き方を導入しました。
3)現在は、「女性活躍」を全社方針として位置づけ、ライフステージに対応した柔軟な支援体制を整備し、「女性管理職の育成と登用」も強化しています。
<V字回復:原稿事例3:成功事例>
1)当初は「1つのサイト」のみで展開しており、売上は約2億円にとどまっていました。
2)しかし、社内だけのマーケティングにおける「成長の限界」を感じ、外部のコンサルティング会社に依頼しました。
3)その結果、サイトを「新規顧客獲得用」と「既存顧客リピート用」の2つに分割し、それぞれに特化した戦略を実行しました。
4)それにより、それぞれの「CVR(成約率)」が大幅に改善し、広告費をほとんど増やすことなく、
売上は1年で「10倍」に成長しました。
日本人は「V字回復」の物語が好きです。
たとえば『ビリギャル』「高校2年時点で偏差値30、学年ビリだったギャルが、たった1年で偏差値を40上げ、慶應義塾大学に現役合格した実話」があります。
最初から優秀だったり、コツコツ努力してきた人の話では、ここまでのドラマにはなりません。この「一度落ちてからの大逆転」という構造こそが、人の心を強く揺さぶるのです。
このV字回復のストーリーは書籍化され、さらに映画化もされました。
彼女(小林さやかさん)はその後、アメリカ・コロンビア大学教育大学院に留学し、認知科学を学び、現在は教育研究・講演・執筆など幅広く活動を続けています。
5−4)マーケティング「未来販路」→【選択の化学】(選択の心理学)
一番売りたい物に絞る【選択の科学】
<大学実験:選択の化学>
コロンビア大学 ビジネススクールの教授
⚫︎シーナ・アイエンガー(Sheena Iyengar)博士
シーナ・アイエンガーは、コロンビア大学ビジネススクールのS.T.リー寄付講座経営学教授で、イノベーションハブのアカデミックディレクターであり、また、選択と問題解決に関する世界的な専門家の一人である。
スーパーの試食販売コーナーで、24種類と6種類のジャムを用意して比較。
選択肢が少ない方が購入率が10倍高かった。
→僕の実験では、1個が最強だった。
有名な「ジャム実験」では、24種類並べた場合の購入率は約3%、6種類に減らすと約30%に増加しました。
た、価格を提示する際、1,000円の商品を先に見せると500円の商品が割安に感じられる
「アンカリング効果」や、同じ結果でも「90%成功」と「10%失敗」で選択傾向が変わる
「フレーミング効果」があります。
さらに選択肢が多すぎると決断までの時間は平均で約2倍かかり、満足度も低下します。
<詳細>
彼女は、市場で提供される商品についての考え方や、顧客のためにそれらをどのように収集・整理するかについての考え方を変え、「ジャム・スタディ[青美1] 」を提唱したことで有名である。彼女の提唱する "ジャム・スタディ"とは、選択肢が多すぎると顧客の購買意欲が低下し、企業の成長も低下する、という研究である。ジャム・スタディ提唱以来、選択過多の現象に関する研究は1,000を超え、「企業の成果(アウトプットと収益)の80%は、20%の原因(インプットと選択)から生まれる」という80/20の法則が広まった。そして、選択に関する専門知識を生かし、ビジネス、テクノロジー、消費者小売、メディア、コンサルティング、投資、STEMなど、幅広い分野の企業数百社に対し、意思決定基準を変革し、ステークホルダーの経験を向上させるためのアドバイスを行っている。
<マーケティング効果と理論>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【お店で作っている感を出す「ミラーニューロン効果」】
「ライブ製造=信頼が増す」効果(心理学・神経科学)
寿司カウンター、目の前で握るライブ感=「信用して食べられる」
→ 人間は、見えないものに対して「不信」「疑念」を感じる性質がある
ミラーニューロン(観察しているだけで、自分も同じ体験をしているように反応)
→ 見ているだけで「食べたい」「自分も欲しい」という感情になる
【便利な鍋が届いたふうにする:記憶に残る価値”=「エクスペリエンス・エコノミー」理論】
【「体験価値」こそが、価格の正当化になる】
→商品単体だと「比較対象」になる
→体験があると「唯一の思い出」になり、“価格競争”から脱却できる
【アンカリング効果】
アンカリング効果とは、最初に提示された数値や情報(アンカー=錨)が、その後の判断や評価に強く影響を与える心理効果です。
たとえば、あるワインを売るときに…
⚫︎先に「この高級ワインは1本1万円です」と見せたあとに、別のワインを「こちらは5,000円です」と提示すると、多くの人が「安い」と感じます。
⚫︎逆に、先に「このワインは1本2,000円です」と見せた後だと、同じ5,000円ワインが「高い」と感じられやすくなります。
この現象は価格だけでなく、アクセスや成約にも直結します。
ECサイトのデータでは、最初に高価格帯の商品ページを見せた顧客は、その後の平均購入単価が15〜30%高くなる傾向があります。
アンカリングは日常にも溢れています。セールで「通常価格15万円 → 特別価格10万円」と表示されると、10万円が安く感じるのも同じ原理です。
この効果を意図的に使えば、アクセス数は変わらなくても、平均購入額や成約率を底上げできます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【フレーミング効果】
⚫︎「成功率90%」と伝えられると、多くの人が安心して受けようとします。
⚫︎同じ手術を「失敗率10%」と伝えると、不安が強まり受けたくなくなる人が増えます。
どちらも意味は同じですが、ポジティブに聞こえる表現とネガティブに聞こえる表現では、
人の感情が大きく揺れ動きます。
マーケティングでは、「残りわずか」「期間限定」など緊急性を強調するネガティブ寄りのフレーミングや、
「送料無料」「今なら+20%増量」など得を強調するポジティブ寄りのフレーミングを使い分けます。
実験では、同じ商品の説明でも表現を変えるだけで購買率が10〜20%変動することが確認されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【デコイ効果(おとり効果)】
選択肢に「わざと魅力のない中間案」を入れることで、
本当に売りたい商品を選ばせやすくする現象。
-
Sサイズ:500円
-
Mサイズ:800円(おとり)
-
Lサイズ:850円(売りたい)
→ MがあることでLが割安に感じられ、Lの購入率が上がる。
実験ではLの選択率が約30%→70%に跳ね上がる例も。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【松竹梅の法則】
3つの価格帯を並べると、人は中間を選びやすいという傾向。
寿司屋やコース料理でよく使われる。
「梅:3,000円」「竹:5,000円」「松:8,000円」と並べると竹が一番売れる。
アクセス解析では、3段階構成にした場合、成約率が1.2〜1.5倍になるケースもある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【希少性の原理(スキャーシティ効果)】
残りが少ないと購買意欲が高まる心理。
「残り3点」「あと2時間で終了」など。
Amazonの「残り○点」表示で成約率が約2倍に上がる事例あり。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【社会的証明(ソーシャルプルーフ)】
他人の行動を参考にして選択する心理。
「売上No.1」「レビュー数1,000件以上」「購入者の90%が満足」など。
レビュー表示の有無だけで、購入率が最大20%変わるデータもある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【損失回避の法則(プロスペクト理論の一部)】
人は得をする喜びより、損を避ける心理の方が強い。
「買わないと損」「期間内に申し込まないと割引が消える」といった訴求が有効。
5−5)マーケティング「未来販路」→【獲得型】
営業戦略の考え方を変えるのです。
リアルでもネットでも同じです。
一生懸命告知し、買わない人(購入率が低い人)を集めて、
いつか、買う人をイメージして、集客するのではなく、
買う人(購入率が高い人)を集めて、販売するのです。
私のマーケティングの事例です。
ある会社は、営業が強い会社でした。
集客をして、リストを集め
買う気がない人に、無理やり、売っていくのです。
なかなか売れず、クレームも多かったのです。
そこで、営業方針を大きく変えました。
営業を3分の1にし、そのお金を
マーケティングに投入したのです。
今までの集客【アクセス型】では、なく、
【獲得型】のマーケティングです。
さらに商品も強化されました。
営業経費が減ったので、商品に費用をかけれるようになったのです。
すると、買いたい人が集めるので、
営業はしやすくなり、
売上も5倍に増えました。
さらに、クレーム減りました。
その企業は上場しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<会社の変革と成長>
1)個人事業主期(目安:社長 1人)
→「マーケティングとは集客」と思ってやっていた。
→告知と広報」に力入れていた。
2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)
→「マーケティングとは雑誌掲載」と思ってやっていた。
→「雑誌掲載」に力入れていた。
→「雑誌掲載」戦略を考えて実践していた。
→年間200本掲載されていて。
3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)
→「マーケティングとは利益」と思ってやっていた。
→自社のサービスは、自社の利益とクライアントの利益」と思っていた。
4)企業化期(目安:社員数 約100人)
→自社オフィスが「最大のマーケティング」と思ってやっていた。
5−6)マーケティング「未来販路」→【デザイン】
私は、デザイン(意匠・外観)よりも、コンテンツ(原稿や写真や図)の方が大事だと考えています。
なぜなら、伝えたいこと・伝えるべきことを、詳しく、正確に、深く表現した方が売れると思うからです。
ただし、コンテンツの質と量が十分に揃った段階では、デザイン(意匠・外観)も重要だと考えます。
そこで、デザインについても記載します。
<基本の考え方:情報発信には「2つの全く異なる目的」がある>
ビジネスにおいて「デザイン」や「広告」、あるいは「SNS」などを活用する際、
すべての情報発信には大きく分けて2つの明確に異なる方向性があります。
【1】「集客」を目的とした発信
【2】「申込」や「受注」を目的とした発信
⸻
【1】「集客」を目的とした発信
これは、より多くの人の目に触れさせ、「アクセス数」を増やすこと、
つまり「認知度」や「話題性」を高めることに特化した発信です。
⸻
【2】「申込」や「受注」を目的とした発信
こちらは、商品やサービスの「申込数」や「成約数」、
「会員登録」や「購入」など、具体的なアクションを生み出すことを目的としています。
⸻
この2つは一見似ているように思えるかもしれませんが、実際にはまったく異なる性質を持つものであり、戦略も方向性も全く異なるものです。
⸻
<よくある誤解:「アクセスを増やせば申込も増える」は間違い>
多くの方が陥る典型的な勘違いに、「とにかくアクセスを増やせば、申込も自然に増えるはずだ」という考えがあります。
しかしこれは、実際のマーケティング現場では全く通用しない考え方です。
⸻
<例で考えてみましょう>
極端な例を挙げてみます。
仮にあなたが「カレー」を売りたいとします。
その際に、「1,00万円プレゼント」と大々的に広告を打てば、
確かに多くの人がアクセスしてくるでしょう。
しかし、カレーに関心がある人ばかりが集まるわけではありません。
その結果、申込率はほとんど伸びない可能性が高いのです。
一方で、「カレーを無料でプレゼント」という企画であれば、アクセス数はそれほどでなくとも、
カレーに興味のある人が集まりやすく、申込率は高くなる傾向にあります。
⸻
<結論:目的によって戦略は全く異なる>
このように、「ただアクセスを増やしたい」のか、「申込を増やしたい」のかによって、打ち出すべき施策やコピー、デザイン、配信タイミングなど、全ての戦略が根本的に変わってくるのです。
ですから、情報発信を行う際には、まず自分が何を目的としているのかを
明確にした上で、その目的に最適な方法を選びましょう。
5−7)マーケティング「未来販路」→【理論と心理効果100個】
マーケティング戦略の理論と心理効果100個
高額商品・ファン化・リピート・LTVを劇的に高める行動経済学
<プレミアム効果(Premium Effect)>
価格が高いほど、顧客はそれを「特別」「希少」と認識しやすく、購入後の満足度や愛着が高まる現象。愛着が強いほどリピート率も上がりやすくなる。
<コスト・シンク効果(Sunk Cost Effect/埋没コスト効果)>
高額な支払いをした顧客は「元を取ろう」とする心理が働き、積極的に商品やサービスを利用する。結果、継続利用や追加購入の確率が上がる。
<自己一貫性の原理(Self-Consistency Principle)>
人は自分の選択を正当化し、一貫性を保とうとする。高額商品を購入した顧客は「これは価値がある」と自分に言い聞かせ、長期的にブランドを支持しやすくなる。
<ヴェブレン効果(Veblen Effect)>
高価格そのものがステータスの象徴となり、需要が増える現象。富裕層市場で強く働き、ブランドの格を高める。
<スノッブ効果(Snob Effect)>
他人が持たない希少で高価な物を選びたくなる心理。限定生産やシリアルナンバー入り商品で効果が高い。
<プレスティージ価格効果(Prestige Pricing)>
高価格設定によって品質や信頼性を連想させ、購入意欲を高める戦略。ワインや化粧品業界で顕著。
<価格=品質ヒューリスティック(Price–Quality Heuristic)>
「高い=品質が良い」という思い込み。特に専門知識のない市場で強く働き、高額化による購買率向上を促す。
<ロイヤルカスタマー化のフィルタリング効果>
高価格が自然に顧客を選別し、本当に価値を理解する層だけを集める。結果としてリピート率とLTVが上昇する。
<コンコルド効果(Concorde Fallacy)>
投資額が大きいほど途中でやめられなくなる心理。高額契約の継続率を押し上げる要因。
<所有効果(Endowment Effect)>
一度手に入れた物は、支払った金額以上の価値があると感じる傾向。高額商品ほど愛着が増し、手放しにくくなる。
<排他性の原理(Principle of Exclusivity)>
限られた人しか買えない高額商品は、その排他性がファンの帰属意識を高める。
<コミットメント効果(Commitment Effect)>
高額支払いによる強いコミットメントが、ブランドとの長期的関係を生む。
<ラグジュアリー効果(Luxury Effect)>
高価格が「贅沢さ」を象徴し、日常では得られない体験価値を与えることでファン化を促す。
<ハロー効果(Halo Effect)>
高価格ブランドの一部商品が好印象を持たれると、他の商品にもその良い印象が波及する現象。
<選択的露出効果(Selective Exposure)>
高額ブランドを選んだ人は、自分の選択を裏付ける情報だけを積極的に集め、ブランド愛を強化する。
<心理的オーナーシップ効果(Psychological Ownership)>
高額商品は「自分の分身」のように感じやすく、長期的な利用とリピートを促す。
<儀式化効果(Ritualization Effect)>
高額商品は特別な扱いを受けやすく、その購入・使用行為自体がブランド儀式となり愛着を強化する。
<バンドワゴン効果(Bandwagon Effect)>
高額商品でも「皆が買っている」という情報があれば追随者が増え、ブランド熱が高まる。
<象徴的自己完成理論(Symbolic Self-Completion Theory)>
人は自己イメージを完成させるために、高額で象徴的な商品を選び、継続的に消費する。
<心理的参入障壁効果(Psychological Entry Barrier)>
高額価格が参入障壁となり、既存顧客の特別感とブランドへの忠誠を高める。
<インカム効果(Income Effect)>
高額商品を購入できる経済力があると示すことで、購買者は自己肯定感を高め、ブランドへの忠誠を深める。
<コンティンジェンシー価値効果(Contingent Value Effect)>
高額支出を伴う商品は、その利用機会やシーンに強く結びつき、特別な体験記憶として残る。
<ブランド資産蓄積効果(Brand Equity Accumulation)>
高価格帯で販売を続けることで、ブランドそのものの資産価値が増し、顧客の長期的支持を得やすくなる。
<ゴール・グラディエント効果(Goal Gradient Effect)>
高額商品の購入が、顧客に「大きなゴールを達成した感覚」を与え、ブランドとの心理的距離を縮める。
<高額希少性プレミアム>
高価格と希少性が掛け合わさることで、入手困難性が増し、ファンの熱狂度とリピート率が高まる。
<エリート意識形成効果>
高額商品を所有することが、自分を「選ばれた側」と感じさせ、ブランドコミュニティへの結束力を高める。
<承認欲求満足効果>
高価格ブランドの利用は、周囲からの評価・羨望を得やすく、顧客の承認欲求を満たす。
<経験価値の増幅効果>
高額商品は購入・使用体験そのものが強く記憶に残り、ブランドへの愛着を強める。
<パトロナージ効果(Patronage Effect)>
高額顧客はブランドを「支援者」として認識し、長期的に購入を続ける傾向が強い。
<エフォート・ジャスティフィケーション効果(Effort Justification Effect)>
高額商品を得るための努力や時間が、その価値をさらに高く感じさせる。
<アイデンティティ強化効果>
高額商品は購買者の自己イメージやライフスタイルと結びつきやすく、ブランド依存度を高める。
<ステータス維持効果>
高額商品を所有し続けることで社会的地位を維持しようとする心理が働き、リピート購入を促す。
<ポジティブ記憶バイアス>
高額購入の体験は、時間が経つほど美化され、再購入の意欲を高める。
<ブランド儀礼効果>
高額商品の購入・受け取り・開封といったプロセスが儀式化し、感情的な満足を増幅する。
<排他的アクセス効果>
高価格顧客だけが得られる限定イベントやサービスが、ブランドロイヤルティを強化する。
<トークン効果(Token Effect)>
高額商品は所有そのものが「資格証明」のように機能し、所有者同士の絆を強める。
<サンクコスト・ロイヤルティ>
高い埋没コストが、顧客の離脱を防ぎ、長期利用を促す。
<記念品価値効果>
高額商品が人生の節目や特別な記念と結びつき、感情的価値が増幅される。
<マイルストーン達成効果>
高価格品の購入が、人生やキャリアの達成感を象徴し、そのブランドを再び選ぶ動機になる。
<審美的プレミアム効果>
高額ブランドはデザインや美的要素が強調されやすく、美的価値が購買理由になる。
<物語化効果(Narrative Effect)>
高額商品には背景ストーリーが付与されやすく、顧客はその物語と自分を重ね合わせる。
<限定生産効果>
供給量を絞ることで、高額商品の需要とロイヤルティが持続する。
<自己投資効果>
高額購入を「自己成長や自己投資」と解釈し、継続的な購入を正当化する。
<パーソナルブランド強化効果>
高額ブランドの利用が、顧客自身のブランドイメージ向上に直結する。
<社会的比較優位効果>
高額商品の所有が、周囲との比較で優位感を与え、維持のために再購入を促す。
<信頼性付与効果>
高価格設定が企業やブランドの信頼性を高め、顧客離脱を減らす。
<成功の象徴効果>
高額商品が「成功者の証」として機能し、自己満足とリピート購買を生む。
<希少機会効果>
入手機会が限られることで、次回の販売時に即購入する行動を誘発する。
<ロックイン効果(Lock-in Effect)>
高額購入によりブランドのシステムやサービスに依存するようになり、離れられなくなる。
<熟達者志向効果>
高価格帯は「本物志向」「上級者向け」という印象を与え、専門家層のファン化を促す。
<長期保証効果>
高額商品の保証期間やアフターケアが長いほど、顧客はブランドとの関係を続けやすくなる。
<サブカルチャー形成効果>
高価格帯ブランドの愛好者が独自の文化や価値観を形成し、強固なファン層を生む。
<反転価格効果>
値上げによって逆に需要が増える現象。ブランド価値を高める価格戦略として機能。
<リファレンス価格効果>
高額商品の存在が、他商品の価格を安く感じさせ、全体の売上を底上げする。
<メンバーシップ効果>
高価格顧客限定の会員制度が、特別感と継続利用を生む。
<長期使用愛着効果>
高額商品の長期利用が愛着を深め、買い替えや追加購入の動機になる。
<期待値上昇効果>
高額商品の使用経験が顧客の基準値を上げ、同ブランド内での再購入時にも高価格帯を選びやすくなる。
<プライド所有効果>
高額ブランドを持つ誇りが、再購入や紹介行動を促進する。
<代理ステータス効果>
高額商品の贈答が、贈り手の社会的地位を示し、ブランド価値を広げる。
<文化的資本効果>
高額ブランドの所有が「文化的素養」の象徴となり、同質層とのつながりを強化する。
<ラストチャンス効果>
高額商品の「最後の機会」訴求が購買決定を加速する。
<資産化効果>
高額商品が資産的価値を持ち、長期保有のインセンティブとなる。
<収集欲求刺激効果>
高価格帯コレクション品が、コンプリート欲求を生みリピートを促す。
<社会的同調圧力効果>
高額商品所有者が周囲に増えることで、新規顧客の参入意欲が高まる。
<ラグジュアリー・ネットワーク効果>
高価格帯ブランドのコミュニティ参加が人脈や社会的資本の拡大に直結する。
<恒常化効果>
高額ブランドの利用が生活習慣化し、他ブランドに切り替える心理的障壁が高まる。
<ポジショニング強化効果>
高価格が市場におけるブランドの位置づけを明確にし、コアファンを固定化する。
<セレクティブ・ロイヤルティ効果>
高額ブランドのみを選び続ける選択パターンが習慣化する。
<成功体験再現効果>
過去の高額購入が成功体験として記憶され、同ブランドを再選択する動機になる。
<顧客教育効果>
高額ブランドが顧客に正しい使い方や価値観を教育し、離脱率を下げる。
<ブランド・レガシー効果>
高価格帯商品の長期的歴史や伝統が、ファンの忠誠心を高める。
<信念強化効果>
高額ブランドを支持することが、顧客の価値観や信念を補強する。
<象徴的消費効果>
高価格商品がライフスタイルや価値観の象徴となり、継続利用を促す。
<ネットワーク固着効果>
ブランドを通じた人脈や友人関係が、顧客を離れにくくする。
<ラグジュアリー依存効果>
高額ブランド利用の快感が習慣化し、リピート消費を誘発する。
<アップセル連鎖効果>
高額商品の購入経験が、さらに高価格帯へのステップアップを促す。
<ブランド・セーフティ効果>
高価格ブランドの購入が「失敗しない選択」という安心感を与え、継続利用につながる。
<達成動機強化効果>
高額商品の所有が新たな目標達成意欲を刺激し、追加購入の動機になる。
<経験価値依存効果>
高価格体験が「もう一度味わいたい」という依存性を生み、再購入率を高める。
<稀少感持続効果>
高価格帯商品の希少感が長期間持続し、長期的ファンを育てる。
<関係性深化効果>
高額顧客に提供される特別対応や専任担当が、ブランドとの深い関係性を築く。
<自己報酬効果>
高額購入を自分へのご褒美として位置づけることで、定期的な購入を習慣化する。
<アップグレード志向効果>
高額商品を選んだ経験が、次も上位モデルや限定版を選ばせやすくする。
<ラグジュアリー・コンフォート効果>
高価格商品の快適さや満足度が、他の選択肢を選べなくする。
<認知的不協和低減効果>
高額購入後の後悔を避けるため、積極的にその商品やブランドを評価し続ける。
<ブランド・パートナーシップ効果>
高価格ブランド同士のコラボが、顧客の誇りと愛着を倍増させる。
<エモーショナル・アンカリング効果>
高額商品の購入経験が感情的基準点となり、再購入時の価格許容度を引き上げる。
<ブランド・ストーリーテリング効果>
高価格ブランドの物語が顧客の自己物語と結びつき、強いロイヤルティを生む。
<長期関係投資効果>
高額顧客はブランドとの関係を「資産」と見なし、維持のために継続的に購入する。
<高額安心感効果>
高い価格が品質保証のシグナルとなり、不安を減らしてリピートを促す。
<ブランド帰属意識効果>
高価格ブランドを選ぶことで、自分が特定コミュニティの一員であるという感覚が強まる。
<自己実現支援効果>
高額ブランドの利用が、顧客の自己実現の一部として機能し、長期的なファン化を促す。
<プレステージ持続効果>
高価格帯を維持し続けることで、ブランドの格と顧客の忠誠心が持続する。
<ブランド・インサイダー効果>
高額顧客にだけ共有される情報や裏話が、特別感と継続利用を生む。
<顧客ストーリー共有効果>
高額商品の利用体験を語ることで、顧客自身の満足とブランドの拡散が同時に進む。
6−1)ブランド戦略【未来ブランド戦略】
未来経営での「ブランド戦略」は
高く売れる事」に限定します。
知名度ではなく、
広告でもなく、
最初に、「選ばれること」
さらに、「信頼が積み重なった、選ばれ続けること」
同じような製品でもこの「ブランド」があると高く売れる事です。
結果的に本物を指すことが多いです.
知名度があるのとは違います。
たとえば「ユニクロ」と「マクドナルド」は、
有名で知名度はありますが、本物のブランドとは違うと思います。
多額の費用で宣伝や告知で「ブランド」を有名にしているのは、
ただ「知名度」があるに過ぎないのです。
本物のブランドは、その言葉の価値です。
⚫︎会社のブランド(企業名・起業ロゴ)
⚫︎製品のブランド(製品名・サービス名)
⚫︎個人のブランド(パーソナルブランド)
をつくりましょう!
★ブランドを明確にする。
★たくさん売れる事。
★高くても売れる事。
★在庫がなくても売れる事
6−2)ブランド戦略【未来ブランド戦略】→長期ブランド戦略
みんなは「ブランド」を作って、
直ぐに売れることを目指します。
しかし、そんな短期間でブランドを作るには、
莫大の費用が必要です。
広告費や宣伝費です。
ただし知名度は上がりますが、
ブランドにはなりにくいのです。
また、短期で作ったブランドは、直ぐに崩れます。
本来ブランドができると、何もしないでも
売れていきます。
マクドナルドのように、常に宣伝しないと売れない商品は、
本当のブランドどは言えません。
そこで、長期ブランド戦略が必要なのです。
⚫︎初期ブランド戦略
⚫︎中期ブランド戦略
⚫︎後期ブランド戦略
を、ステップごとに考えるのです。
宣伝費やSNS活用は、「後期ブランド戦略」です。
6−3)ブランド戦略【未来ブランド戦略】→初期ブランド戦略
初期のブランド戦略は、とにかく売れる事です。
高くても売れて、
在庫がなくても売れるのです。
「ブランドがあるから売れる」のではなく、
「売れるからブランドになる」のです。
私が思う。ブランド商品は「フェラーリ」です。
⚫︎みんなのイメージが同じ
⚫︎宣伝しなくても売れ
⚫︎高くても売れる
⚫︎在庫がなくても売れる
⚫︎中古も高く売れる。
もし、「フェラーリ」が知名度があり、
ブランドがあっても・・
⚫︎宣伝しないと売れない
⚫︎高いと売れない
⚫︎在庫がないと売れない
⚫︎中古が安くしか売れない
⚫︎誰も持ってない。
これだと、「ブランド」があっても意味はないでしょう!
また、これだと、「ブランド」があるとは、言えないでしょう!!
そこで、「初期のブランド戦略」は、
売れる事です。
みんなが欲しくて、
探してでも買いたくなる。
高くても売れる事です。
7−1)売上向上【未来売上】売上アップ
売上アップは、経営者の一番の悩みでしょう!!
更に、「人材獲得「と「売上アップ」の2輪は、
経営者の最大のテーマ」です。
どちらかが、うまくいけば、
どちらかが、足りなくなるのです。
どちらかを、常に気にするのが経営です。
更に、「売上アップ」→「人材獲得」→「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」「売上アップ」→「人材獲得」
と、永遠に続くのです。
そこで、「売上アップの方法」と「無限ループの脱出」の方法を、ここでは伝えていきたいです。
<売上アップ方法>
⚫︎クライアント向けセミナー毎月(情報種集・情報発信)
⚫︎同業者向けセミナー毎月(ブランドアップ・非ライバル化)
⚫︎業界マップ(独自位置)
⚫︎独自研究
⚫︎独自理論
⚫︎独自商品
⚫︎単品戦略で一点突破を狙う
⚫︎独自マーケット
⚫︎全体構造戦略(入り口から出口まで)
⚫︎超ニッチ(細部に集中して行う)
⚫︎新規獲得とリピート獲得(CVR(購入率)を最優先で改善する)
⚫︎松竹梅戦略
⚫︎高額戦略(超高品質戦略)
⚫︎サブスク戦略(毎月収入・年間契約)
根本的解決は、
顧客が、喜び、感動する商品は、自然に売れる。
→集客しなくても、営業しなくても、売れる商品を開発し、
その「売上アップ」戦略を考える。
一般的に企業は「今月の売上」を追っかけている。
未来経営では、「3ヶ月後」「半年後」の売上を追っかけます。
<売上意識>→<現金主義>
売上主義より、利益主義。
利益主義より、現金主義。
かっこよくいうと「キャッシュ」
これによって、キャッシュフローが良くなる。
<無限ループ脱出>
「人材獲得」「と「売上アップ」の2輪は、
経営者の最大のテーマ。
どっちが足りていると、どっちが足りない。
いつも、どっちかを追いかけている。
常に、それぞれの戦略とノウハウが必要です。
⚫︎売上アップ戦略
⚫︎人材勝つ約戦略
⚫︎人に任せる:「人材獲得」は人事責任者に・「売上アップ」は売上アップ責任者に
⚫︎チームに任せる:「人材獲得」は人事チーム・「売上アップ」は売上アップチームに
⚫︎人材と売上に余裕を持つ:未来経営で・・「未来人事」「未来売上」
ーーーーーーーーー
<売上アップと人材獲得、どちらが先か?>
経営者からよく聞かれる質問があります。
「売上を先に上げるべきか?、
それとも先に人材を獲得すべきか?」
私の答えは、まずは売上を上げることが先です。
売上がなければ、人材を雇う予算も出ません。
逆に売上が順調であれば、より優秀で高報酬な人材にもアプローチできるようになります。
だからこそ、経営の最初のステップとしては、売上を作ることに注力すべきなのです。
⸻
<売上を先に上げるための工夫>
とはいえ、「まだ社員が少ない」「リソースが足りない」といった状況では、売上を上げるのも難しいのが現実です。
その場合は、まず業務を外注化することをおすすめします。
バックオフィスや制作、管理業務などは一旦すべて外注に任せて、自社の社員は全員“営業”に集中させる。
そして、売上が上がればまた外注を活用しながら、その分の利益で人材を増やしていく。
このサイクルを繰り返すことで、効率的かつ無理のない会社の成長が実現できます。
⸻
「売上 → 人材 → 売上 → 人材」
この「はしご」をバランスよく、一段ずつ登っていくことが、会社成長の王道です。
7−2)売上向上【未来売上】売上アップの目的
売上を上げる本当の目的は、
会社の質を上げるためです。
稼いだお金で、
研究し
最高の商品の
いい商品を開発する。
いいサービスを
素早く丁寧に提供する。
社員には、いい環境で、
最高の手当と福利厚生を提供し、
給料を業界1にする。
最高の待遇にする。
<寿司屋>
私は、お寿司が大好きです。
⚫︎綺麗なタオルで
⚫︎最高のネタを
⚫︎最高の職人で
⚫︎ネタの話でもしつつ
⚫︎最高のサービス
で食べたいです。
逆に、
袋に入ったペーパータオルで、
美味しくないネタを
ロボット握りで
魚の事もわからない店員で
適当なサービスで
食べたくないです。
会社も同じです。
研究した商品の
最高の商品の
いい商品を
いいサービスで
チェックを受けた商品を
素早く提供したいです。
8−1)営業戦略「未来営業」(セールス)
一般的な企業は「売れないものを努力と根性で売る」
未来経営では、「売れる仕組みで自然に売れる」
現在の営業方法は?どんな受注構造ですか?
⚫︎営業しないと売れない。
⚫︎呼ばれて行っても受注率が低い
⚫︎営業期間が長い(6ヶ月)・営業回数が多い(6回以上)
⚫︎成功事例未掲載
⚫︎手形入金
<未来受注構造>未来営業
自ら営業しないでも売れる
未来の受注構造を作りましょう!
⚫︎自ら営業しない
⚫︎呼ばれて行ったら受注率100%
⚫︎短期間営業(2週)・短期間営業(2回)
⚫︎成功事例掲載約束
⚫︎前金入金
そんな夢の理想の「受注構造」を考えてみましょう!!
しかし、営業の「売りやすさ」と「テクニック」は必要です。
<売りやすさ>
それには、「未来商品」と「USP」です。
「営業は足で稼ぐ」は古い。
今は
「営業は頭で稼ぐ」
<営業のテクニック>
企画書作成やプレゼンの能力です。
練習しましょう!!
そもそも、友人に、その企画書と
プレゼンで、Iがが欲しがらなければ、
誰も欲しがりません。
外に出る暇があったら、机に座り、最高の企画・企画書を作る。
→100%受注できる企画・企画書を作る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★<セールス戦略・営業戦略>
セールスや営業に頼らなくても、
自然に売れていく、戦略をいつも考えていた。
そのために「売れる商品開発」・「売れるUSP」・
「成功事例」(お客様の声)の獲得に全力を注いでいた。
商品そのものが価値を語り、
お客様の声が次の顧客を呼び込む──
そんな自走型のセールス構造をつくることが、
最大のセールス戦略でした。
9−1)求人戦略 求人採用「未来採用」求人募集ステップ
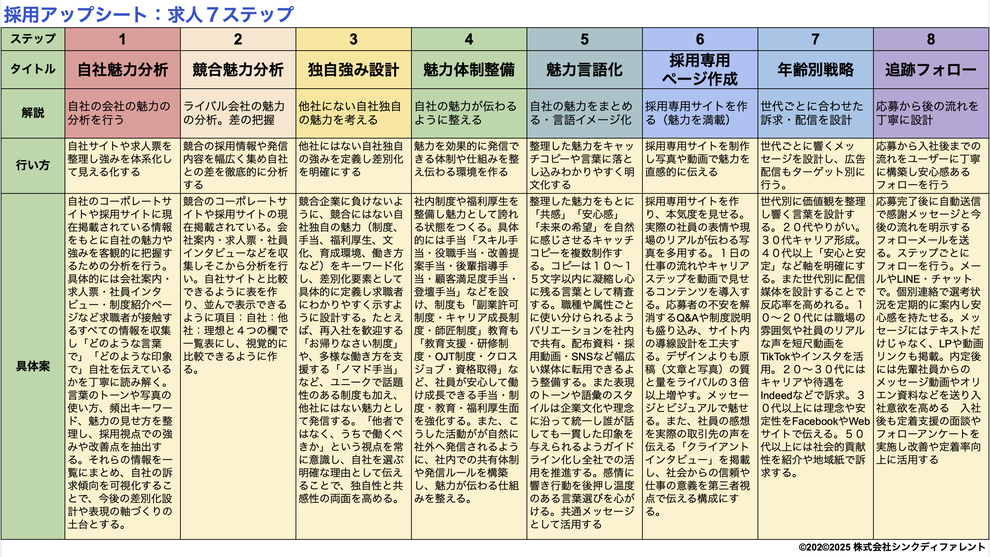
<求人募集>
採用は単なる人員補充ではなく、会社の未来を形づくる重要な戦略です。
人材は企業の成長を左右する最大の資源であり、どのような人が集まり、
どのように働くかで未来が決まります。そのため、自社の魅力をしっかり分析し、
ライバルとの差別化を行い、なぜ自社で働くべきかという明確な理由=USPを提示することが重要です。
求人募集を単なる作業ではなく「未来経営の一環」として設計することで、
優秀な人材が自然に集まり、組織の成長が加速していきます。
人材獲得数は10倍以上になる可能性があるのです。
<求人募集ステップ>「人材獲得数は10倍以上になる可能性」
(1)自社の魅力を分析
(2)ライバル会社の魅力を分析
(3)自社のUSP(なぜ他社ではなく自社で働くべきか)を考える
(4)会社を魅力的に整える
(5)魅力をまとめて言語化・イメージ化
(6)求人専用サイト「採用ページを独立作成(魅力いっぱいに)」
(7)年齢別ターゲット戦略
(8)フォローフロー作成
(1)自社の魅力を分析
自社の「成長できる環境」「仲間から学べる文化」「給料・福利厚生」「働きやすさ」
などの魅力を洗い出します。
会社の良さを自覚することで、求人でアピールすべきポイントが明確になります。
(2)ライバル会社の魅力を分析
競合他社の採用ページや制度を調査し、何が応募者を惹きつけているのかを把握します。
他社の強みを学ぶことで差別化ポイントを見つけ、自社にしかない魅力を際立たせることができます。
(3)自社のUSP(なぜ他社ではなく自社で働くべきか)を考える
「なぜこの会社を選ぶべきか」という独自の理由=USPを明確にします。
仕事内容、社風、成長機会、報酬などを通じて他社にはない価値を示し、
応募者が「ここで働きたい」と思える根拠をつくります。
(4)会社を魅力的に整える
制度や福利厚生を改善し、オフィス環境を整えるなど、実際に働く場を魅力的にします。
求人広告で伝えるだけでなく、実際に社員が働きやすい環境を整えることが、応募者の信頼につながります。
(5)魅力をまとめて言語化・イメージ化
分析した自社の魅力やUSPを「言葉」と「ビジュアル」にまとめます。
キャッチコピーやイラスト、写真を活用して、
応募者が直感的に「働いてみたい」と思える形に表現することが重要です。
(6)求人専用サイト「採用ページを独立作成(魅力いっぱいに)」
本気度を示すために、独立した採用サイトを作成します。
会社の目標・ビジョン、オフィス写真、社員インタビュー、女子社員の声、
手当・福利厚生などを掲載し、応募者が安心して応募できる場をつくります。
(7)年齢別ターゲット戦略
Z世代には動画広告、
20〜30代には専門広告、
30代以上にはネット広告、
50代以上には紹介・人脈と、
年齢層に合わせた媒体と訴求を行います。
世代ごとの価値観に応じたアプローチで応募率を高めます。
(8)フォローフロー作成
応募後から採用までの流れをスピード感を持って設計します。
応募受付→返信→面接案内→結果連絡の一連の流れを整備することで、
応募者が安心し、会社の印象も高まり、辞退を防ぐことができます。
これにより応募者が安心し、会社の印象も高まり、辞退を防ぐことができます。
採用活動は「応募を集める」だけでなく「信頼を積み重ねるプロセス」でもあります。
応募者との最初の接点から面接、結果連絡に至るまで、
誠実でスピード感ある対応を徹底することで、会社のブランド力も自然に上がります。
結果的に「この会社で働きたい」という確信が生まれ、
入社後の定着率やモチベーション向上にもつながります。
そして最終的に、優秀な人材を獲得しやすくなり、
人材獲得数は10倍以上になる可能性があるのです。
9−2)求人戦略 求人採用「未来採用」
求人票を作る前に、
最初に、自社や自分の会社の魅力を最大化します。
⚫︎会社の魅力
⚫︎求人票の魅力
⚫︎多彩な手当
です。
まずは、理想の架空の「求人票」を作ります。
たくさんの応募があり、獲得率も高い、
求人票が出来上がります。
それを実現するために必要なことを書き出します。
それを、以下を行い実現を目指します。
⚫︎分散化 ⚫︎細分化 ⚫︎プロジェクト化 ⚫︎AI化します。
その架空の「求人票」を実現します。
理想になった求人票には、人材獲得ができると思います。
ーーーーーー
一般的な企業は「凡庸な企業が、優秀な人材を取ろうとする」
未来経営では、「企業の魅力を高め、自分より優秀な人だけを獲得する」
経営は、売上が足りていると人材が足りない。
人材が足りていると売上が足りない。
とにかく、成長する企業は、常にどっちかが足りない。
そこで人材獲得を急遽行わなければならなくなる。
一般的な企業は「求人を「補充」と考えている」。
未来経営では「求人は「進化」と「成長」と捉えている」
まず選ばれる会社になろう!
自社を魅力的にする。
誰でもが入社したい会社になる。
そして、自分より優秀な人だけを獲得する。
<優秀な人を雇う方法>
⚫︎まず社長自身が秘書を雇い自分自身の魅力を増やす。
⚫︎現在の社員の給料が増えるように効率化を行う。
⚫︎先に地域NO1の給料が払えるようにする。
⚫︎彼が入社しても、より優秀になる仕組みが社内にあるようにする。
⚫︎魅力的な仕事、魅力的なクライアントがいるようにする。
<求人方法>
人材の求人方法・採用方法・人材獲得方法の具体的方法
→会社を魅力的にする
1)自社の会社の魅力の分析を行う。
2)ライバル会社の魅力の分析を行う。
3)自社の魅力のUSPを考える。「なぜ、他者ではなく、うちで働くべきか」
4)自社の魅力的に整える
5)自社の魅力をまとめる・言語化・イメージにまとめる。
6)採用ページを作る(魅力いっぱいの)
7)会社の想いや哲学を発信する
8)これで、人材の集客・人材応募・人材獲得の
すべての成功率を高めていきます。
<自社を魅力的にする>
1)成長できる(スキル・知識・知恵・経験)
2)先輩・師匠・仲間ができる(習える・目指せる)
3)オフィスが素敵や面白く見える。
4)給料が高く安定収入(生活しやすい)
5)福利厚生がしっかりある。(保健・休暇)
6)手当が多い。手当が面白い。制度が面白い
7)教育制度がしっかりしている
8)自由(服装・髪型・爪・趣味)
9)挑戦できる(新しい仕事・新しいプロジェクト)
10)社会に貢献できる(誰かのためになる)
<求人・採用・人材募集>
まず最初に、会社の魅力をアップする。
「戦略的人材獲得」を行います。
現在の自社の「求人票」を見て、
ライバルと比較して、
それを超える、理想の架空の「求人票」
を、作ります。
それを実現するために
必要なことを書き出します。
それを、以下を行い実現を目指します。
⚫︎分散化 ⚫︎細分化 ⚫︎プロジェクト化 ⚫︎AI化します。
その架空の「求人票」を実現します。
理想になった自社には、人材獲得ができると思います。
<社員教育:戦略的人材獲得>
人材を教育しよう!管理しようと思わない。
「入社すれば誰でも自然に成長できる仕掛けがあり
全員が成果を出せる仕掛け」
よって社員の給料が高い。
そんな【仕組み・仕掛け・システム】を会社に作るべきだ。
才能や努力頼らず、
⚫︎仕掛け
⚫︎仕組み
⚫︎IT&クラウド
⚫︎システム
で人を自然に自動に成長させ、強い組織をつくる。
<会社の変革と成長>
★優秀な人を採用しないと決めた。
★会社の仕組みや仕掛けで、誰でもが突然優秀になる仕組みを作った。
9−3)未来経営 求人採用「募集方法」「手当」
<優秀人材の努力を引き出す20の手当>
(1)成果給手当
⚫︎売上や利益、目標達成に応じて追加報酬を支給。
⚫︎例:目標達成率に応じて、月給の5〜20%を上乗せ。
(2)資格取得手当
⚫︎会社が必要とする資格取得に対して受験料や講座費用を支援。
⚫︎例:合格時に報奨金3万円を支給。
(3)スキル研修手当
⚫︎外部セミナーや研修参加に会社が補助。
⚫︎例:研修費用の半額〜全額を会社負担。
(4)自己投資手当
⚫︎書籍購入やeラーニング受講費を補助。
⚫︎例:月5000円まで会社負担。
(5)プロジェクト達成手当
⚫︎特別案件や新規事業が成功した時に全員へ支給。
⚫︎例:達成時にチーム全体で10万円を分配。
(6)残業ゼロ手当
⚫︎効率的に仕事を終わらせた人に支給。
⚫︎例:残業ゼロ達成月に1万円支給。
(7)健康維持手当
⚫︎健康診断や運動習慣を続けた社員に支給。
⚫︎例:ジム利用やフィットネス費を月5000円まで補助。
(8)皆勤手当
⚫︎無遅刻・無欠勤の社員に支給。
⚫︎例:月1万円支給。
(9)改善提案手当
⚫︎業務改善や売上UPに貢献する提案をした人へ。
⚫︎例:採用された提案1件につき5000円。
(10)リーダーシップ手当
⚫︎部下育成やチーム牽引力を発揮した人へ。
⚫︎例:月ごとにリーダー選出、1万円支給。
(11)後輩指導手当
⚫︎新入社員教育に尽力した人へ支給。
⚫︎例:研修終了後に指導担当者へ3万円支給。
(12)社内講師手当
⚫︎自分の得意分野を活かして社内研修を行った社員へ。
⚫︎例:1回の講義につき5000円。
(13)表彰手当
⚫︎月間・年間MVPを選び報奨金を支給。
⚫︎例:月間MVPは1万円、年間MVPは10万円。
(14)イノベーション手当
⚫︎新商品・新サービスを生み出した人へ。
⚫︎例:採用されたアイデア1件につき3万円。
(15)顧客満足度手当
⚫︎顧客アンケートやレビューが高評価だった社員へ。
⚫︎例:平均4.8点以上で月1万円支給。
(16)コミュニケーション手当
⚫︎社内の雰囲気改善やイベント企画に貢献した人へ。
⚫︎例:イベント主催者に1万円支給。
(17)チーム貢献手当
⚫︎個人成果ではなく、チーム全体の成功に貢献した人へ。
⚫︎例:リーダーだけでなくメンバー全員に均等支給。
(18)紹介採用手当
⚫︎社員の紹介で採用に至った場合、紹介者に支給。
⚫︎例:入社3カ月継続で5万円支給。
(19)ライフサポート手当
⚫︎育児・介護と両立する社員へ支給。
⚫︎例:在宅勤務導入+月1万円支援。
(20)特別感謝手当
⚫︎社長や上司が特別に感謝を伝えたい時に支給。
⚫︎例:プロジェクト成功時に臨時で5000円〜支給。
9−4)未来経営 求人採用「募集方法」「年齢別ターゲット戦略」
<人材募集は年齢別ターゲット戦略で>
人材を効果的に募集するには、「ターゲット別」に戦略を立てることが重要です。
なぜなら、告知・広告・募集方法は「誰に届けるか」で大きく異なるからです。
特に年齢層によって「情報を受け取る媒体」が全く違います。
若い世代は、ネット検索よりも動画などの「流れてくる情報」に触れる傾向が強く、
会社の雰囲気や日常、リアルなイメージを重視します。
反対に、社会経験を積んだ世代は検索や比較をしっかり行い、
条件や実績を見て判断します。
そのため、年齢ごとに最適な媒体を選び分けることが、
採用活動の成功率を大きく高めます。
以下に、年齢別に「見る媒体」と「反応のポイント」を整理しました。
⚫︎10代後半〜20代前半(Z世代・新卒層)
→媒体:「動画広告(インスタ・TikTok)」
→特徴:「検索しない世代」/動画の流れの中で自然に接触する
→重視点:会社の雰囲気・職場の日常・社員のリアルな声
→補足:短尺動画で直感的に伝える/ストーリー性ある採用動画が効果的
⚫︎20代〜30代(転職・キャリアアップ層)
→媒体:「専門広告(Indeed、リクナビ、マイナビ)」
→特徴:「検索する世代」/条件検索・比較を徹底する
→重視点:給与・待遇・キャリアパス・職務内容
→補足:企業の信頼性を数値や実績で示すと強い/「応募のしやすさ」も重要
⚫︎30代〜40代以上(経験者・管理職層)
→媒体:「ネット広告(WEBサイト・Facebook)」
→特徴:「情報の信頼性を重視する世代」/Facebook利用者が多い
→重視点:企業の安定性・実績・社会的意義/マネジメントや専門性の活かしどころ
→補足:企業ホームページで「代表メッセージ」「理念」などを確認する傾向が強い
⚫︎50代以上(シニア・ベテラン層)
→媒体:「紹介・人脈・地域紙・チラシ」
→特徴:「検索よりも直接の声掛け・つながり」で動く層
→重視点:安定性・役割・社会的貢献性/ライフスタイルとの両立
→補足:再雇用・顧問ポジション・地域活動との連動での訴求が効果的
<まとめ>
年齢ごとに「媒体」と「重視点」を変化させることで、採用は格段に効率化されます。
・Z世代には「動画広告」で共感とリアル感を
・20〜30代には「専門広告」で条件とキャリアを
・30代以上には「ネット広告」で信頼性と安定感を
・50代以上には「紹介・人脈」で安心と社会的意義を
結論として、人材募集は「年齢層×媒体×訴求ポイント」の
組み合わせで設計することが、最も成果を出す方法です。
9−5)未来経営 求人採用「優秀な人材確保」
優秀な人材が会社を成長させます。
最初に行うのが、自分自身を
優秀にすることです。
それには「秘書」です。
自分の思考・能力・知恵・意識・常識の
全てが3倍以上になります。
秘書にAIを駆使させます。
東大合格の知識と知恵を授けるのです。
★チャットGPTは、 「2025年」東大合格しました。
⚫︎一緒にいる時:自分自身の能力が2倍になります。
⚫︎一緒にいない時:自分の代わりに働いてくれています。量が2倍になります。
自分の長所を超越させ、短所を補完して、
まずは、自分自身を優秀な人材に加速させます。
私は秘書が2人いました。
⚫︎トゥデイ秘書:毎日外出、とにかく毎日一緒で、会議も一緒。私のメールも全て読む。私の全てを私以上に知る人です。
⚫︎トゥモロー秘書:明日以降のスケジュールを全て行ってくれる。私へのコンタクトの全てが彼女が受ける。
9−6)未来経営 求人採用「専用サイト」
人材確保には、求人専用サイトです。
単体で作ることで、本気度が伝わり、
情報の質も量も増えるのです。
そして、専用サイトだかからこそ、
なんでもかけるのです。
もちろん、年収も書きましょう!!
プロデューサー:450万円〜650万円」など
⚫︎トップページ
⚫︎企業写真集
⚫︎クライアントの声
⚫︎スタッフの声
⚫︎採用情報
ーーーーーーー
<詳細>
⚫︎トップページ→会社の目標・目的
⚫︎企業写真集→魅力的な会議室・魅力的なカフェ・魅力的なソファーコーナー・魅力的なライブラリ・魅力的なデスク
⚫︎クライアントの声→顧客の声が一番大事です。
⚫︎スタッフの声→女子の声と写真を多めに
⚫︎採用情報→面白い制度・面白い福利制度・戻ってきやすい制度
<選ばれる会社に>
- 社名の信頼性とイメージ・ブランディング
- 仕事を効率化でき「給料が高い」
- サイトの情報や写真の質と量の高さ
- 給料・福利厚生・手当の充実
- 柔軟な働き方(IT・クラウド・AIの活用)
- 社内制度の革新性
企業が選ばれる側になる意識への転換が鍵です。
10−1)未来経営「未来人事」【人事戦略】
<人事戦略>
人事戦略とは、単に人を雇うことに留まりません。
人材の「採用」から始まり、「確保」「教育」「成長」「リーダー化」「定着」まで、
組織全体の発展に直結する一連の戦略的活動を指します。
企業の未来を形作るのは人であり、その土台となるのが人事戦略なのです。
<人材が会社を決める>
会社とは、なんでしょう!
私は人材が会社だと思います。
人材が会社のレベルを決め
人材が会社の仕事量を決め
人材が会社の売上を決めます。
人材を雇うとき、
必ず、自分より「優秀な人」を雇いましょう。
そうすれば、自ずと会社は、成長します。
逆に、アシスタント的な
人を雇えば、会社は下落していく
もちろん社員とは、
全員、外注でも構いません。
ーーーーーーーーーー
<会社の変革と成長>
1)個人事業主期(目安:社長 1人)
社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。
→とにかく、自分より優秀な人を雇うことに全力を注いだ。
→この「採用方針」こそが、会社成長の最初のエンジンとなった。
→優秀な人の力で、自分を超える会社へ一歩踏み出す。
2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)
社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。
→会社の魅力が育ってくると、自然と人が集まるようになった。
→しかし、ここで矛盾が生じる。
→ 会社より優秀な人は、なかなか雇えない。
→さらに、優秀な人が入っても、ノウハウを蓄えて独立・転職してしまうという課題が浮上。
3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)
組織が「ピラミッド構造」化チームができる。
役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。
→優秀な人を「分散化」し、個人依存を回避する設計へ。
→仕事を1人では完結させない設計に切り替える。
→ノウハウや工夫はブラックボックス化し、仕組みに内蔵。
→凡人でも即戦力になれるよう、仕組み×仕掛けの「システム」内蔵型組織へ進化。
4)企業化期(目安:社員数 約100人)
仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。
→研究部・企画部などを設け、内部で「進化」を仕組みに。会社の人材の優秀化を行った。
→ 会社が「人を進化させる装置」へと変貌する。
→優秀な人材は“組織の中で分散・分化”させて専門化・研究化。
→更に優秀すぎる人には、あえて「独立心」「転職心」を先に与える戦略へ。
→「この会社から巣立つのが前提」という前提設計。
10ー2)未来経営「未来人事」(人材が5人以下の企業へ)
社員は需要。ただし、採取が大変。
「社長自身」と「社員」のバランスは非常に重要です。
⚫︎社長1人 → 社員1人:
ただでさえ忙しいのに、
「自分1人でやった方がマシ」
社員のフォローでさらに負担が増える。
売上も増えない。しかもすぐに辞める・・・
⚫︎社長1人 → 社員2人:
「教えること」で手一杯になり、自分の生産性は50%に。
社員2人の力を合わせても、「1人分の80%」にも満たない。
人材を雇わなきゃ良かった」と思うころ
⚫︎社長1人 → 社員3人:
やっと「実質1人を雇えた」のと同じ効果。
ここで初めて報われた実感が出る。
⚫︎社長1人 → 社員4人:
「実質2人分」の力が加わり、ようやく売上が安定して伸び始める。
⚫︎社長1人 → 社員5人:
「実質3人分」の戦力となり、
ここから一気に会社が加速していく段階に入る。
10−3)未来経営「未来人事」(人材が5人以上の企業へ)
私の場合の
<会社の変革と成長>
会社の成長は、以下の4つの段階に分かれました。
1)個人事業主期(目安:社長 1人)
社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。
2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)
社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。
3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)
組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。
4)企業化期(目安:社員数 約100人)
仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。
5)卒業期(目安:社員数 約120人)
社長がいなくても会社が回る」から「社長がいない方が会社が回利加速する」
と、言われてしまう時期。人材育成・組織が上手くいった証拠!
それぞれの時期によって、必要なノウハウや工夫はまったく異なります。
10−4)人事退社「未来人材」→「人材退社」
人材退社はラッキーだと思いましょう!
今、人材を辞めさせるのは難しい。
それを向こうから辞めてくれるから最高だ」と思おう。
これで、また、さらに優秀な人材が雇える。
夢にまでみた、理想の組織に、近づく。
また、本当に、いい会社(魅力的な会社)になっていれば、
かならず、他の会社のノウハウを持って、帰ってくる。
★福利厚生「お帰りなさい制度」を作っておく
夢みて、他社に行った社員が、もどってきてくれます。
これこそが、本当の自社の強さです。
11−1)組織戦略「未来組織」
現状の集まったメンバーで「組織を作る」より、
未来経営では、「最強の組織をつくる」
「最強のチーム」を作ります。
現在の理想と思う未来の組織図を架空で書いてみる。
「最強のチームをつくる」
現在の人材、組織を改善して、組織を作るのではない。
理想の未来の組織をイメージして「未来組織」を作る。
そして、それに近づけていく
例えば、
100人ぐらいの組織になった時
研究部や企画部・マーケティング部が欲しい。
そんな夢のアメーバー組織を思考してみる。
架空の組織図を書いてみる。
まだ雇ってない社員の
架空の給料マップも書いてみる。
現在の組織と未来の組織を
見比べ、足りないところを
埋めていきながら、
理想の組織に近づいていこう
<組織とピラミッド>
文鎮型からピラミッドにしていく、
しかし、最初、プレイヤーが多く、
せっかく部署を作っても、部長になる人がいない。
しかし「チーム」を作って、
「チームリーダー」になら
人はなってくれるから不思議だ。
「未来組織マップ」「未来給料マップ」を作る
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<組織構築事例>
ーーーー
1)元々、私1人で働いていました。
→プレゼンも営業も受注も業務も経理も一人で行っていました。
★以前会社を倒産させて、社員を辞めてもらった覚えがあるので、
誰も雇いたくなかったのです。
ーーーー
2)3人+外注(アウトソーシング)
私は人一倍、苦手なことが多い。
そこで、一番苦手なこと(経理)を
外注(アウトソーシング)にしました。
ある人がどうしても社員になりたい。
というので、社員にしました。
→社員になりたい人が集まったのは、
→私の会社紹介の企画書のおかげです。
この頃は、社員には業務を手伝ってもらいました。
→プレゼンも営業も受注も一人で行っていました。
★会社の知名度もない。売上もない。ブランドもない。
自社の魅力は、「未来イメージ」と思ってました。
ーーー
3)10人+外注(アウトソーシング)
会社経営がすごく楽しかったです。
昔、私が社員だった時、私は会社が苦手だったのに感動です。
僕にはできない「システム開発」を新しい社員が
来てくれて、
差別化ができ急速に成長しました。
→プレゼンも営業も受注も一人で行っていました。
→組織はまだ無く、組織はまだ文鎮型です。
★この頃、雇って良かったのが、秘書です。
自分の知識や知恵、能力、工数が爆上がりしました。
ーーー
4)30人+外注(アウトソーシング)
営業も入り、だんだん、会社ぽくなってきました。
プレゼンも営業も受注も人に任せようと
思いましたが。
何度も失敗しました。
私の売っている商品を私と同じ売り方では、
難しいと、気づきました。
→商品を思いっきり可変しました。
→売り方も思いっきり可変しました。
→組織というより、チームに分かれていきました。
★社長が売っている商品・社長の売り方では、
誰も売れない。と気づき。
社員ように商品開発・売り方・売り方の仕組みづくり・
を、行って、成功しました。
複数で、営業するので、一気に、
売上が上がるようになりました。
★チームに分けて、チームリーダーが、
各チームを見てました。
ーーー
5)70人外注(アウトソーシング)
これまでは、社員の給料をなるべく
安く抑えようと考えていました。
しかし、それは間違っていたと気づきました。
現在の社員には、その担当業務における
「理想の社員」と同じだけの給料を支払うべき
だと考えるようになりました。
そこで「未来給料マップ」を作成し、
同じ業務には同じ給料を支払うようにしました。
たとえ退職しても、その業務をすぐに保管できる体制を整えています。
だからこそ、地域で最も給料の高い会社を目指すことにしました。
だからこそ、商品も高額にしました。
11−2)組織戦略「研究部」「企画部」
研究部・企画部の需要性
会社のUSPを
企画し、
開発し、
実行に移す。
結果、会社の売上・利益を生み
人材獲得、人材育成も生む。
研究部・企画部の設立による未来への投資】
企業がある程度の規模に成長した段階では、
利益の一部(目安としては売上の20%程度)を
「研究費」として投資することが重要になってきます。
そして、その研究費を効果的に使うためには、
明確に「研究部」や「企画部」といった組織的な部門を設けるべきです。
これらの部署は、直接的に商品開発やサービス向上に関わるため、
将来的に会社にとって最も重要な“利益を生み出す源泉”になります。
なぜなら、ノウハウは会社の持続的な競争力の根幹を成すからです。
実際、日本国内には“研究型企業”はまだまだ少なく、
この分野に本気で取り組めば、突出して利益を伸ばすことが可能になります。
11−3)組織戦略「右腕」片腕・後継・承継の行い方
片腕の作り方は、
普通は「誰か1人を見つけて育てる」方法が一般的です。
しかし、どれだけ育てたとしても、
創業者には勝てません。
なぜなら、「0→1」をつくった起業の想い・思想、
そのときのノウハウや努力、工夫には、
誰も勝てないからです。
さらに、現在は
⚫︎テクノロジーが進化し
⚫︎ライバルも淘汰され
⚫︎少子高齢化が進行し
⚫︎高度成長期でもない
という非常に厳しい環境下です。
このような状況では、
どんなに優秀でも、前社長の「80%」程度の
パフォーマンスしか出せないのが現実です。
だからこそ、
後継・承継を成功させるためには、
「前社長の1.2倍以上の能力を持つ人材」が必要になります。
それを実現するには、
⚫︎「超天才」を見つけるか
⚫︎「分散・長期型」で構成するか
の2択しかありません。
多くの人が最初は、
「自分の分身を1人見つけよう」とし、
その人を一生懸命「育てたり」「コンサル」したりしますが、
長期的・根本的には育ちません。
結果、前社長が戻ってくる…という事態も起こります。
そこで、私がおすすめするのが、
「分散・長期型」の片腕づくりです。
【分散型】
自分自身を機能別に分解し、
それぞれに特化した人材を3人以上配分します。
例えば私の場合、
「営業・研究」「経理・財務」「人事・求人」
に分け、それぞれに
自分の1/3の領域を担当し、
自分より1.2倍の能力を持つ人材を見つけます。
⚫︎1/3 × 1.2 × 3人 = 自分の1.2倍
⚫︎または、0.4 × 3人 = 自分の1.2倍
これで、自分を超える「片腕」「右腕」「後継」「継承」が完成します。
⚫︎特化型:全体ではなく、1/3だけでいいから、特化した能力成長でOK。
⚫︎分散型:仮に誰かが辞めても補充しやすく、他の人への負担も少ない。
【長期型】
短期間で一気にすべてを覚えさせる必要はありません。
むしろ、時間をかけて、
教育・経験・体験を積ませる方が確実です。
これが、「分散・長期型」による片腕づくりの本質です。
12−1)管理戦略「未来管理」マネージメント
管理するのは、「顧客」+「社員」+「会社」
一般的な企業は「命令と指示で、現状維持」
未来経営では、「未来を見せて、未来の仕組みで働く会社」
<顧客管理>
顧客管理をしっかり行い、
⚫︎数字的管理:利益・入金・工数
⚫︎心情的管理:感想・関係・気持ち・合う
⚫︎サポート管理:会う・電話・メール
→知らないうちに顧客離れしないように
<社員管理>
管理というより、夢と褒美制度。
成果=給料+待遇+環境
どんな事をすると、
給料や待遇が良くなるのかを、
明確にする
社員の不満と社員の満足を理解しておく、
一人ずつ、全く、違う。
それを理解しておく。
★給料マップ」を作る?
<幹部管理>
幹部は育つと辞めていく!
ライバル会社に移ったり、
下請けやクライアントに移る場合がある。
→組織・チームが壊れる
→辞める前に、独立させる。(分社化)
<会社管理>
⚫︎オフィス環境
⚫︎業務環境
⚫︎組織環境
★任せるとは、勝手になんでも自由にさせることじゃない。
★任せるとは、見守りながら引き上げること!
成長したから、任せるのではない。
任せた瞬間から、成長を始める。
任せるとは「放置」「手を離す」ことではない。
「指導」と「監視」と「褒める」
12−2)管理戦略「未来管理」人に仕事を任せる際の3つの原則
<マネジメントとは>
マネジメントとは、組織やチーム、プロジェクトを効果的に運営し、成果を最大化するための一連の活動を指します。日本語では「管理」や「統括」と訳されることが多く、英語圏では「ビジネスマネジメント」や「プロジェクトマネジメント」などの用語で用いられます。
本来のマネジメントとは、単に人を管理することではありません。目標を設定し、それに向かってチームを導き、必要な資源を適切に分配し、成果が出るようにサポートする、極めて戦略的かつ創造的な行為です。現代のビジネス環境では、管理者というよりも「成長支援者」や「環境整備者」としての役割が重要視されつつあります。
⸻
<人に仕事を任せる際の3つの原則>
人に業務を任せる場面は、マネジメントの核心とも言える重要な局面です。その際に意識すべきは、以下の3つの原則です。
①「自分がハブにならない」
②「仕事はすべて一括で渡す」
③「最初から最後まで完結させる」
ーーーーーーー
①「自分がハブにならない」
仕事を誰かに依頼する際、よく見られる誤ったパターンが、「自分が中継地点になってしまう」ことです。たとえば、指示や情報を一旦自分が受け取り、そこから担当者に渡し、また確認を戻して…という流れです。これは一見丁寧に見えますが、実際には非効率で、結果として時間も労力も余計にかかります。仕事を任せたなら、当事者同士を直接つなげ、自分は必要以上に介在しない。これが、本当の意味での「任せる」姿勢です。
②「仕事はすべて一括で渡す」
仕事を分割して少しずつ渡すのではなく、全体像を見せた上で、まとめて一括で任せることが理想的です。部分的な情報だけでは、全体の文脈をつかむことができず、成果にも限界が出てしまいます。最初から仕事の始まりから終わりまでを任せることで、その人の判断力・創造力が最大限に発揮され、本来の力を出せるようになります。
③「最初から最後まで完結させる」
仕事は途中で交代させたり、途中から割り振ったりせず、できる限りその人に一貫して任せることが重要です。最初から関わることで、プロセス全体を理解し、関係者とのコミュニケーションも円滑になります。何より、責任感が生まれ、仕事の質とスピードが向上します。「信じて任せる」ことが、その人の成長にもつながります。
⸻
<視覚化による管理の重要性>
マネジメントにおいて、すべての情報や業務の状況を“見える化”することは極めて重要です。業務内容や進捗、問題点などが一目でわかるように、リストや表、フローチャート、マップ、グラフなどを活用して情報を整理しましょう。
「見える化」によって、分析が可能となり、現状の課題や改善すべきポイントが明確になります。結果として、問題の早期発見と迅速な対策が実現でき、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。
⸻
<時間工数の管理:時間は最大の経営資源>
どの業務にどれだけの時間がかかっているのか、どのクライアントに対してどのくらいの工数が費やされているのか。さらには、各スタッフの労働時間、自身の時給換算まで把握することが、マネジメントには不可欠です。
時間と工数を「見える化」することで、何にリソースを使い過ぎているのか、どの業務が収益を生んでいないのかなどが明確になります。これらの分析が、業務の最適化や人員配置の見直し、コスト削減、そして最終的には利益の最大化へとつながるのです。
⸻
<比較分析で気づきを得る>
情報をリスト化・表化したら、それを活用し「比較」を行いましょう。比較することで初めて、良い点・悪い点が浮き彫りになり、改善の糸口が見えてきます。
例えば、自社と競合企業のサービス内容や価格帯の違い、スタッフごとの業務生産性、クライアントごとの利益率など、多角的に比較することで、思いがけない気づきが得られることもあります。今やインターネット上には多くのデータや情報がありますので、積極的に外部情報も取り入れて、分析を深めましょう。
div
13−1)業務効率化・業務改善「未来業務」
業務効率を上げると、
2人で3人分の仕事ができるようになり、
売上も上がるし、
原価(材料)にも高い金額がだせ、
さらに、社員に高い給料が出せる。
もちろん自分の年収にも
最高の仕組み
そして、研究や実験・企画・検証
にもお金がかけれる。
面倒な業務を改善し、「利益」と「時間」の余裕を生み出す。
結果、それが「思考」を生み出し、
成長する!!
一般的な企業は「高額パソコン・ビックWモニター」は、経費の無駄。
未来経営では、「高額パソコン・ビックWモニター」は、業務効率の最初。
業務効率を上げると、
⚫︎仕事が短くなり、
⚫︎仕事が早く、
⚫︎ミスが減り、
⚫︎誰でもできるようになり、
⚫︎仕事が正確に、
⚫︎仕事の質が高くなる
⚫︎結果、原価や経費が下がる
だから、少人数でも成果が出る。
その結果、社員に高い給料が出せる。
最高の仕組み!!
最高の業務システムは、
入社して「業務システム」にログインすると
⚫︎直ぐに仕事ができる。
⚫︎覚えなくても仕事ができる。
⚫︎優秀な即戦力ですぐに
⚫︎退社するとその社員からノウハウがなくなる仕組み。
13−2)業務効率化「未来業務」→社員の声と経営判断のギャップ
現場の社員たちから「忙しいので人を増やしてほしい」
という要望を受けることは、どの企業でもよくあることです。
確かに、目の前の業務が多すぎて手が回らないと感じている社員にとって、
人手を増やすことは切実な願いです。
しかし、経営者やマネージャーという視点で見ると、
そこには慎重な判断が必要です。
もし仮に人員を増やしたとしても、
売上がそのままであれば、
一人あたりが生み出す利益は確実に減少します。
つまり会社全体の利益率が下がり、
結果として社員一人ひとりの給与アップが難しくなってしまうのです。
それどころか、下がる場合もあるのです。
ところが、現場の社員はそのような視点で、
会社の利益構造を捉えることは少なく、
「人が足りない」という目先の感覚だけで訴えてくることが多いのが実情です。
このようなときこそ、私たち経営者が果たすべき役割は、
「単に人を増やす」のではなく、
業務の効率化を通じて、仕事をより楽に・スムーズに進められるように整備することです。
その上で、成果を出してくれた社員にはきちんと還元し、
「楽になって、さらに給与も上がる」という理想的な好循環を目指すことが重要です。
<業務改善と業務効率化の本質>
「業務改善」や「業務効率化」という言葉はよく耳にしますが、実際に現場でどう取り組むか、具体的なイメージを持っている人は少ないかもしれません。では、業務改善とは何を意味するのでしょうか。
それは、以下のような成果を目指す取り組みです。
簡単にいうと
⚫︎少ない人数でできる。
⚫︎速くできる。
⚫︎簡単にできる。
⚫︎自動化できる
詳細にいうと
•同じ業務量を、より少ない人数でこなせるようにする
•作業スピードを上げて、短時間で完了できるようにする
•複雑な手順を見直して、誰でも簡単にできるようにする
•さらには、業務そのものを自動化・デジタル化して、人が介在しなくても成果が出る仕組みをつくる
これらを実現することで、会社全体の利益率が上がり、社員への給与アップや新しい投資に回せるリソースが生まれます。
⸻
<業務改善で取り組むべき8つの切り口>
業務改善の手法としては、次のようなアプローチが挙げられます:
• 仕組み化:業務の流れを定型化し、属人化を排除する
• 仕掛け化:自然と仕事が進むような環境・仕掛けを用意する
• システム化:ITツールやソフトウェアで作業を効率化
• クラウド化:業務の情報をクラウドで一元管理し、どこでも対応できるようにする
• AI化:判断や作業の一部をAIに任せる
・ロボット化:作業の一部をロボットに任せる
• そもそもその仕事をなくす:不要な業務を思い切って削減する
こうした施策を組み合わせることで、業務の質もスピードも向上します。
⸻
<業務改善の進め方:4つのステップ>
業務改善には明確なステップがあります。順番を意識して進めることが成功の鍵です。
1. 業務表の作成
まずは、全社員の業務を洗い出し「業務一覧表」を作成します。
2. 業務の分析
誰が、どのクライアントの、どんな業務に、どれくらいの時間をかけているのかを記録・集計します。Excelやスプレッドシートなど、誰でも使えるツールで構いません。
3. 業務の解析
分析データをもとに、どこに無駄があるか、どの業務が利益につながっていないのかを特定します。時間単価・利益率・作業の重複などの視点で深掘りします。
4. 改善の実行
改善すべきポイントが明らかになったら、前述の7つの手法の中から最適な方法を選び、段階的に導入していきます。
ーーーーーーーーーー
<業務改善:まとめ>
社員からの「人を増やしてほしい」という声に対しては、安易に人員を追加するのではなく、まずは業務の効率化と改善に取り組むことが先決です。
働き方を見直し、無駄をなくし、生産性を高め、結果として働く人にとっても、会社にとっても“ラクになって儲かる”状態を実現する。それが、これからの経営に求められる「賢い選択」です。
<はじめかた>
業務改善の第一歩は「全社員の業務の見える化」から
業務改善を実施するにあたり、最初に必ず取り組むべきステップがあります。
それは、**「全社員の業務内容を徹底的に分析すること」**です。
どこに無駄があるのか、どこを効率化できるのか、そして何をシステム化すれば良いのか――これらを見極めるためには、まず現状を正確に把握する必要があります。
■ ステップ1:業務の棚卸し(やっていることの洗い出し)
まずは、すべての社員に対して、自分が日々行っている業務を洗い出してもらいましょう。
ExcelやGoogleスプレッドシートなどのシンプルなツールを使って、次のような項目で入力してもらいます:
•担当者の名前
•担当しているクライアント名
•具体的な業務内容(例:資料作成、打ち合わせ、請求処理など)
•各業務にかかっている所要時間(1日または1週間単位)
•業務頻度(例:毎日、週1回、月1回など)
■ ステップ2:データの集計と可視化
社員が入力した業務シートを集計し、部署別・業務別に時間・コストの傾向を見える化します。
これにより、次のようなことが見えてきます:
•特定のクライアントに過度に時間がかかっている
•同じような作業が複数人によって繰り返されている(重複作業)
•明らかに時間効率が悪い業務が存在している
•属人化していて他の人が対応できない業務がある
■ ステップ3:業務の解析・改善ポイントの抽出
集計・可視化されたデータをもとに、改善すべきポイントの優先順位をつけていきます。
たとえば、
•「この業務はテンプレート化すれば10分の1の時間で済む」
•「この手順はシステム化すれば人的ミスをゼロにできる」
•「この業務はやめても支障がないので、完全に削除できる」
など、**“やめる・仕組みにする・自動化する”**という視点で整理するのがポイントです。
⸻
このように、最初の段階で社員のリアルな仕事の中身をデータとして“見える化”し、冷静に分析することが、業務改善・効率化のスタートラインです。
現場の感覚だけでは見えてこない、会社全体の無駄やボトルネックが明らかになります。
業務効率を高めて、働き方をラクにしながら、成果を最大化していくためには、このステップを丁寧に行うことが不可欠です。
⸻
13−3)業務効率化「未来業務」→「具体的方法」
一般的な企業は「高額パソコン・ビックWモニター」は、経費の無駄。
未来経営では、「高額パソコン・ビックWモニター」は、業務効率の最初。
<業務効率化>
⚫︎高速パソコン使っている
⚫︎高速パソコン支給している
⚫︎高速パソコンを新卒や進入社員に至急している?(仕事の遅い人ほど高速化が大事)
⚫︎モニターはビックモニター
⚫︎モニターはWモニター
⚫︎モニターは縦おき(二台以上なら)
⚫︎チャットGPTを使う
⚫︎チャットGPTの有料版を使う
⚫︎チャットGPTの「マイGPT」を使う
⚫︎会社資産(ノウハウ)をチャットGPTの「マイGPT」で使う
⚫︎パソコンは1人に数台あるか
⚫︎高速プリンター
⚫︎高速サーバー
⚫︎高速AIサーバー
⚫︎仕組み化
⚫︎仕掛け化
⚫︎システム化
⚫︎自動化
⚫︎IT化
⚫︎クラウド化
⚫︎AI化
⚫︎外注化
⚫︎秘書をつける
⚫︎PDCA→HDCAP
⚫︎その仕事を、そもそも無くす。
マニュアルを作って、それを守らせるのではない、
会社に入ると、自然に仕事ができる。
ワクワクしながらできる。
★業務効率化を考えるの社長の仕事
★業務改善を必ず行う
★給料マップ」を作る?
<幹部管理>
幹部は育つと辞めていく!
ライバル会社に移ったり、
下請けやクライアントに移る場合がある。
→組織・チームが壊れる
→辞める前に、独立させる。(分社化)
<会社管理>
⚫︎オフィス環境
⚫︎業務環境
⚫︎組織環境
★任せるとは、見守りながら引き上げること!
成長したから、任せるのではない。
任せた瞬間から、成長を始める。
任せるとは「放置」「手を離す」ことではない。
「指導」と「監視」と「褒める」
divDIV:高速HDCAP:https://www.clipinc-web.com/miraikeiei#13-4
13−4)業務効率化「未来業務」→分解・分散 「PDCA」→「DCAP」→「HDCAP」→「高速HDCAP」
<会社成長>の成長は、スピード・スピード・スピードです。
仕事のスピードを上げるのは、分解と分散です。
仕事や人生が思うように進まなかったり、大雑把になったり、
運が悪い、引き運がなかったり、
そんな時は、仕事を分解して、仕事を詳細に分けて、
細かいステップに分けましょう!
細かくすることで、仕事が進んでいるように思えます。
また、その結果、実際に仕事が進むことができます。
その実績と自信が、仕事を更に加速化させます。
実績と自信によって、チャンスも運も向いてきて、
奇跡も起こりやすくなります。
運も細かく分解することで、運のいいことが起こる事が増え、
引き運が芽生えて、運引きよせグセが付き、
新たな運を引き寄せやすくなります。
そうすることで、自分が運のいいことに気がつき始めます。
自分を騙すことで、脳も騙され、
加速するのです。
また、仕事を数値化して、進行状況を、パーセンテージ表記すると、
悪いこともいいことも、両方わかり加速します。
さらに数値化は、自分だけじゃなく、
周りにも、伝わるようにしましょう!
スタッフにも数値を見せることで、達成感があり、
細かい達成が大きな達成に繋がります。
★仕事と人生の細分化・分解化・分散化
★項目やステップ、スケジュールの細分化
★仕事や人生の数値化
<会社成長>仕組み化
全てのことを自分だけでするのではなく、
自分や自社を分解して、仕事や業務を分散しましょう!
仕事や業務は、専門家やプロ、担当者に任せて、
集中させて、行ってもらいましょう!
人は、1つのことに集中するほうがパフォーマンスが上がります。
自分は、得意なことや、経営だけに集中して、
他のことは、担当者や秘書や外注に任せましょう!
自分の片腕が欲しい方は、
自分と全く同じことを
「同じ量」を「同じスピード」「同じ熱量」で
できる人を探しているでしょう!
でも、そんな人は見つかりません。
「この人だ!」と、思っても、何かがたりなく、
欠点ばかり見つけてしまいます。
そこで、自分を1人の人で探すのではなく、
自分を分解して、探すのです。
例えば、自分を「営業」「経理」「人事」「業務」の
4つに分解して、それぞれをそれぞれのの得意な人に任せましょう!
自分より経理が2倍できる人を探すのです。
20%でもいいです。
そして、自分の苦手な物ほど、人に任せましょう!
もし、自分の得意なことがあれば、自分はそのことに集中しましょう!
もし、自分を4つに分解して、
人に任せるなら、
それぞれを自分ょり20%できる人に任せましょう。
そうすると、
1.2×1.2×1.2×1.2=2.07になり、約2倍以上になり、
たった、4人で自分の片腕が2人雇えたことになになります。
もし、2倍できる人を4人見つけたら、
2倍×2倍×2倍×2倍=16倍。
たった、4人で自分の片腕が16人雇えたことになになります。
<分散化のメリット>
⚫︎自分を増やせる
⚫︎同時に進行する
⚫︎自分がいなくても仕事が回る
⚫︎リスクヘッジ
⚫︎会社を売却できる。
<会社成長>行動化(PDCA→DCAP)
とにかく、今スグ行動してみる。
⚫︎実際に少しやってみる
⚫︎人にプレゼンする
⚫︎人と話す
⚫︎人に会ってみる。
⚫︎誰かとお茶する。
⚫︎ネットワーク広げる。
⚫︎情報を集めるのではなく、自分から情報を発信してみる。
現在「PDCA」が大事だと言われています。
しかし、「プラン」をアレコレ考えるより、
直ぐに行動に移し、「何かをやってみる」ことが大事です。
机上空論:「机上の空論」にならないようにしましょう!
<高速HDCAPとは何か?>
「HDCAP」は「PDCA」の進化系として提唱します。
「HDCAP(ハイディーキャップ)」という概念に由来しています。
<通常のPDCA>
(1)Plan(計画する)
(2)Do(やってみる)
(3)Check(検証する)
(4)Action(改善する)
↓
「高速HDCAP」は、「仮説検証型・即実行型・未来設計型」の思考サイクルで、
「行動しながら仮説を作る」「行動から検証し、最後に計画を立てる」逆転型の考え方です。
↓
<高速HDCAP>
(1)Hypothesis(仮説)
(2)Do(やってみる)
(3)Check(検証する)
(4)Action(改善する)
(5)Plan(計画する)
これが「HDCAP」は「PDCA」のさらにその先で、
「H=Hypothesis(仮説)」が先頭にくることで、
「仮説→やる→検証→改善→設計」までを連続して
しかも高速で何度も回す。
「高速HDCAP(高速ハイディーキャップ)」と呼びます。
<HDCAPの目的>
⚫︎机上の空論を避ける
⚫︎即行動からのリアルな結果重視
⚫︎未来逆算型の実践サイクル
<まとめ>
「HDCAP」とは、「仮説→行動→検証→改善→計画」という順番で、
未来に向けたリアルな成長や実験的戦略に使う超実践型フレームワークです。
⚫︎未来経営「戦略サイト」の作り方!
14−1)デジタル「未来思考」【戦略的サイト】の作り方
デジタル(未来思考)とは、
コンピュターとITとキラーサイトとクラウドシステムと社内システムとAIを
上手に活用する!
ここでは、ホームページ構築について語ります。
更に、普通のホームページではなく
「戦略的ホームページ」をつくって、
活用しようというブロックです。
<戦略的ホームページの基本>
⚫︎人に変わって、24時間・365日営業してくれる。
⚫︎地域だけじゃなく、世界中からアクセスされる
⚫︎戦略的サイトだと、簡単に受注してくれる。
⚫︎自動で、解説・受注してくれる。
⚫︎マンションでも2週間で受注できる
⚫︎人材求人・人材教育も行ってくれる
⚫︎SEOをしなくても。戦略的ホームページだと、自然にSEOが効くようになる。
★金額の高いものは、スマホよりホームページで受注!
<戦略的ホームページの特徴>
⚫︎制作事例ではなく、成功事例が載っている。
⚫︎成功事例のリストが「V字回復」で4個以上、期間、改善前、改善後、成果が載っている。
⚫︎目的・目標が掲載されている
⚫︎コミット(相手の利益)が載っている。
⚫︎成功事例の詳細が「V字回復」で4個以上、期間、改善前、改善後、成果が載っている。
⚫︎会社概要がページ内にある。(サイト内にある。)
<統一感>
一貫設計いて、全てが「統一」し「統一感」していることが大事です。
ーーーーーー
「広告」ー「告知」ー「サイト」ー「SNS」ー「チラシ」ー「店内」ー「空間」ー「演出」ー「クレド」ー「スタッフ」ー「接客」ー「会話」ー「商品・サービス」ー「包装」ー「お渡し」ー「体験」ー「感動」ー「記憶」ー「共感」ー「再来店」ー「ファン化」ー「レビュー」ー「投稿」ー「紹介」ー「拡散」ー「共鳴」ー「伝播」ー「ブランド化」
ーーーーーー
⚫︎すべてが「一つの世界観」で「一貫設計」されていることで、顧客の信頼と共感が生まれます。
<戦略的ホームページの作り方>
⚫︎サイトはターゲットによって分ける「新規顧客サイト」「リピート顧客サイト」
⚫︎サイトは目的やコンテンツによって分ける「会社概要サイト」「商品サイト」「求人サイト」「ブログサイト」
⚫︎サイトはLPではなく、独立したサイトにする。(サブドメインではダメ)
⚫︎ドメインも目的によって分ける。独自ドメイン
⚫︎メニューは少なく、バナーやリンクも少なく、シンプルに!!
<求人サイト>
⚫︎写真がいっぱい載っている(見学したみたいに)
⚫︎収入事例が、収入実績が具体的に掲載されている。
<独立サイト「独自サイト」の理由>
とにかく、普通のホームページは、付け足しでぐちゃぐちゃです。
⚫︎1つだけのサイトだと、メニューも多い。ボタンも多い。バナーも多い。リンクも多い。
⚫︎ターゲットが不明確。関係ない情報が多すぎる。
⚫︎情報が多すぎるのに、欲しい情報は少ない。情報と写真は多く。
⚫︎内部リンクも多く、外部リンクも多く、どこから飛ばされるが戻って来れない。
⚫︎LPでは、真剣さ、本気さが伝わってきません。
⚫︎サブドメインもです。リンクを辿っても関係ない情報!
⚫︎独自ドメインが、あなたの「本気」「真剣」が伝わります。
⚫︎会社情報でもクライアント、パートナー、求人、株主、向けなどによって情報は違うはず。
→決まったターゲットにターゲットだけの情報を、
→質の良い量のある(テキストと写真)を届けましょう!!
→シンプルで情報が多い。
14−2)デジタル「未来思考」【AIを活用する】
<AIとともに>
私は11歳でマイコンを組み立て、
プログラマーになりました。
21歳でアップルのマッキントッシュをを購入し、
22歳でサンフランスシコ・シリコンバレーを訪れ、
23歳でアップルセンター天神(福岡)の店長に就任しました。
23歳、当時から、作ってもらった専用機器で、脳波で電子機器を動かす研究を
自宅で行っていました。
その頃から「A I」に触れていました。
ただし当時の「AI」は、あくまで、
「データベースから情報を引き出す」ようなイメージであり、
まさか「チャット」や「創作」や「アート」ができるほど発展するとは想像もしていませんでした。
しかし今や、AIは「歌詞を作り」「曲を書き」「歌い」、
さらには「アートで賞を取る」までに進化しています。
まさに、恐るべき進歩です。
しかも、開発者でさえその仕組みを完全には理解していません。
「重力」「量子もつれ」「DNAジャンク領域」「時空」「AI」「プラセボ効果」など、
私たち人類は、いまだに完全には解明できない力を使いこなし、
ある意味で『神「自然界の力」』を
活用しているのです。
私たちも「神」の「力」を使いましょう!
<AIの力を活用しよう!!>
⚫︎AIを上手に活用しましょう!!
さらに先、
人類の人口は、将来的に100億人に達すると言われています。
その頃、ロボットも100億台になるかもしれません。
多分いずれ
「人間の仕事は100%なくなる」
と私は考えています。
では、人間はそのとき何をするのか?
昔、アテネ市民(特に裕福層)は、働かなくても
「土地・奴隷・商売の利益」で暮らしていました。
よって、「一部の特権市民は、仕事をせずに生きていた」と言えます。
そして彼らは、主に「政治・軍事・哲学・芸術・趣味」に従事していました。
私たちも、いずれ「哲学」や「芸術」・「趣味」に従事する時が来るかもしれません。
14−3)デジタル「未来思考」AIとの戦い方! 「ITとAIで加速する未来イメージ「全ての仕事は100%なくなる」
AIとの戦い方|<一般人がAIに勝つ4原則>
1)【構造を作る】「問い設計力」で勝つ
AIは「回答」は得意でも、「問い」や「設計」は苦手です。
「何を聞くか」「どこまで聞くか」「誰向けか」など、“設計思考”が勝敗を分けます。
2)【感性でつなぐ】「感性・共感力」で勝つ
AIは「理屈」は得意でも、「気持ち」「空気」「違和感」には弱い。
人間にしかできない“共感力・言語化力・気づき”が、これからの価値になります。
3)【ストーリーにする】「再構成力」で勝つ
単発情報ではなく、思考・提案・背景・感情を「ストーリー化」して届ける力。
⚫︎ 違和感を察知する
⚫︎ 相手の気持ちを読む
⚫︎ 言葉のトゲを丸くする
こうした「人と人との間の力」は、圧倒的に人間の領域です。
「言葉で人を動かす」ことは、AIが最も苦手とする領域です。
4)【組み合わせる】「複合力」で勝つ
AIだけ、デザインだけ、営業だけでは勝てません。
勝つのは、「複数の価値を掛け合わせて、成果をつくる人」。
⚫︎ AI × 感性 × ストーリー
⚫︎ AI × 現場経験 × 顧客心理
⚫︎ AI × マーケ × デザイン × コピー
つまり、「ハイブリッドな能力構造」を持つ人こそが、AI時代で“最強の人材”になるのです。
まとめ:「問いを設計し、感性でつなぎ、ストーリーで伝え、複数の価値を組み合わせること」
——これが、AI時代に一般人がAIに勝つための4原則です。
14−4)デジタル「未来思考」AIとの戦い方!【属人化】と【独自化】
<実践スキルまとめ:属人化から独自性へ>
実務の現場では、仕事を進める上で「属人化」と「独自性」の両方が大きなテーマになります。
この二つをどう整理し、どう活かすかによって、チーム、部署、組織、会社の力が大きく変わってきます。
⚫︎「属人化」(属人性)について
属人化とは、経験や過去の蓄積、つまり「事例」や「経験」をその人の中にため込んでいる状態です。
ここには「ミスの記録」「注意事項」「失敗事例」「成功事例」といったものが含まれます。
たとえば、ある人が過去にトラブルを経験して「こうすると危ない」という学びを得たとします。
それを本人だけが知っている状態だと、その人がいなくなった時に
チーム、部署、組織、会社全体としての再現性が失われます。
逆に、それを「共有事項」として仲間に伝えられると、
それは「ナレッジ(知識)」として蓄積されます。
つまり属人化のリスクを、チーム、部署、組織、会社の力に変えるためには
「記憶」から「記録」と「共有」が不可欠なのです。
⚫︎「独自化」(独自性)について
独自化とは、単なる経験の積み重ねにとどまらず、
そこから生まれる「工夫」や「応用」のことです。
ここで大事になるのは、「どう改善したか」「どう対処したか」「どんな手順を踏んだか」という、
具体的で実践的なやり方です。
もしくは、その経験時に「どう改善したらいいのか」「どう対処したらいいのか」「どんな手順を踏むのか」
と、言う未来への方法です。
これらは一人ひとりの工夫の中から生まれますが、それを言語化して整理し、
「ノウハウ」としてまとめることで、チーム、部署、組織、会社の財産になります。
たとえば「失敗した時にこうリカバリーした」「お客様対応でこう工夫した」
「業務効率を上げるためにこう手順を変えた」といった経験は、
他の人にとっても役立つ実践知になります。
⚫︎「ナレッジ」と「ノウハウ」の違い
ここで区別したいのは、「ナレッジ」と「ノウハウ」の関係です。
ナレッジは「過去の記録・学びの共有」、いわば経験のストックです。
ノウハウは「未来に生かすための具体策」、つまり実際のやり方そのものです。
両方が揃ってはじめて、チーム、部署、組織、会社は学びを「次の行動」に活かせるようになります。
ーーーー
【属人化】(属人性)
過去蓄積(事例・経験)=ナレッジ
→「ミス・注意事項・失敗事例・成功事例」の共有事項
【独自化】(独自性)
対策蓄積(工夫・応用)=ノウハウ
→改善案・対処方法・手順・対策・やり方」の具体的方法
ーーーー
⚫︎まとめると
「属人化=過去の経験を知識として共有すること」
「独自性=その知識を工夫と応用に変えて方法論にすること」
この二つを循環させることが、実践スキルを磨く最大の近道になります。
つまり、失敗も成功も全て「共有すれば資産」になり、それを工夫に変えることで「競争力」に育っていくのです。
属人化に埋もれてしまう知識をチームで開放し、独自性を加えて進化させること。
14−5)デジタル「未来思考」【機材性能アップ】
デジタル(未来思考)とは、
コンピュターとITとキラーサイトとクラウドシステムと社内システムとAIを
上手に活用する!
私は、最初、高いコンピューターやモニター、プリンターは、
経費の無駄だと思ってました。
なので、優秀な人ほど、
高速なパソコンを提供していました。
特に、新卒は、仕事もできないので、
勿体無いと、古いパソコンを
当て得ていました。
しかし、途中で、気がついたのです。
仕事ができない。
仕事の効率が悪い者ほど、
高速で、速いパソコンを提供し、
大きなメモリで更に高速化し、
ビックモニターを2つ設置するのだと、
すると、新卒でも、
効率が良くなったのでした。
15−1)市場戦略「未来市場」マーケット戦略
未来市場」と聞くと、多くの人は「世界展開」「海外進出」といったイメージを思い浮かべるかもしれません。
しかし、真の意味での市場化とは、単に国境を越えることだけではありません。
例えば、地方にある小さな企業が、日本全国に向けて商品やサービスを提供するようになった時点で、
それはすでに立派な「市場化」の一歩だと考えるべきです。
実際、地域限定のビジネスと全国展開のビジネスとでは、その市場規模に圧倒的な違いがあります。たとえば、自分の住んでいる県の人口と日本全国の人口を比べてみてください。規模によっては50倍、あるいは100倍以上の差があることも珍しくありません。このように、マーケットの広がりがそのままビジネスの成長ポテンシャルに直結するのです。
よく、まずは「地域ナンバーワンを目指せ」と言われます。確かに局所的なブランディングや実績づくりの観点から、それも一つの戦略ではあります。しかし、地域でトップになることだけにとどまらず、最初から「全国で勝負する」という視点を持つことで、売上規模は50倍、100倍と跳ね上がる可能性を秘めています。だからこそ、ビジネスを始める段階から、全国展開を強く意識すべきなのです。
⸻
【全国展開している企業との連携が、成功の近道になる】
仮に、あなたの会社が「ホームページ制作」や「コンサルティング」といったサービス業であれば、仕事を依頼するクライアント選びも、ビジネスの成果に大きく影響します。
たとえば、ローカル市場のみで事業を展開している企業のホームページを制作するのと、全国規模で商品を販売している企業のサイトを手がけるのとでは、その報酬額や意思決定スピードに大きな違いがあります。
全国展開している企業は、売上規模が50倍、100倍にもなることが多く、予算規模も大きく、意思決定も迅速です。そのため、サービス提供側としても、プロジェクトがスムーズに進み、成果にもつながりやすくなります。
つまり、同じ労力をかけるなら、より規模の大きなクライアント、かつ成長意欲の高い企業と連携する方が、ビジネスとしての展開も速く、報酬面でも高い成果が得られます。
⸻
【世界展開も「まずはネットでテスト」する時代】
かつて、海外展開といえば、まずは大手商社に頼み、その国に拠点を構え、人材を派遣したり、現地の人材を採用してから市場に参入する、というのが一般的な流れでした。しかし、時代は大きく変わりました。
現在では、インターネットを活用すれば、初期投資を抑えつつ、世界中のマーケットに商品を届けることが可能です。まずは自社の製品やサービスを海外向けにネット上で販売してみて、どの国・地域から最もアクセスがあるのか、どこに反応が強いのかをデータで把握する。そして、反応が良かった国や地域に絞って、改めて本格的に展開していく──このように、デジタル起点で市場を探索するのが、今の時代の「世界展開」のスマートなやり方です。
この方法であれば、リスクを最小限に抑えながらも、世界中のチャンスを手に入れることができます。特にデジタルサービスやEC事業を展開している企業にとっては、この柔軟な発想と小さな実験を重ねる姿勢が、将来的な国際的成功のカギとなるでしょう。
【今の現在市場と過去市場と未来市場】
自分のビジネスの市場を、
戦略的に考えてみましょう!!
現在の市場は、きっと過去の市場です。
過去からすれば、現在は未来の市場です。
このままでは、未来も同じ市場です。
そこで、大きく変えるのです。
例え「地域N01」を目指しても、
地方では、所詮全国の2%から10%程度!
成功しても微々たる物です。
しかもノウハウが溜まったとしても、
次の戦略「全国展開」には、使えません。
「地方NO1」
↓
「県NO1」
↓
「北日本・南日本:NO1」
↓
「全国NO1」
↓
「世界進出」
は、間違っています。
ネットのなかった時代は
全国展開が難しかったので、
あっていたかもしれませんが、
それは、古い方法です。
<ステップアップ式デメリット>
⚫︎地域NO1を目指すのも全国展開目指すのも全く違うノウハウがいる。
⚫︎地域NO1での単価が安い
⚫︎地域NO1での収益が少ない(50分1〜20分1)
⚫︎地域NO1での収決が遅い
⚫︎地域NO1での決断が遅い
⚫︎地域NO1での見積もりからの受注率が低い
⚫︎ノウハウがリセットされる
⚫︎顧客リストもリセットされる
⚫︎人材もリセットされる
⚫︎仕組みも価格もリセット
⚫︎途中で資金が尽きてしまう。
そこで、最初から「地域N01」でもなく、
「全国展開」でもない。
しかも、両方のいいとこどりの
面白い方法があります。
この方法で売上を10倍から50倍に増やせるのです。
それが、「未来市場戦略」「グロースマーケット戦略」です。
15−2)市場戦略「未来市場戦略」「グロースマーケット戦略」
具体的な方法から説明します。
<サービスの場合>
⚫︎自分は地方にいて、「全国展開している企業」に自分のサービスを販売する。
<商品の場合>
⚫︎自分は地方にいて、「全国展開している企業」に自分の商品を卸す。
こうすることによって、自分自身は、
全国ネットや都心に進出しなくても、
地方にいながら全国をマーケットにできる。
<未来市場戦略:メリット>
⚫︎広い市場で戦える。「狭い市場」で戦うな
→ 人口減・エリア制限のある市場では、努力が報われない
⚫︎高額で売れる。
→年収を全国調査せよ、あなたの製品は、年収の何分の1か
⚫︎「今の市場」より「未来に拡大する市場」に乗れ
→ 成長市場を先取りし、「風に乗る」ように成長する
→人口は増えているのか? 減っているのか?
⚫︎「市場設計」を商品より先にやれ
→ 商品開発の前に、「誰に売るか=市場」を定義するのが先
⚫︎「拡張性」を最初から設計せよ
→ ローカルから都心へ、全国まで、拡張しやすい構造で設計せよ
もしくは、思い切って、
最初から自分でネットで東京・全国展開する。
すると、利益が50倍になるかも?
<都心マーケット戦略>
⚫︎自分は地方にいてネットで都心をターゲットに行う。
私は、この方法で成功しました。
私のクライアントは、東京・大阪・名古屋でしたが、
彼らが全国ネットで販売していました。
⚫︎社員は120人。95%〜99%地方にいました。
⚫︎クライアントは50社。都内中心で、95%〜99%でした。(東京・大阪・名古屋)
<ネット全国販売メリット>
⚫︎人口が多い(現在のローカルの人口と比較してみる)
⚫︎都心は単価が高い
⚫︎都心は総収益が多い(50分倍〜20分倍)
⚫︎都心は決済が速い
⚫︎都心は決断が速い
⚫︎都心は見積もりからの受注率が高い
⚫︎最初から、全国展開のスキルとノウハウが学べる。
⚫︎入金も速い
⚫︎社員の給料も増やせる
会社の最終、目標と目的! お金かorロマンか?
私は美味しい寿司屋が好きです。
どんなに儲かっていても、
その会社の株価が高くても、
⚫︎店員が魚のことを知らない。
⚫︎職人が技術がない。
⚫︎材料が悪い。
⚫︎美味しくない。
そんな店には、行きたくありません。
私は美味しい寿司屋が好きです。
私が作る会社も寿司が美味しい
高級寿司屋のような会社を目指していました。
私が作っていた会社には、
新卒への「寿司研修」がありました。
実際に高級寿司屋に行きました。
カウンターで
美味しい寿司を食べ、
最高の「ネタ」「技術」「おもてなし」を受ける研修です。
⚫︎高い原価(美味しいネタ)
⚫︎職人(素晴らしい技術)
⚫︎高品位(あったかいおしぼり)
⚫︎サービス(おしぼりが、最初、途中、最後と3回でる)
⚫︎サービス(お茶も、最初、途中、最後と種類が違う)
⚫︎綺麗な店内(ハードも大事)
⚫︎おもてなし(入り口から出口まで)
ビジネスの本質を知るためです。
出口戦略:会社のエグジット戦略:16通り
<会社のエグジット戦略>概要
会社のエグジット戦略とは、「経営の出口=終わり方」を明確に設計することです。売却(M&A)、事業譲渡、株式上場(IPO)、事業承継など、どの形で会社を手放すかを先に決めることで、現在の経営判断が変わります。未来経営では「出口戦略を先に描く」ことで、そこから逆算して、商品・組織・数字・価値を高める設計を行います。最初の「起業」より、最後の「出口」が成功の鍵。売れる会社をつくること自体が、最強の経営戦略となるのです。
<会社のエグジット戦略>気をつける事
エグジット戦略で最も気をつけるべきは、自社が「売れる会社」になっているかどうかです。創業者のカリスマや属人的スキルに依存していると、譲渡や売却が難しくなります。仕組み・業務・営業・人材が「再現可能」であることが重要です。また、財務や契約も整理されておらず曖昧だと価値が下がります。さらに、エグジットを考えるあまり短期的な利益だけを追求すると、ブランドや組織が崩壊する危険もあります。未来を見据えた「価値設計」が最優先です。
<会社のエグジット戦略:IPO>概要
IPOを目指す際に最も大切なのは、まず「会社の中身が整っているか」です。これは見た目や売上ではなく、会計・契約・人事・ガバナンス・情報管理など、すべての基盤が上場基準に達しているかということ。内部が整っていない会社は、上場できてもすぐに信頼を失い、株価が下がり、逆にダメージを受けます。次に大事なのは、「お金が集まったときにパフォーマンス(質と利益と売上)が跳ね上がる仕組みができているか」。IPOで得られる資金は、ただの燃料です。それを使って売上が10倍、100倍に伸びる「事業構造・商品構造・営業構造」を事前に整えておく必要があります。そして3つ目は、「売れる会社の資産がひと目で伝わる形でまとまっているか」。商品力・サービス品質・顧客基盤・ブランド価値・人材・仕組みなど、企業価値を明確に言語化・視覚化しておくことが、上場成功の鍵です。すべては「見える化」から始まります。
<会社のエグジット戦略>リスト版
簡単な順(基準は「準備コスト・交渉範囲・買い手との距離感・実行難易度・市場の希少性」などから判断しています。)
(1)【社内承継型(MBO)】(売先:社内)
(2)【親族承継型】(売先:親族)
(3)【パートナー企業買収型】(売先:業務提携先・長期取引先)
(4)【顧客による買収型】(売先:ヘビーユーザー・VIP顧客)
(5)【事業分割売却型】(売先:事業特化企業)
(6)【ブランド資産売却型】(売先:ブランド活用企業)
(7)【サブスク資産譲渡型】(売先:IT企業・投資家)
(8)【AI・IT資産売却型】(売先:非IT企業・自治体・海外企業)
(9)【異業種拡張型】(売先:全く別業界からの参入企業)
(10)【外部M&A型】(売先:同業他社・業界内企業)
(11)【譲渡プレミアム型】(売先:大手企業・シナジー企業)
(12)【ファンドバイアウト型】(売先:投資ファンド)
(13)【社員持株会型】(売先:社員全体)
(14)【自治体・公共団体型】(売先:自治体・公的機関)
(15)【クリエイター買収型】(売先:YouTuber・インフルエンサー・著名人)
(16)【IPO型】(売先:株式市場)
<会社のエグジット戦略>詳細版
⚫︎(1)【社内承継型(MBO)】
(売先:社内)
幹部や右腕社員に会社を譲る。一番準備が少なく済むが、信頼関係と資金設計がカギ
⚫︎(2)【親族承継型】
(売先:親族)
子どもや兄弟に引き継ぐ。経営能力の育成が最大の課題
⚫︎(3)【パートナー企業買収型】
(売先:業務提携先・長期取引先)
日頃の信頼関係から自然な譲渡が成立するパターン。取引先企業が“丸ごと買いたくなる”
⚫︎(4)【顧客による買収型】
(売先:ヘビーユーザー・VIP顧客)
商品やサービスを気に入った顧客が、事業ごと買収。クリニック・店舗でよく発生
⚫︎(5)【事業分割売却型】
(売先:事業特化企業)
いくつかの事業に分割し、売れる部分だけを売る。交渉範囲が小さくて済む
⚫︎(6)【ブランド資産売却型】
(売先:ブランド活用企業)
商標・デザイン・ブランドイメージのみを売る。会社本体は残すことも可
⚫︎(7)【サブスク資産譲渡型】
(売先:IT企業・投資家)
定期課金顧客ベースや契約収入だけを「資産」として売却
⚫︎(8)【AI・IT資産売却型】
(売先:非IT企業・自治体・海外企業)
独自の業務システムやAI設計を売る。「仕組みを売る」形式
⚫︎(9)【異業種拡張型】
(売先:全く別業界からの参入企業)
IT、介護、美容などで“ノウハウ丸ごと買いたい”異業種からの買収が増加傾向
⚫︎(10)【外部M&A型】
(売先:同業他社・業界内企業)
買収希望企業との交渉。業界理解があり、評価は堅実型
⚫︎(11)【譲渡プレミアム型】
(売先:大手企業・シナジー企業)
未来の価値や仕組みを演出し、高額で売却を狙うプレミア型M&A
⚫︎(12)【ファンドバイアウト型】
(売先:投資ファンド)
利益構造と成長性を見せ、ファンドに高額買収してもらう。資料と説明力が必要
⚫︎(13)【社員持株会型】
(売先:社員全体)
全社員による株式持分取得によって、全社共同運営型へ移行する民主型承継
⚫︎(14)【自治体・公共団体型】
(売先:自治体・公的機関)
地域密着型サービスや公共性が高い事業が、行政・自治体に吸収されるパターン
⚫︎(15)【クリエイター買収型】
(売先:YouTuber・インフルエンサー・著名人)
影響力のある個人が、ブランドや仕組みごと買収する時代。「企業 × 個人」型M&A
⚫︎(16)【IPO型】
(売先:株式市場)
最もハードルが高いが、上場により不特定多数の投資家から資金を得る
覚田語録
ここまで、読んでくれて、ありがとうございました。
大変だったと思います。
そこで、最後に、私が大切にしている
言葉やエピソードを伝えたいと思います。
<コンセプト>
それは何の為にやっているの?
本当に重要なことなの?
もともとの目的は何だったの?
いつのまに本来の目的からずれているんじゃない?
本当の目的は何だったの?
コンセプトはとても重要だと思う
僕の思考の原点。コンセプト!
<コンセプト:本文>
学生時代、ある不思議なアルバイトをしたことがあります。
それは、一人暮らしの寝たきりのお年寄りの枕元に
「非常用ブザー」を設置する仕事でした。
何百人という寝たきりのおじいちゃんの所に
ブザーを取り付けるアルバイトだ。
一人暮らしのおじいちゃんに、
もしものことが
あった時に周りの人達に知らせるために
寝室の枕元の手元にスイッチを取り付け
押すと自宅に玄関の表に付けたブザーが鳴る仕組みである。
その手元スイッチの取り付けと、
表のブザーを取り付け、
それをつなぐ配線をする仕事だ。
今思うと不思議なアルバイトだ。
1日に数10件の取り付け
1週間にわたって行った。
結局、僕はこのアルバイトを通じて
何百という寝たきりのおじいちゃんの所に行くのだった。
実際におじいちゃんの所に行くと、ひどいもんだ。
だいたい、六畳一間ぐらいの畳の間の
隅の方に布団が引いてあって、
その上で寝ているのだけれど、もう何日も動いていない感じで、
布団が引いてある畳のところがへこんでいた。
そして、布団の周りに水や紙や便器などがおいてあって、
もうしばらく、人が来ていない感じがする。凄いところだ。
そんなところにスイッチとブザーを取り付けにいく
最初は驚いていたけれど、だんだんなれていくのだった。
誰が作ったか解らないけどマニュアルがあって、
その通りにする。
手元に「押しブザー」の高さや距離などが明確に書いてある。
しかし、その通りやると、
本来の目的は達しない。
マニュアル通りにしてもおじいちゃんはブザーを押せないのだ。
だって、手が上がらない人もいれば、寝返りができない人もいて、
さらには手が握れない人もいる。
ブザーをマニュアル通りに壁の柱にねじで留めると
お爺じゃんは、ボタンを、押せない。
届かない。見えない。触れない。
しかし、マニュアル通りにやらないとお金をもらえないので、
取りあえずその通りの壁にブザーを付けて報告書用の写真を撮る。
こういう県や市の仕事は必ず報告書に写真を添付するようになっている。
そして、僕たちその後に配線を伸ばして
本来の目的であろうおじいちゃんが
押せるような所にスイッチを設置したのだ。
そして、おじちゃんと会話をして
押してもらうテストをして設置してきた。
果たしてこの行為は、委託者である
県や市、国などに対しての裏切り行為なのか?
果たして、マニュアル通りに設置することが正しいのか?
それとも、マニュアルに反して押せるようにするのが正しいのか?
これ、果たしてどちらが正解なのだろうか?
しかし、高校生の僕は思った。
「このマニュアルの通りにやってはいけない。
本来の目的を達成したい。」
本来の目的とは、
「もしものときにおじいちゃんや
おばあちゃんがブザーを押せること」
同じチームの人を説得し2度手間になるけど
僕たちは続けた・・・・
このマニュアルに大きな問題がある。
そして大事な言葉が抜けている。
「コンセプトだ!!」
ブザーの設置の高さや長さなどばかり書いてあって、
肝心の「おじいちゃんがブザーを押せること」
と、いう言葉が抜けている。
他のチームの人に聞くと、
「マニュアル通りにした。そうしないとお金がもらえないから」と言っていた。
しかし、それでは何人かのおじいちゃんはスイッチを押せない
実際には何の役にもたたないのだ。
悲しい・・・・
きっと、このマニュアルを作った人は
現場に来てない。実際に取り付けをしたこともない。
現場で何回も何回も検証をしていない。
きっときれいなオフィスの中の机の上で作ったんだ。
本当の現場のおじちゃんと話したことも
無い人が作ったのだ。
そう確信してしまった。
なぜなら、数人の設置をやってみればこのマニュアルの
問題は明らかにわかり改善できると思ったからだ。
しかし、このシステムにはもっと大きな
根本的な問題があった。
僕たちは、通電テストの為に家毎に
何回かブザーを鳴らす。
最初は、誰かがびっくりして、
実際に家に飛び入ってきたり、
通報されたり、救急車や警察が来たら
嫌だな~~と、思って
チームのひとりが表に立って見張っていて
周りを見ながら実験をしていた。
設置の際もなるべく音が鳴らないように
しながら接続し苦労して設置していた。
しかし、しばらくすると
見張りがいらないことに気がついた。
だって、ブザーが鳴っても誰も出てこないし、
誰も助けにも来ない。
救急車もこない。警察も来ない。
なのできっと通報もされなかったんだろう。
いったい、このシステムは誰のために、
何のためにやったものなんだろう。
僕たちは結構儲かったが、
その上の人はもっと儲かったと言っていた。
きっと、その上は、
もっともっと
儲かったんだろうなぁと~、
と今の僕は思う。
このシステムは崩壊している。
本来の目的である
「一人暮らしのおじいちゃんの
緊急時に対応できるシステム」が、
途中からは目的がブザーを
ただ取り付ける仕事に変わっていた。
このプロジェクトにはコンセプトが無い。
コンセプトが書かれていない。
マニュアルには、スイッチとブザーの
取り付け方が書かれているだけだ。
逆に報告書に関しては細かく指示があるらしい。
そもそも「何のために取り付けるのか?」
「取り付けたあとの周りへの対応は?」
などは、何も書かれていない。
結局、このプロジェクトは最終的な目的。
「おじいちゃんを助ける」
一番大事なコンセプトを忘れてしまって、
目的のすり替えが起こってしまったのだ。
僕は絶対に自分がそんな風になりたくない。
そんな仕事をしたくない。
その為にいつもコンセプトを大事にしよう
と、思うようになった。
コンセプト
コンセプト
コンセプト
大事なのは、コンセプト(目的と目標!)
ーーーーー
<コンセプト:まとめ>
「それは、いったい何のためにやっているのか?」
「それは、本当に重要なことなのか?」
「そもそもの目的は、何だったのだろう?」
私たちは、いつの間にか“本来の目的”から外れた行動をしてしまっていることがあります。
気づかないうちに、目先の作業や形式だけにとらわれ、
なぜそれを始めたのかという“原点”を見失ってしまうのです。
だからこそ、私は何よりも「コンセプト」を大切にしています。
それは、すべての思考や行動の出発点であり、軸になるものだからです。
コンセプトは、僕の思考の原点です。
⸻
<コンセプトが欠けると、目的がすり替わる>
マニュアルには、スイッチの設置位置や角度、距離などの**「手順」ばかりが書かれており、
最も大事な「誰のために、なぜこのブザーを取り付けるのか」という“目的”**が、どこにも書かれていませんでした。
他のチームの人にも聞いてみましたが、
「マニュアル通りにやらないとお金が出ないからね」と言うだけ。
でも、それではブザーを押せないお年寄りがたくさん出てきてしまう。
つまり、まったく意味のないシステムになってしまうのです。
きっとこのマニュアルを作った人たちは、現場に来たことがないのだろう。
お年寄りと直接話したことも、寝室の空気を感じたこともないのだろう。
ただオフィスの机の上で、設計図と数字だけを見ながら作ったのだと思います。
現場に一度でも足を運び、数件でも取り付けを経験すれば、
このマニュアルの欠陥にはすぐに気づけたはずです。
⸻
<コンセプトを忘れないために>
この経験を通じて、僕は強く思いました。
コンセプトがなければ、組織もプロジェクトも必ず崩壊する。
何のためにやっているのか?
誰のための仕事なのか?
その“原点”を忘れてしまうと、仕事はただの作業になり、
大切な人の命さえ守れない仕組みになってしまいます。
だからこそ、私はどんな仕事をする時も「コンセプト」を何よりも大切にすると決めたのです。
⸻
コンセプト。
コンセプト。
コンセプト。
――すべては「目的」と「意味」から始まる。
そしてそれを忘れないこと。
それが、僕の働く理由です。
<起業コンセプト>
起業は何のためか?
⚫︎自分のためか?
⚫︎顧客のために働くのか?
⚫︎社員の暮らしを良くしたのか?
⚫︎投資家のために働くのか?
会社に利益ができた時、
⚫︎社員にボーナスを渡したいのか?
⚫︎自分の収入を増やしたいのか?
⚫︎顧客へのサービスを強化するのか?
⚫︎投資家たちにお金をわたすのか?
あなたの大事な順番を考えておきましょう!
<起業コンセプト>
起業した時の気持ちをまとめておきましょう!
仕事は、家族のためか?
僕も最初、そう思ってました。
→今は仕事は私の趣味だと思っています。
→自分のクリエイティブを謳歌できる場所です。
<3本の矢>
戦国大名「毛利元就」が、自分の三人の息子に伝えた団結の教えが由来です。
長男:毛利隆元(たかもと)、
次男:吉川元春(きっかわ もとはる)、
三男:小早川隆景(こばやかわ たかかげ)、
この3人は、のちに「毛利三兄弟」として名将と呼ばれる存在になります。
戦国時代、中国地方を治めた名将・毛利元就(もうり もとなり)は、
老境に差しかかったある日、自分の三人の息子――
毛利隆元、吉川元春、小早川隆景を呼び寄せました。
そして、それぞれに一本の矢を手渡し、
「この矢を折ってみなさい」と言いました。息子たちは簡単に矢を折ることができました。
次に、今度は三本の矢を束ねて渡し、「この三本の矢を一緒に折ってみなさい」と命じました。
三人は交代で力を込めて折ろうとしましたが、束ねられた矢はびくともせず、
誰一人として折ることはできませんでした。
その様子を見た元就は静かに語ります。
「一本の矢は簡単に折れてしまうが、三本束ねれば折れない。
お前たち三人も同じだ。兄弟が力を合わせ、心を一つにすれば、
どんな困難も打ち破ることができる。だが、一人でも離れれば、たちまち力は弱くなってしまう」
この教えは、やがて「三本の矢の教訓」として広く語り継がれ、
**「団結の力」「協力の重要性」**を象徴する日本の名言として、
現代まで残ることになりました。
現代においてもこの教えは色あせることなく、
ビジネスにおけるチームワーク、家族や組織の絆、さらには国家戦略における多角的施策の比喩としても用いられています。
たった一人の力では届かない目標も、信頼し合う仲間と力を束ねれば、実現できる。
それが、「三本の矢」に込められた、時代を超えた普遍のメッセージなのです。
<現代版「3本の矢」>
かつて「三本の矢」といえば、毛利元就の逸話が象徴するように、
同じものが3つ揃えば、それは束ねることでより強くなるという、
団結の象徴として語られてきました。
確かに、その時代においては「同質の力を重ね合わせて強くする」
という発想が重要だったのかもしれません。
しかし、現代の社会、そして組織やチームが直面する課題は、複雑で多様です。
だからこそ、私が考える「現代の三本の矢」とは、**“同じ矢”ではなく、
“異なる3つの特性を持つ矢”を束ねること”**なのです。
異なるもの同士が融合し、補い合うことで、単独では到達できなかった次元の強さを発揮する。
これこそが、今の時代における「最強の矢」だと考えています。
たとえば、建築の世界において代表的な「鉄筋コンクリート」。
これは、**圧縮には強いが引っ張りには弱い“コンクリート”**と、
**引っ張りには強いが圧縮には弱い“鉄筋”**という、
性質のまったく異なる2つの素材を組み合わせることで生まれた構造です。
それぞれが単体で用いられたときには不安定でも、
互いの弱点を補い合うことで、比類なき強度を発揮する――まさに現代の智慧です。
この考え方は、人と人との関係にもそのまま当てはまります。
3人の人間が、まったく異なる個性、異なる価値観、異なる強みと弱みを持っているとします。
一見するとバラバラで、噛み合わないように思えるかもしれません。
しかし、お互いの「強みを活かし、弱みを補い合う」という関係性が築かれたとき、
そのチームは、均質な3人では絶対に生み出せない力を発揮するのです。
つまり、**現代の三本の矢とは、「異なる3つの力の融合」**です。
同じではなく、違うからこそ意味がある。
反発するのではなく、噛み合うことで強くなる。
多様性を恐れず、違いを歓迎し、組み合わせることで、私たちはこれまでにない強さを手に入れることができます。
<弱音を吐こう>
人に強い材料と聞くと、普通は鉄と答えると思う。確かに鉄は強い。
しかし途中まで硬いが折れる時はパキンと折れる。
しかし、たけの場合はどうだろう。
竹はすぐに曲がり始める。ある意味弱い。
しかし、曲げても曲げても曲げても折れない。
これこそが本当に強いと言うんじゃないだろうか。
要は、本当強いとは、すぐに曲がることではないのかのか?
仕事で、言うと、仕事仕事与えた時、「無理して自分が全部やります」
と言うのは強くて格好はいいが、結果的にできなかったり、納期に間に合わない場合。
弱音を吐かずひたすら頑張る。ことより、少しやってみて、難しいと思ったら途中で投げ出すことより
自分には難しそうだと呟いたりして、周りの何かを活用するパソコンやシステム、IT、クラウド、AIなど。
それでも難しそうだったら、周りの人たちに頼みながら、
いろんなものに助けを求めながら、最終的な結果のレベルを上げあげたり、
納期を守ったり、ことが大事なんじゃないだろうか。
<弱音を吐ける人こそ、本当に強い>
「強い素材は何ですか?」と聞かれれば、多くの人は「鉄」と答えるかもしれません。
確かに、鉄は非常に硬く、強固なイメージがあります。
しかし、鉄には“ある特徴”があります。
それは、折れる時にはパキンと突然、脆く折れてしまうことです。
では、「竹」はどうでしょうか?
竹は強風に吹かれればすぐにしなる。
一見すると弱く、頼りないように見えます。
しかし、実際には――いくら曲げても、なかなか折れません。
つまり、「強さ」とは、硬さや頑丈さだけではない。
“しなやかさ”や“折れずに耐える柔軟さ”こそ、本当の強さなのではないか?
そんなことを、私はよく考えるのです。
⸻
この考え方は、仕事にも通じます。
仕事を任されたとき、
「自分が全部やります!」「絶対にできます!」と宣言する人は、一見頼もしく、強く見えるかもしれません。
でももし、期限に間に合わず、結果も中途半端になってしまったら――
それは本当に“強い人”と言えるのでしょうか?
実は、本当に強い人とは、「弱音を吐ける人」なのだと思います。
たとえば、仕事に取りかかってみて「これはちょっと難しそうだな」と感じたとき、
すぐに「助けてください」と言わなくてもいい。
まずは、自分なりにできるところまでやってみる。
でも、限界が近づいた時には、
「これは自分だけでは厳しいかもしれない」と口に出すこと。
それが、“しなやかに曲がる竹”のような強さです。
⸻
現代の働き方では、便利なツールや支援がいくらでもあります。
IT、クラウド、AI、システム――
すべて「助けてくれる道具」です。
それを素直に活用すること。
周りの人に相談し、協力を仰ぎ、チームで仕上げること。
それによって、最終的により高い成果が出せたり、納期を守れたりするのであれば、
それこそが、真に「仕事ができる人」ではないでしょうか?
⸻
無理して折れるより、
しなやかに曲がって、最後まで立ち続けること。
その方が、よほど美しくて、強い。
「弱音を吐く」というのは、負けでも甘えでもありません。
それは、自分の限界を知り、周囲を信じる強さです。
だからこそ、私はこう言いたいのです。
――「弱音を、吐いてもいいんだよ。」
<人生の目的>
誰もが聞きたい
神様に聞きたいよね
⚫︎人生の意味
⚫︎人生の目的
⚫︎人生の生きる意味
⚫︎自分の人生の意味
⚫︎人生の結論:
↓
しかし、そんなものに答えはない。
実は神様から自分に訊かれているのだ。
↓
お前は「君の人生をどうしたいの?」と、
毎日訊かれ続けている。
↓
お前の人生の
⚫︎楽しいこと
⚫︎苦しいこと
⚫︎しんどいこと
⚫︎辛いこと
は、お前の人生に
どんな意味があるのか?
ーーーーーー
どれだけ私たちが人生に絶望していたとしても、
人生はあなた絶望することは決してない。
自分が何かで悩んでいる人がいても、
人生は、さて、この局面、どう切り抜けるのか?
と、みている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<人生が辛い時・苦しい時・しんどい時・悲しい時・絶望・苦悩>
辛い時は、そのことを自分をフカン的(自己距離化)に自分を見る。
⚫︎人事(ひとごと)に考える
⚫︎これは、実験だと思うこと
⚫︎これは、調査だと思う
⚫︎人に話たら面白いかなと思う事
⚫︎未来の夢をみる
ーーーーーーーーーーーー
未来経営管理リスト&進捗状況
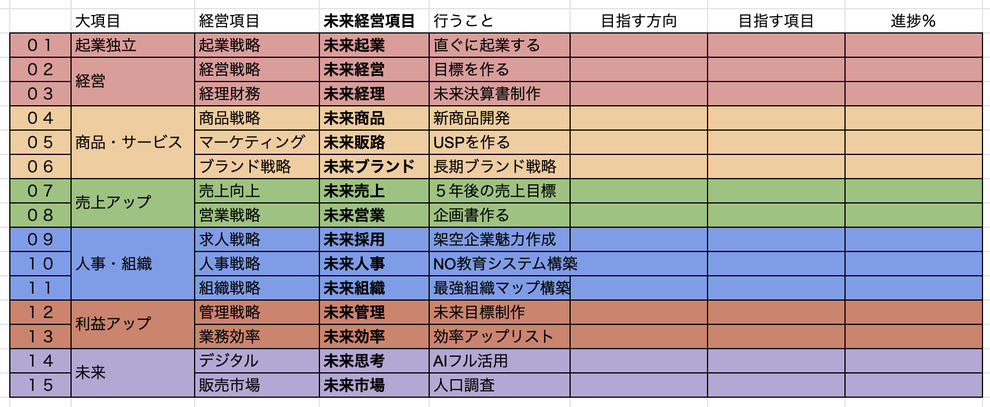
AI:未来経営「質疑応答」チャットGPT
未来経営15:運営会社
株式会社シンクディファレント株式会社(福岡)
ブランド名:クリップインク
【ダイヤモンドヘッドアカデミー】
● 経営講座
● 未来経営
● 経営アカデミー
● 起業講座セミナー
● 売り上げが上がるマーケティング
● キラーサイト&CVR
● ハワイ講座
● 越境EC講座
● 暇経営
